どうもどうも。「売国奴」のことを長らく「ばいこくやっこ」と読んでいたのがpsy-pubです。さすがに漢字を見れば意味はわかりましたが。それでも中学くらいまでは,なんとなく「とうふ」のようなイメージをもっていたのもまた事実であります。
しかし,「ばいこくど」と言われたら,3日はへこみそうな言葉の強さがありますが,「ばいこくやっこ」だと,京都の祇園あたりで,「ヘエ,今日は新しい妓が入りましたよって,ばいこくやっこッ,ばいこくやっこッ,はようこっちにッ,もうどこ行ってたんや,もうホンマ気のきかん妓で……」なんていっても通用する気がしないでもするでもありませんな。まあしないね。
などと,ついどうでもいいこと書いてしまいました。前フリ完全スルー,登録完全無料(男性会員)にて,科学を考えるシリーズ第4弾,今日はSTSであります。
●関連エントリ
現代と科学とconflict of interest
科学をわしも考えた~現代と科学とconflict of interest PART2
すべて偉大なものは単純である~現代と科学とconflict of interest PART3
で,STS,ってなんだろな? と言いますと,諸説ありまして,
★先制タイムリー,センター前に抜けたーッ!!
★先生,あなたはか弱き大人の代弁者なのか?
★サルマタケ? 知ってるよ,松本零二先生の『男おいどん』に出てくるアレでしょ? いやあ,こんなところで,サルマタケの話が出るとは思わなかったなあw。個人的には『男おいどん』と言われると,『独身アパートどくだみ荘』のこと思い出しちゃうんだけど……あ,知ってる? さすがw,もう今日これ,終電で帰れなくなっちゃうなあ……
まあ,さすがに終電では帰りましたけどね。って関係ないね,ごめんなさい。
気を確かに持って行きますが,STSとは
科学技術社会論(Science, Technology and SocietyとかScience and Technology in Society)
のことでございます。学会もございます。
科学技術社会論学会
こういうのも。
STS Network Japan Web Site
そんでもって,科学技術社会論つうのは何かと申しますと,上記サイトを参照ください,なんて言ってもいいんですが,ま平たくいいますと,科学技術と現代社会との葛藤軋轢摩擦をおおいに考える会,ということでしょうか。
科学哲学っていうのが,科学者コミュニティ外から,わりと科学の中身にまで踏み込んで語りだしたため,科学者サイドからは「素人ふぜいが語るんじゃない!」なんつう,みもふたもない反論もあったりして,それは半分以上は正論でありますが,その反省を踏まえてってわけじゃないけど,要は,科学技術の現実社会への適応,というところを楽観視しないで考えようじゃないかということだと,個人的には思います。
誤解を恐れまくっていえば,原子爆弾の原理は,社会的に構成されたものではない,と思いますが,原子爆弾の開発および運用については,これ社会的なところを考えないわけにはいかない,というのは賢明なる皆さんはもうとっくにご存知のことと思いますが,そういうことであります。
要は,男には自分の世界があるたとえるなら空を駆けるひとすじのホニャラララではないですが,研究者には研究者の世界があるということで,当たり前なんですが,EBMが客観的に正しいから皆がEBMを信奉するのではなく,皆がEBMが正しいと「思うから」,EBMが支持されている,という側面があるわけです。もちろんそれだけじゃないけどね。
というわけで,これ。
いや実は買ってしばらく積読してしまってたわけですが,科学的知見は科学者間の説得的なネットワークによって支持されるとする「アクターネットワーク理論」なんかの話をしつつ,科学技術実践へと参与観察するわけです。著者の専門は情報ネットワークということでして,いわゆる科学哲学的なある種不毛なアプローチとは一線を画した議論になっています。専門家集団のダイナミズムを扱うということでありまして,まあ流行の路線であるというとなんですが,ネットワーク全盛の昨今,話がわかりやすいです。
もうひとつ,状況論的アプローチという話が出てくるのですが,
個人的には,心理療法でいう「いま,ここ」っつうのは,状況論的に分析できるのではないかなんて思いますね。精神分析的にも,スキナリアン的にも,アフォーダンス的にもイケル感じ。オモロイ。
ま,科学技術実践って,社会学といえば社会学ですが,社会学っつうのはこれ,現代人類学なわけでして,
というのも出ております。人類の営み,これ全部人類学の範疇でありまして,科学技術も例外ではございません。
ぐっとテーマを絞りますと,
こんなんありますぜ。カバーおどろおどろしすぎですね。
ま,なんつって,ここまでツラツラ述べてきてるわけですが,急速にまとめる方向にいきたいと思うのですが,,科学の社会学的な側面って,「説得」「コンセンサス」「説明責任」というところで成り立っておるわけですが,現実社会とのコミットということになりますと,「説明責任」っていうところがクローズアップされてくるわけでして,一般市民を対象とするとなると,あるいは「啓蒙」だとか「リテラシー」だとかいう話でもあるのですが,まあこれ実は結構難しい,某ロリコンのキャスバル坊や曰く「ならいますぐ愚民どもに叡智を授けてみせろ」って,愚民どもって,アータ,㌧だ思い上がり野郎ではありますが,一面の真実がないこともない。
とはいえ,全部運用上の問題,にしてしまうのは,イクナイ。科学の使い方を誤った,なんてよく言いますが,科学の使い方に誤ったもくそもないわけですが,前にもいいましたが,「本当の○○」だとか「○○は誤解されてる」だとか,そんなもんは幻想でして,ひとこと「現実を見ろ!」と言いたいわけですが,ナラティブ・ベースド・科学技術実践,なんつって,現実を見ずして,説明責任など果たせようはずがない,と思うわけですね。
とはいえとはいえToi et moe,啓蒙の大切さももちろんあるわけで(なんなんだ),納豆食ったけど痩せなかったけど後で効果がないと聞いて大量に買い込んで余った納豆どうしてくれるんだTV局に文句いっちゃる,つうのもまあいいんですけど,そもそも「買い込まない」ということもできるわけでして,体制側(という言い方もアレだけど)からみれば「啓蒙」,市民側から見れば「リテラシー」つうのはやっぱ大事ですね。一般市民にとって,金銭は無限ではないですから,カシコクお金を使わなくてはなりません。
ここら辺では,かなり具体的な問題に踏み込んだ議論がなされております。一方で,なんだかひどく当たり前のような気もするわけですが,こういう論点がもっとクローズアップされるべきだと思いつつも,権力化してしまうとそれはそれであれだなあとも思うわけですが。
まあデモね,必要以上に社会的なものを重視してしまいますと,先日述べた「JBM:Judgement Based Medicine」ってことにもなるのかなと思うのですが,EBMとNBMとJBMで三権分立モンテスキューなんつって適当なこといっちゃったりして。
まあ,ところで,このシリーズの最初のほうで,科学と宗教は同質だ的なことをいっちゃったわけですが,まあ本質的にはそうだと思ってるのですが,現実適応上においては違いももちろんある。ま,科学とオカルトというふうに考えると,これ結構,科学者としては腕が鳴るところなのかも知れず,わりと一生懸命になってる感じがするのですね。
でもオカルトなくならない,科学者いらだつ,っていうイタチゴッコなんですが,なんでオカルトが死に絶えないかというと,オカルトが人類の文化・慣習を非常に鑑みつつ構成されているため,科学よりも,一般市民における「説得」「コンセンサス」というところで,アドバンテージがあるからなのでして,特徴として,科学っつうのはまあオカルトよりは真正直すぎでして,オカルトはそこらへんは狡猾なんですよね,世渡り上手というか。そして,そのアーミテージもといアドバンテージを楯になんとなくのノリで「説明責任」を回避し続ける,それがオカルトです。
真正直で真面目な人が必ずしも正当な評価を受けるとは限らないのが,世知辛い社会というもの。軽薄だけど,世慣れたオカルトさんがもてはやされてるのを見ると,激しくイライラしてくるわけで,逆上して,正論ばっかブッてると,ますます「あの人,なんかコワーイ」なんて女子に噂されちゃって,ますますモテなくなっていき……,って話がずれた。
だから,世慣れよ,科学よ! ってことでもなくて,世慣れすぎちゃうとconflict of interestあるいはAru Aruになっちゃうわけで,まあpsy-pubとしては,頑張れよッ,応援してっから,と肩をポンと叩きたいわけですね。いろいろアプローチはありますけど,最近の代表的な戦いに,「進化論」をめぐる科学VS.オカルトが繰り広げられてるわけですね,ずっと前からあるわけですが,主にアメリカで最近活発なのは,ご存知かと思います。
進化論をめぐるところでは,生物学の方たちは結構四苦八苦してるところではないかと思いますが,その分,最強最大のライバルに対抗すべく,哲学的な理論武装を頑張ってる感じもありますね。
はじめての進化論
進化論の見方
この河田雅圭先生は,生物学系の科学哲学を専門とされております。すでに書籍化されているものをWEB上で公開するという,ある種の反則技ではありますが,しかしこの熱意,受けとめるべきだとは思いませんか,みなさんッ。
ねじくれたアプローチとしては,以前紹介したこれになりますでしょうか。
ま,いわゆる創造科学を揶揄してるわけですが,文字通りに読んでみても(普通読めないけど),その論理構成の仕方が,「説明責任」ということを考える時,よき教科書になる側面もあり,なかなか複雑な味わいがあります。
…………
というわけで,ながらくお送りしたこのシリーズ,とりあえずこれにてオシマイですが,今後も陰に日向に顔を出すと思われますので,みんなもぜひ考えてみてくれよなっ!
しかし,「ばいこくど」と言われたら,3日はへこみそうな言葉の強さがありますが,「ばいこくやっこ」だと,京都の祇園あたりで,「ヘエ,今日は新しい妓が入りましたよって,ばいこくやっこッ,ばいこくやっこッ,はようこっちにッ,もうどこ行ってたんや,もうホンマ気のきかん妓で……」なんていっても通用する気がしないでもするでもありませんな。まあしないね。
などと,ついどうでもいいこと書いてしまいました。前フリ完全スルー,登録完全無料(男性会員)にて,科学を考えるシリーズ第4弾,今日はSTSであります。
●関連エントリ
現代と科学とconflict of interest
科学をわしも考えた~現代と科学とconflict of interest PART2
すべて偉大なものは単純である~現代と科学とconflict of interest PART3
で,STS,ってなんだろな? と言いますと,諸説ありまして,
★先制タイムリー,センター前に抜けたーッ!!
★先生,あなたはか弱き大人の代弁者なのか?
★サルマタケ? 知ってるよ,松本零二先生の『男おいどん』に出てくるアレでしょ? いやあ,こんなところで,サルマタケの話が出るとは思わなかったなあw。個人的には『男おいどん』と言われると,『独身アパートどくだみ荘』のこと思い出しちゃうんだけど……あ,知ってる? さすがw,もう今日これ,終電で帰れなくなっちゃうなあ……
まあ,さすがに終電では帰りましたけどね。って関係ないね,ごめんなさい。
気を確かに持って行きますが,STSとは
科学技術社会論(Science, Technology and SocietyとかScience and Technology in Society)
のことでございます。学会もございます。
科学技術社会論学会
こういうのも。
STS Network Japan Web Site
そんでもって,科学技術社会論つうのは何かと申しますと,上記サイトを参照ください,なんて言ってもいいんですが,ま平たくいいますと,科学技術と現代社会との葛藤軋轢摩擦をおおいに考える会,ということでしょうか。
科学哲学っていうのが,科学者コミュニティ外から,わりと科学の中身にまで踏み込んで語りだしたため,科学者サイドからは「素人ふぜいが語るんじゃない!」なんつう,みもふたもない反論もあったりして,それは半分以上は正論でありますが,その反省を踏まえてってわけじゃないけど,要は,科学技術の現実社会への適応,というところを楽観視しないで考えようじゃないかということだと,個人的には思います。
誤解を恐れまくっていえば,原子爆弾の原理は,社会的に構成されたものではない,と思いますが,原子爆弾の開発および運用については,これ社会的なところを考えないわけにはいかない,というのは賢明なる皆さんはもうとっくにご存知のことと思いますが,そういうことであります。
要は,男には自分の世界があるたとえるなら空を駆けるひとすじのホニャラララではないですが,研究者には研究者の世界があるということで,当たり前なんですが,EBMが客観的に正しいから皆がEBMを信奉するのではなく,皆がEBMが正しいと「思うから」,EBMが支持されている,という側面があるわけです。もちろんそれだけじゃないけどね。
というわけで,これ。
 | 科学技術実践のフィールドワーク―ハイブリッドのデザイン上野 直樹 土橋 臣吾 せりか書房 2006-12売り上げランキング : 159881 |
いや実は買ってしばらく積読してしまってたわけですが,科学的知見は科学者間の説得的なネットワークによって支持されるとする「アクターネットワーク理論」なんかの話をしつつ,科学技術実践へと参与観察するわけです。著者の専門は情報ネットワークということでして,いわゆる科学哲学的なある種不毛なアプローチとは一線を画した議論になっています。専門家集団のダイナミズムを扱うということでありまして,まあ流行の路線であるというとなんですが,ネットワーク全盛の昨今,話がわかりやすいです。
もうひとつ,状況論的アプローチという話が出てくるのですが,
 | 文化と状況的学習―実践、言語、人工物へのアクセスのデザイン上野 直樹 ソーヤー りえこ 凡人社 2006-10-07売り上げランキング : 83660 |
個人的には,心理療法でいう「いま,ここ」っつうのは,状況論的に分析できるのではないかなんて思いますね。精神分析的にも,スキナリアン的にも,アフォーダンス的にもイケル感じ。オモロイ。
ま,科学技術実践って,社会学といえば社会学ですが,社会学っつうのはこれ,現代人類学なわけでして,
 | 現代人類学のプラクシス―科学技術時代をみる視座山下 晋司 福島 真人 有斐閣 2005-11売り上げランキング : 48089 |
というのも出ております。人類の営み,これ全部人類学の範疇でありまして,科学技術も例外ではございません。
ぐっとテーマを絞りますと,
 | 帝国医療と人類学奥野 克巳 春風社 2006-03売り上げランキング : 153725 |
こんなんありますぜ。カバーおどろおどろしすぎですね。
ま,なんつって,ここまでツラツラ述べてきてるわけですが,急速にまとめる方向にいきたいと思うのですが,,科学の社会学的な側面って,「説得」「コンセンサス」「説明責任」というところで成り立っておるわけですが,現実社会とのコミットということになりますと,「説明責任」っていうところがクローズアップされてくるわけでして,一般市民を対象とするとなると,あるいは「啓蒙」だとか「リテラシー」だとかいう話でもあるのですが,まあこれ実は結構難しい,某ロリコンのキャスバル坊や曰く「ならいますぐ愚民どもに叡智を授けてみせろ」って,愚民どもって,アータ,㌧だ思い上がり野郎ではありますが,一面の真実がないこともない。
とはいえ,全部運用上の問題,にしてしまうのは,イクナイ。科学の使い方を誤った,なんてよく言いますが,科学の使い方に誤ったもくそもないわけですが,前にもいいましたが,「本当の○○」だとか「○○は誤解されてる」だとか,そんなもんは幻想でして,ひとこと「現実を見ろ!」と言いたいわけですが,ナラティブ・ベースド・科学技術実践,なんつって,現実を見ずして,説明責任など果たせようはずがない,と思うわけですね。
とはいえとはいえToi et moe,啓蒙の大切さももちろんあるわけで(なんなんだ),納豆食ったけど痩せなかったけど後で効果がないと聞いて大量に買い込んで余った納豆どうしてくれるんだTV局に文句いっちゃる,つうのもまあいいんですけど,そもそも「買い込まない」ということもできるわけでして,体制側(という言い方もアレだけど)からみれば「啓蒙」,市民側から見れば「リテラシー」つうのはやっぱ大事ですね。一般市民にとって,金銭は無限ではないですから,カシコクお金を使わなくてはなりません。
 | 誰が科学技術について考えるのか―コンセンサス会議という実験小林 伝司 名古屋大学出版会 2004-01売り上げランキング : 229972 |
 | 科学技術社会論の技法藤垣 裕子 東京大学出版会 2005-11売り上げランキング : 90597おすすめ平均  |
ここら辺では,かなり具体的な問題に踏み込んだ議論がなされております。一方で,なんだかひどく当たり前のような気もするわけですが,こういう論点がもっとクローズアップされるべきだと思いつつも,権力化してしまうとそれはそれであれだなあとも思うわけですが。
まあデモね,必要以上に社会的なものを重視してしまいますと,先日述べた「JBM:Judgement Based Medicine」ってことにもなるのかなと思うのですが,EBMとNBMとJBMで三権分立モンテスキューなんつって適当なこといっちゃったりして。
まあ,ところで,このシリーズの最初のほうで,科学と宗教は同質だ的なことをいっちゃったわけですが,まあ本質的にはそうだと思ってるのですが,現実適応上においては違いももちろんある。ま,科学とオカルトというふうに考えると,これ結構,科学者としては腕が鳴るところなのかも知れず,わりと一生懸命になってる感じがするのですね。
でもオカルトなくならない,科学者いらだつ,っていうイタチゴッコなんですが,なんでオカルトが死に絶えないかというと,オカルトが人類の文化・慣習を非常に鑑みつつ構成されているため,科学よりも,一般市民における「説得」「コンセンサス」というところで,アドバンテージがあるからなのでして,特徴として,科学っつうのはまあオカルトよりは真正直すぎでして,オカルトはそこらへんは狡猾なんですよね,世渡り上手というか。そして,そのアーミテージもといアドバンテージを楯になんとなくのノリで「説明責任」を回避し続ける,それがオカルトです。
真正直で真面目な人が必ずしも正当な評価を受けるとは限らないのが,世知辛い社会というもの。軽薄だけど,世慣れたオカルトさんがもてはやされてるのを見ると,激しくイライラしてくるわけで,逆上して,正論ばっかブッてると,ますます「あの人,なんかコワーイ」なんて女子に噂されちゃって,ますますモテなくなっていき……,って話がずれた。
だから,世慣れよ,科学よ! ってことでもなくて,世慣れすぎちゃうとconflict of interestあるいはAru Aruになっちゃうわけで,まあpsy-pubとしては,頑張れよッ,応援してっから,と肩をポンと叩きたいわけですね。いろいろアプローチはありますけど,最近の代表的な戦いに,「進化論」をめぐる科学VS.オカルトが繰り広げられてるわけですね,ずっと前からあるわけですが,主にアメリカで最近活発なのは,ご存知かと思います。
進化論をめぐるところでは,生物学の方たちは結構四苦八苦してるところではないかと思いますが,その分,最強最大のライバルに対抗すべく,哲学的な理論武装を頑張ってる感じもありますね。
はじめての進化論
進化論の見方
この河田雅圭先生は,生物学系の科学哲学を専門とされております。すでに書籍化されているものをWEB上で公開するという,ある種の反則技ではありますが,しかしこの熱意,受けとめるべきだとは思いませんか,みなさんッ。
ねじくれたアプローチとしては,以前紹介したこれになりますでしょうか。
 | 反・進化論講座―空飛ぶスパゲッティ・モンスターの福音書ボビー ヘンダーソン Bobby Henderson 片岡 夏実 築地書館 2006-11売り上げランキング : 18027 |
ま,いわゆる創造科学を揶揄してるわけですが,文字通りに読んでみても(普通読めないけど),その論理構成の仕方が,「説明責任」ということを考える時,よき教科書になる側面もあり,なかなか複雑な味わいがあります。
…………
というわけで,ながらくお送りしたこのシリーズ,とりあえずこれにてオシマイですが,今後も陰に日向に顔を出すと思われますので,みんなもぜひ考えてみてくれよなっ!












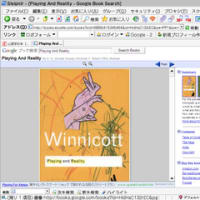


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます