ええっと先日のエントリ「医学がすなるEBMといふものを臨床心理学もしてみむとてするなり」のコメント欄にて,不肖サイパブが書いた「後期ロジャーズは「実証研究」にもかなり積極的だったようですね」という部分について,ガイドスピリットからのスピリチュアルメッセージ,もとい,とある先生よりEメールを頂戴しました。既に同コメント欄に訂正はしたのですが,自分の勉強不足は棚にレイアップしておいて,このメールが大変面白い内容で,こんな面白いものをただで頂いておいて,サイパブのメールボックスの中に留めておくのはもったいない,そんなのってイヤヨイヤイヤ,イエイエガールってことで,承諾済みの上,一部改変して再掲させて頂きます。しまりす先生(仮名)ありがとうございました!
=====================================================
ロジャーズの著作は,「実証」に関連する範囲で,以下のように並べられます。
①1939 問題児の臨床的処遇
②1942 カウンセリングと心理療法
③1951 クライアント中心療法
④1954 心理療法と人格変化
⑤1967 治療関係とそのインパクト
結論は,「ロジャーズは<初期から一貫して>実証研究に<非常に>積極的だった」。学位論文(1931)は「子どもの処遇決定のための人格適応尺度の作成」で,そのもととなった実践,あるいは,それをもとにした実践の成果が①。これで大学教授になりました。
②と③とは,よく,前者は技法,後者は態度(哲学),とされます。ロジャーズからすると,②が(非指示という)技法としか取られなかったので,主張は(非指示=クライアント中心という)態度(哲学)にあるとして③を著した。しかしこれは,車の両輪です。
②はすぐれた実務書ですが,③を読んだだけでは,態度(哲学)・思想はわかっても,実務でどう(行動)したらいいか,わかりません。両者はセットで読まれなければならないと思います。態度(哲学)なき技法は盲目,技法なき態度(哲学)は空虚。
そして「態度が生かされる技法であればなんでもいい」に至ります。「治療的人格変化の必要十分条件」(1957)論文です(cf.コフート「内省・共感・精神分析」口演の年)。この論文は,クライアント中心療法の創始者ロジャーズが記した論文ですが,クライアント中心療法についての論文ではありません。
S.D.ミラーら(1997)の関係要因30%の核心は,ロジャーズのこの論文,この主張(が実証された)ですが(心理療法全体の必要十分条件ではないにしても,関係要因の必要十分条件ではあろう,ということ),一療法としてのクライアント中心療法のことではないのと同じですね。1957年論文は,クライアント中心療法というみずからの実践をもとに生まれた,心理療法の一般理論についての「仮説」の提示なのです。
閑話休題。
②,③にはまったく一致している点があり,それは,主張に対して,支持する「実証研究」または「面接抜粋」を非常に克明に付していることです。この部分を除くと,ボリューム的に非常に薄っぺらい本になります。
そして,④が神経症圏のクライアントに対する実証研究のまとめ,それらがもととなって,1957年論文に結実。そして,⑤が統合失調症クライアントにおける1957年論文の実証研究,なのです。主張に対して「実証研究」または「面接抜粋」を克明に挙げることは,この領域においてロジャーズが初めて拓きました。心理療法の科学的研究,すなわち,①「実証研究」と②「面接録音」です。前者には統計学の発展があり,後者には機械技術の発展があり,ロジャーズはこれらを進取したのです。新しもの好き,と言ってもいいかもしれません。
=====================================================
もうとくにサイパブごときが言うことはございません。やっぱパイオニアっていうのは多面的なんだなあと,思いますね。フロイトしかりスキナーしかり,です。
ちなみに,上記②,③はこれらぁ。①,④,⑤で本になってるものは…………知ってる人教えてくだっさ~い(他力本願かよ!)。
また,EBMについてもいくつかコメント頂き,その中で
=====================================================
精神医学において,生物主義と心理主義とが繰り返される。量的研究・質的研究だって同じではないか? アイソモルフィックなことが,繰り返し繰り返し,学問各領域で,その時代・その学問領域の言語で語られる。アイソモルフィックな認識に長けていたベイトソンが生きていたら,ぜひ彼の見解を聞いてみたい。
=====================================================
ははあん,ですね。確かにこういう点では,みんな「記憶喪失」になったかのように,あまり省みられませんよね。
ちゅうわけで,こんなに内容がつまったツッコミ,あらためてありがとうございました,しまりす先生!
また他流派で,「ワイの学派の実証研究の歴史はこんなんなっとんやでぇ~。ぜひ知ってや~。ちゅうか知らしめたんぞワレ~。ついでにシバくぞワレ!」っていうステキな先生,いらっしゃると嬉しいなあ。
=====================================================
ロジャーズの著作は,「実証」に関連する範囲で,以下のように並べられます。
①1939 問題児の臨床的処遇
②1942 カウンセリングと心理療法
③1951 クライアント中心療法
④1954 心理療法と人格変化
⑤1967 治療関係とそのインパクト
結論は,「ロジャーズは<初期から一貫して>実証研究に<非常に>積極的だった」。学位論文(1931)は「子どもの処遇決定のための人格適応尺度の作成」で,そのもととなった実践,あるいは,それをもとにした実践の成果が①。これで大学教授になりました。
②と③とは,よく,前者は技法,後者は態度(哲学),とされます。ロジャーズからすると,②が(非指示という)技法としか取られなかったので,主張は(非指示=クライアント中心という)態度(哲学)にあるとして③を著した。しかしこれは,車の両輪です。
②はすぐれた実務書ですが,③を読んだだけでは,態度(哲学)・思想はわかっても,実務でどう(行動)したらいいか,わかりません。両者はセットで読まれなければならないと思います。態度(哲学)なき技法は盲目,技法なき態度(哲学)は空虚。
そして「態度が生かされる技法であればなんでもいい」に至ります。「治療的人格変化の必要十分条件」(1957)論文です(cf.コフート「内省・共感・精神分析」口演の年)。この論文は,クライアント中心療法の創始者ロジャーズが記した論文ですが,クライアント中心療法についての論文ではありません。
S.D.ミラーら(1997)の関係要因30%の核心は,ロジャーズのこの論文,この主張(が実証された)ですが(心理療法全体の必要十分条件ではないにしても,関係要因の必要十分条件ではあろう,ということ),一療法としてのクライアント中心療法のことではないのと同じですね。1957年論文は,クライアント中心療法というみずからの実践をもとに生まれた,心理療法の一般理論についての「仮説」の提示なのです。
閑話休題。
②,③にはまったく一致している点があり,それは,主張に対して,支持する「実証研究」または「面接抜粋」を非常に克明に付していることです。この部分を除くと,ボリューム的に非常に薄っぺらい本になります。
そして,④が神経症圏のクライアントに対する実証研究のまとめ,それらがもととなって,1957年論文に結実。そして,⑤が統合失調症クライアントにおける1957年論文の実証研究,なのです。主張に対して「実証研究」または「面接抜粋」を克明に挙げることは,この領域においてロジャーズが初めて拓きました。心理療法の科学的研究,すなわち,①「実証研究」と②「面接録音」です。前者には統計学の発展があり,後者には機械技術の発展があり,ロジャーズはこれらを進取したのです。新しもの好き,と言ってもいいかもしれません。
=====================================================
もうとくにサイパブごときが言うことはございません。やっぱパイオニアっていうのは多面的なんだなあと,思いますね。フロイトしかりスキナーしかり,です。
ちなみに,上記②,③はこれらぁ。①,④,⑤で本になってるものは…………知ってる人教えてくだっさ~い(他力本願かよ!)。
 | カウンセリングと心理療法―実践のための新しい概念 C.R. ロジャーズ Carl R. Rogers 末武 康弘 岩崎学術出版社 2005-04 売り上げランキング : 44,707 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
 | クライアント中心療法 カール・R. ロジャーズ Carl R. Rogers 保坂 亨 岩崎学術出版社 2005-07 売り上げランキング : 77,265 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
また,EBMについてもいくつかコメント頂き,その中で
=====================================================
精神医学において,生物主義と心理主義とが繰り返される。量的研究・質的研究だって同じではないか? アイソモルフィックなことが,繰り返し繰り返し,学問各領域で,その時代・その学問領域の言語で語られる。アイソモルフィックな認識に長けていたベイトソンが生きていたら,ぜひ彼の見解を聞いてみたい。
=====================================================
ははあん,ですね。確かにこういう点では,みんな「記憶喪失」になったかのように,あまり省みられませんよね。
ちゅうわけで,こんなに内容がつまったツッコミ,あらためてありがとうございました,しまりす先生!
また他流派で,「ワイの学派の実証研究の歴史はこんなんなっとんやでぇ~。ぜひ知ってや~。ちゅうか知らしめたんぞワレ~。ついでにシバくぞワレ!」っていうステキな先生,いらっしゃると嬉しいなあ。












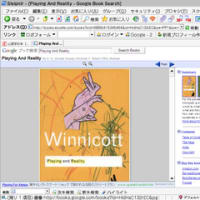


トラックバックさせていただきました。
1939 問題児の臨床的処遇
1954 心理療法と人格変化
?1967 治療関係とそのインパクト
の、邦訳、記事中に挙げました。
(nanaのリンク先が、当記事です。)
psy-pubさんと、しまりす先生(どなただろう)に、謝々<_._>。
>nanaさま
早々にコメント&TBにて,ご教示ありがとうございます! さすがですね!
しかし,こういう記事は,各論文をきちんと読んでいないと分からないことなので,psy-pub的にもたいへん勉強になりましたヨ。逆立ちしたって書けないですね,これは……。