え? あそにおると!?
というわけで,現代と科学とconflict of interest PART5,略して,現科conf. PART5ですが,懲りずに再開しといて,またコレカヨ……と,がっかりイリュージョン気分満載の皆様,朗報です! どうやらこれで,ひとりよがりなブームも終わりのようですよ!
●関連エントリ
現代と科学とconflict of interest
科学をわしも考えた~現代と科学とconflict of interest PART2
すべて偉大なものは単純である~現代と科学とconflict of interest PART3
説得NTあるいはオカルト~現代と科学とconflict of interest PART4
ま,AruAruから遠く離れて,もう話しはズレまくって,どっちかっていうと,科学のことを知る(主にpsy-pubが)的ノリになっていってるわけですが,まあこういうこと,若いうちにベンキョーしとけばよかったなと思いますよ。そしたら今頃は……,いや,そんな話は止しときましょう,タラ・レバーは禁物です。だって嫌いな人もいるから……。
しっかし,社会構築主義とか,いわゆる相対主義なんつうの,すべてを相対化してみる,といえば,それで終わっちまうわけですけど,じゃあ相対化するってナンナンディスカー? ノックしてもしも~し? ってコメカミぐりぐりしながら言われたら……,まあいろいろ説明しようはあると思うのですが,個人的には,昔,誰かがどこかで書いていた(限りなく曖昧なソースで乙)のが「SFというのは価値を相対化することである」というのが,僕にとっては今でもわかりやすくイメージしやすいんですな。
SF? ソレなんてスカル・ファック? なんていわないで,SF=少し不思議,もとい空想科学小説Scientific Fictionですが,誰もが見たことある典型的なSFってなんだろなと思うと,個人的には『猿の惑星』といきたいところなんですが,これ,若人(わかと)は知らない恐れがありまクリスティなので,ViViりつつ,これを。
シリーズ屈指のギミックにとんだ構成で,私のお気に入りでして,リメイク第2弾(観てないですけど)にこれが選択されたことは嬉しかったです。個人的に大長編ドラえもんなら『宇宙小戦争』がバランスでいえば最高ですが(主題歌が秀逸),まあそれはさておいて,『魔界大冒険』です。以下チョロッと私なりにストーリーの導入部をまとめてみました。
……ニートorまんが道の二者択一の岐路まではまだまだモラトリアムなのび太氏,その取り巻き連たるゴロツキのドラえもん一味(ドラミ,セワシなど含む)のおかげで22世紀の科学技術をふんだんに味わえる環境下にも関わらず「もしもボックス」なる現代のローティーンにはその語源(もしもしボックス→公衆電話なのね)すら意味不明で,しかしよくよく考えれば最強クラスのパラドキシカル・アイテムにて,「(科学ではなく)魔法を基盤とする社会になあれ!」などと,普段のドラえもんaddictionどこへやら,ドラえもんを全否定するともとられかねない,科学の否定および現実社会の転覆TENPUKUを試みるのだった。その結果,確かに現実社会が魔法を基盤とするそれになったにもかかわらず,結局は,神の見えざる手すなわち経済原則すなわち金銭的な拘束から逃れられるはずもなく,例によって,思うにまかせぬ現実をここでも知るのび太氏なのであった……。
まあここでいう「科学と魔法の逆転」が,SF的な醍醐味といえるでしょうか。むろん,その逆転を科学の力で為しえているじゃないか,というのはサテオイテ頂ければ幸甚です。科学と魔法が入れ替わっても,ドラえもんが22世紀の最新魔法の粋を凝らしたホムンクルスになることもないです。
ちなみに,実は劇中にて頭脳明晰でかつ人格者の出来杉くんにより,「科学と魔法のオシャレカンケイ」について,解説されているのですが,これが誠にコンパクトで要にして諦な解説になっております。そんな解説ができる小学5年生,なんとも恐るべき子どもっぷりです。
ところで,先述の「SF=少し不思議」つうのは,他ならぬF先生の発案なわけですが,これワタクシの解釈では,F先生なりのリップサービスあるいは謙遜だと思うのでして,確か文庫版短編集のあとがきにて「手塚先生の『火の鳥』のような作品をいつかは書いてみたいけれど……」と述懐されていたのを読んだ時は思わず涙したものでしたが……,ドラえもんの本質は,ドラえもんのもたらす科学(ある種オカルト的な超科学)による,ハードなSF小説に勝るとも劣らない,価値の逆転に満ち満ちておりまして(くりまんじゅうの指数関数的増殖の恐怖を思い出せ!),しかもそれをPOPに仕上げる優しさがある,それが何で手塚先生に劣っているものかよ! と,なんだかひとりで勝手に興奮してまいりましたが,閑話休題。
大長編のみならず,価値を相対化してみること,これをワタクシたちは幸運にもドラえもんを通して,幼少のみぎりより学んできてるわけですが,まあ宗教的にというか無宗教的にというか,日本人つうかアジア人はもともとそういう傾向が欧米人と比べて強いのかもしれないですね。そういう傾向が強いということは,裏を返せば,相対化ということを徹底して考えられない,というか,考える必要性を感じえない,というのはあると思います。
したがって,「それでも地球はまわっている……」なんつう猿芝居(ゴメンナサイ),やる必要がないんですね。猿が人間になったってイイ! というのが日本人的感覚ですが,それと違う感覚をもつ人たちもいるのです。たとえばナラティブセラピーに対して,素朴な感想のひとつとして「なんかとても当たり前のことをいってる気がする……」というのは,批判としては的外れですが,日常感覚的には至極当然なのですね,東洋人にとっては。
しかし,価値の逆転が起こるところに,実は進展があるというのは,もうこれ,なんにせよそうなのでして,罪がなければ逃げる楽しみもない,なんつうロジックfrom砂の女,はさておいて,魔界大冒険でいえば,科学と魔法が入れ替わったがゆえに,魔王が現われるし,冒険も始まるわけですが,これをどうとるかっていうのは,物語のディスクールを抜きにしても,いろいろと想像する余地があるわけですね。
…………
前フリが超絶的に長大になってしまいましたが,こっからどういう話にいくかというと,数学の話にいくわけですが,まあpsy-pubなんぞは微分・積分どころかベクトル・数列レベルの数学すら理解できる頭を持っておりませんので,まあそれなりの展開になることをお許しくださいませネ。
サテ「この世のすべては数学で表現できる!」と鼻息荒かったのは,ポケモンでもおなじみのラプラスさんでして,この人,デーモンを召還して悪魔合体して「全部わかったら全部わかるよ」と主張したわけですが,実は全部わかることは不可能である,もしくは全部わかっても全部わからないかもしれない,あるいは全部わからなくても全部わかるかもしれない,なんつうことがアルヨアルアル,アルアルアwwwww,アルYO! なんて言われてたりするのが最近の主流の考え方なんですよね,センパイ!
にしても,「全部わかっても全部わからないかもしれない」っていうのは,これ結構衝撃的なことでして,数学あるいは科学ということを再考する(科学におぼれた愚かな人間どもよ,っていう話ではなくて)ことになったわけですが,そのきっかけのひとつが,生誕100周年ということで盛り上がっているのが,数学者ゲーデルさんですよ。
ゲーデルの不完全性定理---Wikipedia
ヒルベルトプログラム,すなわち,論理体系が無矛盾ならSG(数学)勝つる~春モード,をみごと粉砕してしまいました。こういうところ,数学をワカランチンどもに非常にウケております。まあそう単純な話でもないのですけどね。
要はいくら公理をきちっと設定し,条件を決めたとしても,数学で解けないこともある,ということでして(ex:自己言及のパラドックス),これをもって,数学ってたいしたことない! と思いたい気持ちは文系の人にはあるかもしれませんが,そういう後ろ向きなことじゃなく,わからないことをわかったうえでの,さらなる進展を目指すわけですな。
さすがに数学界いや科学界の巨人だけあって,生誕100年に合わせ,関連本が結構出ておりますよ。
生涯込みで追うのは,好みです。読み物としては最高にアストロ・クラス,間違いない。
幅広く種々の論考が読めるのが雑誌の利点ですわな。
おどろきの,原論文です。解説も丁寧で,このコンパクトさは,得がたい。
腰をすえて理解しようとするなら,ぜひこれを。全4巻。現在3巻まで出てます。
ま,この不完全性定理に似たような話として,「シュレディンガーの猫」というのがあります。
シュレディンガーの猫---Wikipedia
わかりやすくいうならば,ドラえもんと押入れとドラ焼きを用意して,一定時間経過後に,ドラ焼きはあるかないか,って話ですね(ホントかよ)。ドラえもんはドラ焼きが好きなので,おそらくドラ焼きはなくなるだろうと思うですが,なくなったかどうかは押入れを開けるまではわからない,というね。これを観測問題というそうです(マジで?)。
観測問題---Wikipedia
ミレバワカル,のは日常感覚的には当然過ぎるわけですが,いつも事件は現場で起こっているので,会議室にいる私たちには,わかりませんのです。逆にいえば,会議室にいる私たちもその現場の経過を推測することは可能であり,また,結果そのものも認識することは可能であります。しかし現場の力動性はわかりえないし,究極的には,結果が出たときに結果がわかり,結果が出ていないときには結果はわからないという,トートロジーなんですが,そうとしかいえないわけですね。
じゃあ,現場で一部始終見てりゃあイイジャン? というかもしれないですが,透明人間でない限り,あなたの存在は確実に結果に影響するのですね。これ哲学的な話じゃなくて,実際,現代物理学の実験なんかは,観測機器の影響を無視していないということからも,その影響はほぼ無視できると考えるのは,ちょっと現実的でないのですね。
したがって,私たちの見得ないところで何かが起こっていますが,その結果は,サイコロ振って決めちゃいます,というのが,現代科学の主流なのであります(コペンハーゲン解釈)。まあもちろんそのサイコロは,ただのサイコロではないですが,サイコロはサイコロ,なわけですね。
いきなりなにゆえサイコロの話? というのは説明しだすと長くなりますが,要は,昔かのアインシュタインさんが「神様はサイコロを振らないHe does not throw dice」いった話がありまして,詳しくはGoogleってみてね。
ちなみに,精神医学でもサイコロを振り始めたのは比較的最近の話でして,
ま,この前のDSM-IIIからなのですが,DSM診断基準の妥当性ないし臨床的有用性はともかくとしても,標準版は絶対読んでおくべきであります。そうじゃないと,批判も批判足りえないわけで,まあもうちょっとでDSM‐Vも出そうですけど。
精神医学の標準的なreferenceが統計学に則ったものである,というのは,これ結構ビックリする場面だと思います。ちゅうことは,統計の授業は真面目に受けておけ,ということにもなりますわな。
というところで,字数制限が……。息つくまもなく,後編に続きます。
…………
たとえこの世界がみな,とドラえもんは言った:後編~現科conf. PART5
というわけで,現代と科学とconflict of interest PART5,略して,現科conf. PART5ですが,懲りずに再開しといて,またコレカヨ……と,がっかりイリュージョン気分満載の皆様,朗報です! どうやらこれで,ひとりよがりなブームも終わりのようですよ!
●関連エントリ
現代と科学とconflict of interest
科学をわしも考えた~現代と科学とconflict of interest PART2
すべて偉大なものは単純である~現代と科学とconflict of interest PART3
説得NTあるいはオカルト~現代と科学とconflict of interest PART4
ま,AruAruから遠く離れて,もう話しはズレまくって,どっちかっていうと,科学のことを知る(主にpsy-pubが)的ノリになっていってるわけですが,まあこういうこと,若いうちにベンキョーしとけばよかったなと思いますよ。そしたら今頃は……,いや,そんな話は止しときましょう,タラ・レバーは禁物です。だって嫌いな人もいるから……。
しっかし,社会構築主義とか,いわゆる相対主義なんつうの,すべてを相対化してみる,といえば,それで終わっちまうわけですけど,じゃあ相対化するってナンナンディスカー? ノックしてもしも~し? ってコメカミぐりぐりしながら言われたら……,まあいろいろ説明しようはあると思うのですが,個人的には,昔,誰かがどこかで書いていた(限りなく曖昧なソースで乙)のが「SFというのは価値を相対化することである」というのが,僕にとっては今でもわかりやすくイメージしやすいんですな。
SF? ソレなんてスカル・ファック? なんていわないで,SF=少し不思議,もとい空想科学小説Scientific Fictionですが,誰もが見たことある典型的なSFってなんだろなと思うと,個人的には『猿の惑星』といきたいところなんですが,これ,若人(わかと)は知らない恐れがありまクリスティなので,ViViりつつ,これを。
 | のび太の魔界大冒険藤子 不二雄F 小学館 2007-02売り上げランキング : 31389 |
シリーズ屈指のギミックにとんだ構成で,私のお気に入りでして,リメイク第2弾(観てないですけど)にこれが選択されたことは嬉しかったです。個人的に大長編ドラえもんなら『宇宙小戦争』がバランスでいえば最高ですが(主題歌が秀逸),まあそれはさておいて,『魔界大冒険』です。以下チョロッと私なりにストーリーの導入部をまとめてみました。
……ニートorまんが道の二者択一の岐路まではまだまだモラトリアムなのび太氏,その取り巻き連たるゴロツキのドラえもん一味(ドラミ,セワシなど含む)のおかげで22世紀の科学技術をふんだんに味わえる環境下にも関わらず「もしもボックス」なる現代のローティーンにはその語源(もしもしボックス→公衆電話なのね)すら意味不明で,しかしよくよく考えれば最強クラスのパラドキシカル・アイテムにて,「(科学ではなく)魔法を基盤とする社会になあれ!」などと,普段のドラえもんaddictionどこへやら,ドラえもんを全否定するともとられかねない,科学の否定および現実社会の転覆TENPUKUを試みるのだった。その結果,確かに現実社会が魔法を基盤とするそれになったにもかかわらず,結局は,神の見えざる手すなわち経済原則すなわち金銭的な拘束から逃れられるはずもなく,例によって,思うにまかせぬ現実をここでも知るのび太氏なのであった……。
まあここでいう「科学と魔法の逆転」が,SF的な醍醐味といえるでしょうか。むろん,その逆転を科学の力で為しえているじゃないか,というのはサテオイテ頂ければ幸甚です。科学と魔法が入れ替わっても,ドラえもんが22世紀の最新魔法の粋を凝らしたホムンクルスになることもないです。
ちなみに,実は劇中にて頭脳明晰でかつ人格者の出来杉くんにより,「科学と魔法のオシャレカンケイ」について,解説されているのですが,これが誠にコンパクトで要にして諦な解説になっております。そんな解説ができる小学5年生,なんとも恐るべき子どもっぷりです。
ところで,先述の「SF=少し不思議」つうのは,他ならぬF先生の発案なわけですが,これワタクシの解釈では,F先生なりのリップサービスあるいは謙遜だと思うのでして,確か文庫版短編集のあとがきにて「手塚先生の『火の鳥』のような作品をいつかは書いてみたいけれど……」と述懐されていたのを読んだ時は思わず涙したものでしたが……,ドラえもんの本質は,ドラえもんのもたらす科学(ある種オカルト的な超科学)による,ハードなSF小説に勝るとも劣らない,価値の逆転に満ち満ちておりまして(くりまんじゅうの指数関数的増殖の恐怖を思い出せ!),しかもそれをPOPに仕上げる優しさがある,それが何で手塚先生に劣っているものかよ! と,なんだかひとりで勝手に興奮してまいりましたが,閑話休題。
大長編のみならず,価値を相対化してみること,これをワタクシたちは幸運にもドラえもんを通して,幼少のみぎりより学んできてるわけですが,まあ宗教的にというか無宗教的にというか,日本人つうかアジア人はもともとそういう傾向が欧米人と比べて強いのかもしれないですね。そういう傾向が強いということは,裏を返せば,相対化ということを徹底して考えられない,というか,考える必要性を感じえない,というのはあると思います。
したがって,「それでも地球はまわっている……」なんつう猿芝居(ゴメンナサイ),やる必要がないんですね。猿が人間になったってイイ! というのが日本人的感覚ですが,それと違う感覚をもつ人たちもいるのです。たとえばナラティブセラピーに対して,素朴な感想のひとつとして「なんかとても当たり前のことをいってる気がする……」というのは,批判としては的外れですが,日常感覚的には至極当然なのですね,東洋人にとっては。
しかし,価値の逆転が起こるところに,実は進展があるというのは,もうこれ,なんにせよそうなのでして,罪がなければ逃げる楽しみもない,なんつうロジックfrom砂の女,はさておいて,魔界大冒険でいえば,科学と魔法が入れ替わったがゆえに,魔王が現われるし,冒険も始まるわけですが,これをどうとるかっていうのは,物語のディスクールを抜きにしても,いろいろと想像する余地があるわけですね。
…………
前フリが超絶的に長大になってしまいましたが,こっからどういう話にいくかというと,数学の話にいくわけですが,まあpsy-pubなんぞは微分・積分どころかベクトル・数列レベルの数学すら理解できる頭を持っておりませんので,まあそれなりの展開になることをお許しくださいませネ。
サテ「この世のすべては数学で表現できる!」と鼻息荒かったのは,ポケモンでもおなじみのラプラスさんでして,この人,デーモンを召還して悪魔合体して「全部わかったら全部わかるよ」と主張したわけですが,実は全部わかることは不可能である,もしくは全部わかっても全部わからないかもしれない,あるいは全部わからなくても全部わかるかもしれない,なんつうことがアルヨアルアル,アルアルアwwwww,アルYO! なんて言われてたりするのが最近の主流の考え方なんですよね,センパイ!
にしても,「全部わかっても全部わからないかもしれない」っていうのは,これ結構衝撃的なことでして,数学あるいは科学ということを再考する(科学におぼれた愚かな人間どもよ,っていう話ではなくて)ことになったわけですが,そのきっかけのひとつが,生誕100周年ということで盛り上がっているのが,数学者ゲーデルさんですよ。
ゲーデルの不完全性定理---Wikipedia
ヒルベルトプログラム,すなわち,論理体系が無矛盾ならSG(数学)勝つる~春モード,をみごと粉砕してしまいました。こういうところ,数学をワカランチンどもに非常にウケております。まあそう単純な話でもないのですけどね。
要はいくら公理をきちっと設定し,条件を決めたとしても,数学で解けないこともある,ということでして(ex:自己言及のパラドックス),これをもって,数学ってたいしたことない! と思いたい気持ちは文系の人にはあるかもしれませんが,そういう後ろ向きなことじゃなく,わからないことをわかったうえでの,さらなる進展を目指すわけですな。
さすがに数学界いや科学界の巨人だけあって,生誕100年に合わせ,関連本が結構出ておりますよ。
 | ロジカル・ディレンマ ゲーデルの生涯と不完全性定理ジョン・W・ドーソンJr 村上 祐子 塩谷 賢 新曜社 2006-12-19売り上げランキング : 105852 |
生涯込みで追うのは,好みです。読み物としては最高にアストロ・クラス,間違いない。
 | 現代思想 vol.35-3 2007年2月臨時増刊号 特集=ゲーデル青土社 2007-02売り上げランキング : 34868 |
幅広く種々の論考が読めるのが雑誌の利点ですわな。
 | ゲーデル 不完全性定理ゲーデル 林 晋 八杉 満利子 岩波書店 2006-09売り上げランキング : 28576 |
おどろきの,原論文です。解説も丁寧で,このコンパクトさは,得がたい。
 | ゲーデルと20世紀の論理学(ロジック)〈1〉ゲーデルの20世紀田中 一之 東京大学出版会 2006-07売り上げランキング : 55018 |
腰をすえて理解しようとするなら,ぜひこれを。全4巻。現在3巻まで出てます。
ま,この不完全性定理に似たような話として,「シュレディンガーの猫」というのがあります。
シュレディンガーの猫---Wikipedia
わかりやすくいうならば,ドラえもんと押入れとドラ焼きを用意して,一定時間経過後に,ドラ焼きはあるかないか,って話ですね(ホントかよ)。ドラえもんはドラ焼きが好きなので,おそらくドラ焼きはなくなるだろうと思うですが,なくなったかどうかは押入れを開けるまではわからない,というね。これを観測問題というそうです(マジで?)。
観測問題---Wikipedia
ミレバワカル,のは日常感覚的には当然過ぎるわけですが,いつも事件は現場で起こっているので,会議室にいる私たちには,わかりませんのです。逆にいえば,会議室にいる私たちもその現場の経過を推測することは可能であり,また,結果そのものも認識することは可能であります。しかし現場の力動性はわかりえないし,究極的には,結果が出たときに結果がわかり,結果が出ていないときには結果はわからないという,トートロジーなんですが,そうとしかいえないわけですね。
じゃあ,現場で一部始終見てりゃあイイジャン? というかもしれないですが,透明人間でない限り,あなたの存在は確実に結果に影響するのですね。これ哲学的な話じゃなくて,実際,現代物理学の実験なんかは,観測機器の影響を無視していないということからも,その影響はほぼ無視できると考えるのは,ちょっと現実的でないのですね。
したがって,私たちの見得ないところで何かが起こっていますが,その結果は,サイコロ振って決めちゃいます,というのが,現代科学の主流なのであります(コペンハーゲン解釈)。まあもちろんそのサイコロは,ただのサイコロではないですが,サイコロはサイコロ,なわけですね。
いきなりなにゆえサイコロの話? というのは説明しだすと長くなりますが,要は,昔かのアインシュタインさんが「神様はサイコロを振らないHe does not throw dice」いった話がありまして,詳しくはGoogleってみてね。
ちなみに,精神医学でもサイコロを振り始めたのは比較的最近の話でして,
 | DSM‐IV‐TR 精神疾患の診断・統計マニュアル高橋 三郎 染矢 俊幸 大野 裕 医学書院 2003-12売り上げランキング : 132454Amazonで詳しく見る by G-Tools |
ま,この前のDSM-IIIからなのですが,DSM診断基準の妥当性ないし臨床的有用性はともかくとしても,標準版は絶対読んでおくべきであります。そうじゃないと,批判も批判足りえないわけで,まあもうちょっとでDSM‐Vも出そうですけど。
精神医学の標準的なreferenceが統計学に則ったものである,というのは,これ結構ビックリする場面だと思います。ちゅうことは,統計の授業は真面目に受けておけ,ということにもなりますわな。
というところで,字数制限が……。息つくまもなく,後編に続きます。
…………
たとえこの世界がみな,とドラえもんは言った:後編~現科conf. PART5












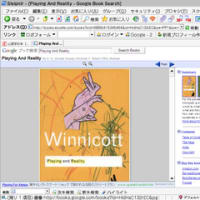


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます