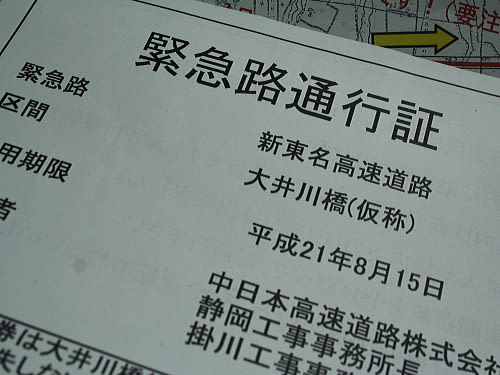29日はバンコクから2回目となるチャーター便が到着しました。今回はタイ国際航空機での運航です。残念ながら業務多忙につき写真はありません。次回の来月3日は・・・と思っております。そこで今日はタイ国際航空飛来記念として空港周辺で見つけたタイ語の看板をご紹介します。
こちらは上から日本語、英語、ドイツ語、中国語、韓国語、タイ語の6ヵ国語が記された多国語看板。

内容からご想像がつくと思いますが、看板があるのは大井川鐵道の新金谷駅前。駅舎内に入ると改札付近の掲示にも中国語やハングルでの表記があります。これも空港が開港したからでしょうか。

大井川鐵道といえばもちろんSLですが、こちらの写真のSLは先の大戦の期間にタイに送られ、戦後はそのままタイ国内で活躍したC56型。里帰りしたのが確か私が高校生の頃でしたから、もう30年位になります。
公式サイトによると、3年ほど前から日本とタイの修交120年を記念してタイで活躍していた当時の塗装を施しています。(写真は2008年撮影)

GW期間中は最大1日3便が運行されるSL。すでに金谷発はほとんど売り切れているようです。
こちらは上から日本語、英語、ドイツ語、中国語、韓国語、タイ語の6ヵ国語が記された多国語看板。

内容からご想像がつくと思いますが、看板があるのは大井川鐵道の新金谷駅前。駅舎内に入ると改札付近の掲示にも中国語やハングルでの表記があります。これも空港が開港したからでしょうか。

大井川鐵道といえばもちろんSLですが、こちらの写真のSLは先の大戦の期間にタイに送られ、戦後はそのままタイ国内で活躍したC56型。里帰りしたのが確か私が高校生の頃でしたから、もう30年位になります。
公式サイトによると、3年ほど前から日本とタイの修交120年を記念してタイで活躍していた当時の塗装を施しています。(写真は2008年撮影)

GW期間中は最大1日3便が運行されるSL。すでに金谷発はほとんど売り切れているようです。