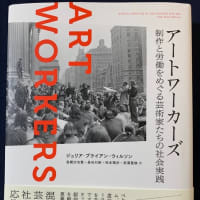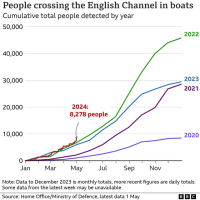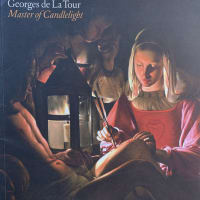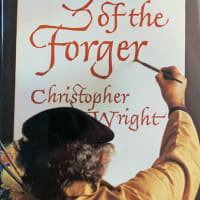本の読み方はさまざまだ。専門書の類はひとまずおくとして、エッセイのように断続的に読んでも、いっこうに差し支えない作品もあるが、小説のように感情の起伏、持続が消えないうちに一気に読みたいものもある。時々立ち止まって、考えながら読む方が深く味わえる作品もある。なんとなく、食べ物に似ている。
これとは少し違ったタイプの本もある。仕事に追われていた頃、途中でさえぎられることなく時間をかけて集中して読んでみたいと思う本を書棚の一角に積み重ねていた。実はその時読もうと思えば読めないわけでもなかったのだが、断続的に読むのは著者に申し訳ないという感じを持っていた(なんとなく言い訳がましい)。結果として、取り上げるに少し勇気?のいる作品が山積みになる。
外国作品の場合、しばしば初めに高い言語の壁が聳えていて身構えてしまうことが多い。とりわけ、ブログ筆者があまり得手ではない非英語圏の作品はそうである(そのいくつかはここに登場したが)。かつてドイツ語の恩師からいただいた100ページほどの現代思想の作品を、辞書を頼りに1年近くかけてなんとか読んだこともあった。いただいた以上、なにかの折には話題となるという圧迫感?がいつも背中を押していた。
これに似たような感じを多少持っていた作家のひとりが、ドイツの現代作家フォルカー・ブラウンである。一寸不思議なご縁で著者には親しくお会いしており、作品に献辞まで記していただいた。それだけにおろそかには読めないという思いがしていた。そんな言い訳も積み重なっている作家の作品だが、これまでに2冊だけ読んでいた。そのひとつは『自由の国のイフィゲーニエ』という戯曲である。幸い日本語訳が刊行されていて、解題を含めても60ページ足らずの小冊子なのだが、読み始めてみるとかなりの難物だった。表題の通り、ギリシャ神話(悲劇)とゲーテに関する素養、そして旧東ドイツの社会についての心象的イメージなしには十分理解できない。中島裕昭氏による「訳者解題」がなかったら、座礁していた可能性が高い。真理は細部にあるのだが、その細部が読み切れない。
この作家に別の点で関心を抱いていたのは、旧東ドイツのドレスデンに生まれ、その後東西ドイツの統合を自らの人生、作家活動の舞台として今日にいたっていることにあった。あのB・ブレヒトの創設した劇団ベルリーナー・アンサンブルの文芸部員、座付作家であったことも関心の片隅にあった。旧東西ドイツ双方の体制を経験してきたこの作家は、2000年、日本における芥川賞にあたるともいわれる「ゲオルク・ビューヒナー賞」を受賞している
旧東ドイツの時代と社会がいかなるものであり、そこで作家としての純粋性を貫いて生きることがどんなことであったかは、今日ではある程度の情報が蓄積され、想像をなしえないわけではない。かなり注意して知見を増やそうともしてきた。しかし、第3者としての想像と、そこに身を置いた人の現実の間には越えがたい断絶がある。
作家として自らが日々を過ごす社会の矛盾に正面から向かい合うほど、軋轢は増す。この作家は、ある時期からあのシュタージ(国家公安局)の常時監視下に置かれていたといわれる。89年に突如として「壁」が壊れた当時、フォルカー・ブラウンは来るべき東ドイツの選ぶ方向として「人民所有+民主主義」を構想していたらしい(訳者解題, p50)。この作家に関心を寄せた理由のひとつに、実はこの問題があった。ブラウンの想定した「人民所有」とはいかなる概念そして実体なのか。
しばらく「労働者自主管理企業」といわれるモデルを研究課題として探索していたことがあった。主として旧ユーゴスラビアなどの社会主義体制下において試みられていた企業組織である。フォルカー・ブラウンが東ドイツの企業管理組織の下で働く労働者の迷走する姿を描いた戯曲の作者であることは知っていた。社会主義に期待が寄せられた時代は消滅したが、代わって世界を席巻している倫理なき資本主義への望みも薄れるばかりだ。
今や「平らになった世界」を体験しているこの作家が、彼の人生の大半を過ごした政治体制との比較において、なにを思っているか、改めて聞いてみたい思いがする。そうしたわけで、ブラウンの新しい作品を読んでみようと思っている。とはいっても、目指す地にたどりつけるかは、まったく定かではない。
「作者による注解」からの引用(p.45):
(略)核心をなす問いは、延期されているかに見える平和的労働の別の可能性に向けられる/だがその労働は、旧い人間たちが新しいタウリスの地を踏むことで緊急のものとなる。トーアスが何を「なす」かは、経験が教えるだろう。ポストコロニアル時代には、勝者も敗者も勝手な振る舞いをしていて、区別ができない。その振る舞いが個性も自然も消し去るのだ。敵役となるのは、排除され、失業者として取り残された者たちだ。それは女性の姿をした黒人男か、黒人の姿をした女性である。サチュロス劇の衣装を取り換えて登場する狂気と理性だ。(以下略)
* Volker Braun. Iphigenie in Freiheit. Frankfursst/M. suhrkammp, 1992(フォルカー・ブラウン:中島裕昭訳)『自由の国のイフィゲーニエ』ドイツ現代戯曲選30(論創社、2006年)、pp.59.