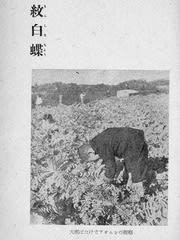3年 中川知己
野生動物学研究室に入室してから一年がたとうとしている。思い返してみるとずいぶんたくさんの動物の解剖をした。リスに始まり、サル、キリン、ゾウ、トラ…とさまざまな動物を解剖してきた。今もアライグマを解剖している途中だ。
私はトウキョウサンショウウオの調査をしているが、その一環として神奈川県でアライグマがトウキョウサンショウウオを食べている可能性があることを知り、アライグマの消化管内容物を分析したいと思った。同県内で駆除されたアライグマは日本獣医生命科学大学に保管されており、高槻先生の紹介でそのサンプルを分析させてもらえることになった。そこで、一月に同大学の解剖に参加することになった。
学外での解剖は初めての経験であり、解剖の作業体制や技術的なことなど学ぶものがたくさんあった。なかでも、学内でおこなっている解剖と決定的に違うことがあった。それは動物への黙祷である。解剖が終わったあと円を組み、動物たちへ一分間の黙祷を捧げた。同大学の方々は黙祷することが習慣となっているようだった。皆さんの真剣な態度をみて、とても大切なことだと思った。そして、自分が研究室で解剖をおこなっても黙祷をしたことはなかったことを思い、この差は何によるものだろうかと考えた。
解剖後の黙祷は命への敬意の表れだと思う。私たちが食事のあとにいう「ごちそうさま」もその類だと思う。日本人はこうした命への敬意を習慣化した結果、慣習として定着させたのだろう。私たちが普段何気なくやっている行動のなかにも慣習となったものが少なくない。普段何気なくやっているために、その行動のもともとの意味を理解していないことがあると思う。
解剖後の黙祷についても、黙祷をするという慣習を機械的にやることに意味はなく、命への敬意を捧げるという気持ちを持つことによってはじめて意味があるものになるはずだ。今回の一件で、私は今までに解剖してきた動物たちに好奇心以外の意思を持ってこなかったことに気付かされた。これからは心から命への敬意を捧げたい。
野生動物学研究室に入室してから一年がたとうとしている。思い返してみるとずいぶんたくさんの動物の解剖をした。リスに始まり、サル、キリン、ゾウ、トラ…とさまざまな動物を解剖してきた。今もアライグマを解剖している途中だ。
私はトウキョウサンショウウオの調査をしているが、その一環として神奈川県でアライグマがトウキョウサンショウウオを食べている可能性があることを知り、アライグマの消化管内容物を分析したいと思った。同県内で駆除されたアライグマは日本獣医生命科学大学に保管されており、高槻先生の紹介でそのサンプルを分析させてもらえることになった。そこで、一月に同大学の解剖に参加することになった。
学外での解剖は初めての経験であり、解剖の作業体制や技術的なことなど学ぶものがたくさんあった。なかでも、学内でおこなっている解剖と決定的に違うことがあった。それは動物への黙祷である。解剖が終わったあと円を組み、動物たちへ一分間の黙祷を捧げた。同大学の方々は黙祷することが習慣となっているようだった。皆さんの真剣な態度をみて、とても大切なことだと思った。そして、自分が研究室で解剖をおこなっても黙祷をしたことはなかったことを思い、この差は何によるものだろうかと考えた。
解剖後の黙祷は命への敬意の表れだと思う。私たちが食事のあとにいう「ごちそうさま」もその類だと思う。日本人はこうした命への敬意を習慣化した結果、慣習として定着させたのだろう。私たちが普段何気なくやっている行動のなかにも慣習となったものが少なくない。普段何気なくやっているために、その行動のもともとの意味を理解していないことがあると思う。
解剖後の黙祷についても、黙祷をするという慣習を機械的にやることに意味はなく、命への敬意を捧げるという気持ちを持つことによってはじめて意味があるものになるはずだ。今回の一件で、私は今までに解剖してきた動物たちに好奇心以外の意思を持ってこなかったことに気付かされた。これからは心から命への敬意を捧げたい。