明日は新聞休刊日
朝1番で旦那がコンビニにスポーツ紙を買いに走れるといいな ・・・
・・・
・・・




 跼天蹐地(きょくてんせきち)
跼天蹐地(きょくてんせきち)
・恐れおののいて、びくびくすること。
・ひどく恐れて身の置き所のないこと。
・世間をはばかって暮らすこと。
・天は高いのに身をかがめ、大地は厚いのに抜き足差し足でそっと歩く意から。
 玉兎銀蟾(ぎょくとぎんせん)
玉兎銀蟾(ぎょくとぎんせん)
・月の異称。
・「玉兎」は、伝説で月にいるという兎。転じて、月の異称。
・「銀蟾」は、伝説で月に入るというヒキガエル。転じて、月の異称。
 曲突徙薪(きょくとつししん)
曲突徙薪(きょくとつししん)
・災難を未然に防ぐことのたとえ。
・煙突を曲げ、かまどの周りにある薪を他に移して、火事になるのを防ぐ意から。
・ある家で、かまどの煙突が突き出していて、そのそばに薪が積んであった。
これを見たある人が煙突を曲げて、薪は別の所に移したほうがよい、
そうしないと火事になるだろうと忠告した。
しかし、その家の主人は言うことを聞かず、火事になってしまったという話から。
 曲眉豊頬(きょくびほうきょう)
曲眉豊頬(きょくびほうきょう)
・美しい女性の形容。
・「曲眉」は、三日月形にゆるやかに湾曲した美しい眉。
・「豊頬」は、ふっくらとした頬のこと。
・類義語 :「氷肌玉骨(ひょうきぎょっこつ)」「粉白黛墨(ふんぱくたいぼく)」
「明眸皓歯(めいぼうこうし)」「容姿端麗(ようしたんれい)」
 挙国一致(きょこくいっち)
挙国一致(きょこくいっち)
・国民全員が心を1つにして、ある目的に向かって団結すること。
・「挙国」は、国中を挙げて、国全体の意。
 河童の屁
河童の屁
・簡単で容易にできることのたとえ。
・取るに足らないことのたとえ。
・味も香りもないもののたとえ。
・河童は水中で屁をするので、力強くないことから出た言葉。
・類義 :「屁の河童」
 河童も一度は川流れ
河童も一度は川流れ
・何事も最初から上手な人はおらず、下手から始めるものだということ。
・泳ぎの上手な河童でも、初めのころ1度は溺れることもあるという意から。
・類義 :「端(はな)から和尚はいない」
 刮目して相待つべし
刮目して相待つべし
・今までの先入観を捨てて、新しい目で相手の変化や成長を見直さなければ
ならないということ。
・「刮目(かつもく)」は、目をこすってよく見ること。
・類義 :「刮目して之を視(み)る」
 勝つも負けるも時の運
勝つも負けるも時の運
・勝ち負けは、その時々の運不運によって決まることが多いという意。
・勝ち負けは、技量や日ごろの練習、努力だけではどうにもならないところが
あるということ。
・類義 :「勝つも負けるも運次第」「勝負は時の運」
「勝つも負けるも軍(いくさ)の習い」
 渇を被て玉を懐く
渇を被て玉を懐く
・表面を飾らず、内に美しい心を持っているたとえ。
・人目にはつかないが、優れた才能や見識を備えていることのたとえ。
・粗末な服を着ているが、懐には美しい宝石を抱いているという意から。
・「渇(かつ)」は、身分が低く貧しい者が着る、荒い毛織物の衣服。
 挙止迂拙(きょしうせつ)
挙止迂拙(きょしうせつ)
・立ち居振る舞いが不器用なこと。
・動作が間が抜けていて、要領を得ないこと。
・「挙止」は、動作、挙動の意。
・「迂拙」は、不器用の意。
 挙止進退(きょししんたい)
挙止進退(きょししんたい)
・人の立ち居振る舞いや身の処し方。
・類義語 :「起居動作(ききょどうさ)」「起居動静(きこどうじょう)」
「行住坐臥(ぎょうじゅうざが)」「挙止動作(きょしどうさ)」
「挙措動作(きょそどうさ)」「挙措進退(きょそしんたい)」
「坐作進退(ざさしんたい)」
 虚実皮膜(きょじつひまく)
虚実皮膜(きょじつひまく)
・芸は実と虚の境の微妙なところにあること。
・事実と虚構との微妙な境界に、芸術の真実があるとする論。
・江戸時代、近松門左衛門が唱えたとされる芸術論。
・「虚実」は、嘘と誠。 虚構と事実。
・「皮膜」は、皮膚と粘膜。転じて、区別できないほどの微妙な違いのたとえ。
 魚質竜文(ぎょしつりゅうぶん)
魚質竜文(ぎょしつりゅうぶん)
・実質は魚であるのに、外見はあたかも竜のように見えること。
・正しいように見えて、実際には間違っていることのたとえ。
・表面は立派に見えるが、内実はないことのたとえ。
 魚菽之祭(ぎょしゅくのまつり)
魚菽之祭(ぎょしゅくのまつり)
・魚や空豆などの日常の食べ物を供物とする、粗末な祭のこと。
・「菽」は、そら豆のこと。
 勝てば官軍、負ければ賊軍
勝てば官軍、負ければ賊軍
・道理はともかくとして、戦いに勝った者が正義となり、負けた者は
不正となるというたとえ。
・勝敗によって正邪善悪が決まるという意。
・類義 :「力は正義なり」「無理が通れば道理引っ込む」「強い者勝ち」
「泣く子と地頭には勝たれぬ」「小股取っても勝つが本」
 糧を捨てて船沈む
糧を捨てて船沈む
・死を覚悟して戦いに臨むことのたとえ。
・楚の項羽が鉅鹿(きょろく)の戦いで、連敗した部下を救援するために、
最後の兵を率いて参戦したとき、黄河を渡り、乗って来た船をみな沈め、
釜などの炊事道具をこわし、宿舎を焼き払い、全軍に生還の心を捨てさせ
戦ったので、秦の軍を大破することができたという故事から。
・類義 :「川を渡り船を焼く」「釜を破り船を沈む」「背水の陣」
 糧を敵に借る
糧を敵に借る
・対立者、反対者を巧みに利用することのたとえ。
・敵方の食糧を奪って使うことから。
 瓜田に履を納れず
瓜田に履を納れず
・人に疑われるような行為は避けよという戒め。
・瓜畑で靴が脱げても、瓜を盗むのかと疑われる恐れがあるので、瓜田で靴を
履きなおすことをしないという意から。
・「履を納れず(くつをいれず)」は、足を靴に入れないという意。
・類義 :「疑いは言葉でとけぬ」「李下に冠を正さず」
 臥榻の側、他人の鼾睡を容れず
臥榻の側、他人の鼾睡を容れず
・自国以外の国の独立を許さないこと。
・あくまでも天下を統一する意図があることのたとえ。
・自分の寝台のそばで、高いいびきをかいて眠っている他人を許す訳には
いかないという意から。
・「臥榻(がとう)」は、寝台。
・「鼾睡(かんすい)」は、いびきをかいて眠ること。
朝1番で旦那がコンビニにスポーツ紙を買いに走れるといいな
 ・・・
・・・
・・・





 跼天蹐地(きょくてんせきち)
跼天蹐地(きょくてんせきち)・恐れおののいて、びくびくすること。
・ひどく恐れて身の置き所のないこと。
・世間をはばかって暮らすこと。
・天は高いのに身をかがめ、大地は厚いのに抜き足差し足でそっと歩く意から。
 玉兎銀蟾(ぎょくとぎんせん)
玉兎銀蟾(ぎょくとぎんせん)・月の異称。
・「玉兎」は、伝説で月にいるという兎。転じて、月の異称。
・「銀蟾」は、伝説で月に入るというヒキガエル。転じて、月の異称。
 曲突徙薪(きょくとつししん)
曲突徙薪(きょくとつししん)・災難を未然に防ぐことのたとえ。
・煙突を曲げ、かまどの周りにある薪を他に移して、火事になるのを防ぐ意から。
・ある家で、かまどの煙突が突き出していて、そのそばに薪が積んであった。
これを見たある人が煙突を曲げて、薪は別の所に移したほうがよい、
そうしないと火事になるだろうと忠告した。
しかし、その家の主人は言うことを聞かず、火事になってしまったという話から。
 曲眉豊頬(きょくびほうきょう)
曲眉豊頬(きょくびほうきょう)・美しい女性の形容。
・「曲眉」は、三日月形にゆるやかに湾曲した美しい眉。
・「豊頬」は、ふっくらとした頬のこと。
・類義語 :「氷肌玉骨(ひょうきぎょっこつ)」「粉白黛墨(ふんぱくたいぼく)」
「明眸皓歯(めいぼうこうし)」「容姿端麗(ようしたんれい)」
 挙国一致(きょこくいっち)
挙国一致(きょこくいっち)・国民全員が心を1つにして、ある目的に向かって団結すること。
・「挙国」は、国中を挙げて、国全体の意。
 河童の屁
河童の屁・簡単で容易にできることのたとえ。
・取るに足らないことのたとえ。
・味も香りもないもののたとえ。
・河童は水中で屁をするので、力強くないことから出た言葉。
・類義 :「屁の河童」
 河童も一度は川流れ
河童も一度は川流れ・何事も最初から上手な人はおらず、下手から始めるものだということ。
・泳ぎの上手な河童でも、初めのころ1度は溺れることもあるという意から。
・類義 :「端(はな)から和尚はいない」
 刮目して相待つべし
刮目して相待つべし・今までの先入観を捨てて、新しい目で相手の変化や成長を見直さなければ
ならないということ。
・「刮目(かつもく)」は、目をこすってよく見ること。
・類義 :「刮目して之を視(み)る」
 勝つも負けるも時の運
勝つも負けるも時の運・勝ち負けは、その時々の運不運によって決まることが多いという意。
・勝ち負けは、技量や日ごろの練習、努力だけではどうにもならないところが
あるということ。
・類義 :「勝つも負けるも運次第」「勝負は時の運」
「勝つも負けるも軍(いくさ)の習い」
 渇を被て玉を懐く
渇を被て玉を懐く・表面を飾らず、内に美しい心を持っているたとえ。
・人目にはつかないが、優れた才能や見識を備えていることのたとえ。
・粗末な服を着ているが、懐には美しい宝石を抱いているという意から。
・「渇(かつ)」は、身分が低く貧しい者が着る、荒い毛織物の衣服。
 挙止迂拙(きょしうせつ)
挙止迂拙(きょしうせつ)・立ち居振る舞いが不器用なこと。
・動作が間が抜けていて、要領を得ないこと。
・「挙止」は、動作、挙動の意。
・「迂拙」は、不器用の意。
 挙止進退(きょししんたい)
挙止進退(きょししんたい)・人の立ち居振る舞いや身の処し方。
・類義語 :「起居動作(ききょどうさ)」「起居動静(きこどうじょう)」
「行住坐臥(ぎょうじゅうざが)」「挙止動作(きょしどうさ)」
「挙措動作(きょそどうさ)」「挙措進退(きょそしんたい)」
「坐作進退(ざさしんたい)」
 虚実皮膜(きょじつひまく)
虚実皮膜(きょじつひまく)・芸は実と虚の境の微妙なところにあること。
・事実と虚構との微妙な境界に、芸術の真実があるとする論。
・江戸時代、近松門左衛門が唱えたとされる芸術論。
・「虚実」は、嘘と誠。 虚構と事実。
・「皮膜」は、皮膚と粘膜。転じて、区別できないほどの微妙な違いのたとえ。
 魚質竜文(ぎょしつりゅうぶん)
魚質竜文(ぎょしつりゅうぶん)・実質は魚であるのに、外見はあたかも竜のように見えること。
・正しいように見えて、実際には間違っていることのたとえ。
・表面は立派に見えるが、内実はないことのたとえ。
 魚菽之祭(ぎょしゅくのまつり)
魚菽之祭(ぎょしゅくのまつり)・魚や空豆などの日常の食べ物を供物とする、粗末な祭のこと。
・「菽」は、そら豆のこと。
 勝てば官軍、負ければ賊軍
勝てば官軍、負ければ賊軍・道理はともかくとして、戦いに勝った者が正義となり、負けた者は
不正となるというたとえ。
・勝敗によって正邪善悪が決まるという意。
・類義 :「力は正義なり」「無理が通れば道理引っ込む」「強い者勝ち」
「泣く子と地頭には勝たれぬ」「小股取っても勝つが本」
 糧を捨てて船沈む
糧を捨てて船沈む・死を覚悟して戦いに臨むことのたとえ。
・楚の項羽が鉅鹿(きょろく)の戦いで、連敗した部下を救援するために、
最後の兵を率いて参戦したとき、黄河を渡り、乗って来た船をみな沈め、
釜などの炊事道具をこわし、宿舎を焼き払い、全軍に生還の心を捨てさせ
戦ったので、秦の軍を大破することができたという故事から。
・類義 :「川を渡り船を焼く」「釜を破り船を沈む」「背水の陣」
 糧を敵に借る
糧を敵に借る・対立者、反対者を巧みに利用することのたとえ。
・敵方の食糧を奪って使うことから。
 瓜田に履を納れず
瓜田に履を納れず・人に疑われるような行為は避けよという戒め。
・瓜畑で靴が脱げても、瓜を盗むのかと疑われる恐れがあるので、瓜田で靴を
履きなおすことをしないという意から。
・「履を納れず(くつをいれず)」は、足を靴に入れないという意。
・類義 :「疑いは言葉でとけぬ」「李下に冠を正さず」
 臥榻の側、他人の鼾睡を容れず
臥榻の側、他人の鼾睡を容れず・自国以外の国の独立を許さないこと。
・あくまでも天下を統一する意図があることのたとえ。
・自分の寝台のそばで、高いいびきをかいて眠っている他人を許す訳には
いかないという意から。
・「臥榻(がとう)」は、寝台。
・「鼾睡(かんすい)」は、いびきをかいて眠ること。










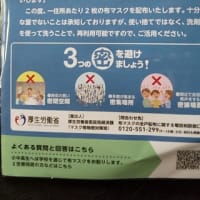










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます