 1月7日
1月7日 七草、七草粥
七草、七草粥 
春の七草を刻んで入れた七草粥を作って、万病を除くおまじないとして食べる
お節料理で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな
栄養素を補うという効能がある。
春の七草は・・・芹(せり)・薺(なずな)・御形(ごぎょう)・繁縷(はこべら)・
仏の座(ほとけのざ)・菘(すずな・・蕪)・蘿蔔(すずしろ・・大根)の7種類
 人日
人日 
五節句の一つ
古来中国では、正月の1日・・・鶏の日
2日・・・狗の日
3日・・・猪の日
4日・・・羊の日
5日・・・牛の日
6日・・・馬の日 とし、其々の日にはその動物を殺さないようにしていた。
そして、7日目を人の日として、犯罪者に対する刑罰は行われないことにした。
また7種類の野菜を入れた羮を食べる習慣があり、これが日本に伝わって七草粥となった。
日本では平安時代から始められ、江戸時代より一般に定着した。
 福岡玉垂宮鬼夜
福岡玉垂宮鬼夜 
鞍馬の火祭り・那智の火祭り等と並んで日本三大火祭りに数えられる、
1600年余の伝統のある邪気を払うお祭りで、国の重要無形民俗文化財に指定されている。
 福岡太宰府天満宮うそ替え
福岡太宰府天満宮うそ替え 
暗闇の中、参拝者が「替えましょう、替えましょう」と唱えながら、木彫りの鷽鳥を手にした
多くの人と交換し合うことにより、知らず知らずのうちに口にした
1年間のウソを、天神様の誠に変えて今年1年の幸せを願う神事。
 千円札の日
千円札の日 
1950年(昭和25年)初めて千円札が発行された。
肖像画は聖徳太子だった。
不出来の500億円分が廃棄された。
 爪切りの日
爪切りの日 
七草を浸した水に爪をつけ柔らかくして切ると、その年は風邪をひかないと言われている。
 夕霧忌
夕霧忌 
大阪の遊女・夕霧の忌日・・・・1678年(延宝6年)










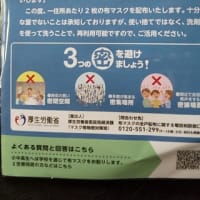










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます