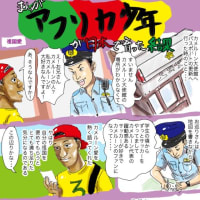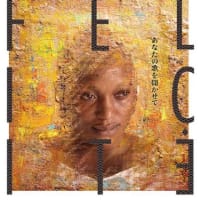コートジボワールの騒擾事件に足を取られてしまったが、一昨日の16日。ちょうど20年前に、旧ザイール共和国の「元帥(Maréchal)」、モブツ大統領の専制が終焉を迎えた日にあたる。
前日、フランス国際ラジオ放送(RFI)は、この日にレトロスペクティブを記事にしている。そのタイトルは
1997年5月16; ルワンダがモブツ体制を転覆
16 mai 1997: le Rwanda renverse Mobutu

え?ルワンダ?
そう、ルワンダなのである。
そして今のルワンダの素顔を知る、重要な横顔でもある。
20年前のこの日、ザイール32年の独裁政治に終止符が打たれた。悪名名高き独裁者、「キンシャサのヒョウ」モブツ大統領が、この国を追われモロッコに国外逃亡した。
7ヶ月にわたる第一次コンゴ戦争をへて、ローラン・デジレ・カビラ氏が、コンゴ東部からキンシャサに入城し、実権を掌握した。彼の勢力は、'ADFL: Alliance des forces démocratiques de libération du Congo'と称した。
このブログでも何度と繰り返しているが、この背後にはウガンダとルワンダが存在し、決定的な役割を演じた。このことは、もはやアフリカではよく知られた事実である。
1994年の大虐殺以降、ルワンダはザイール領のフツ系難民キャンプに逃れた旧ルワンダ兵や民兵からの脅威にさらされてきた。国際社会の無関心の前に、ルワンダ政権はこれらフツ族キャンプの掃討が必要と考えた。特にルワンダの前政権、アビャリマナ大統領はモブツ政権と親密であった。「モブツのザイールがフツをかくまう限り、ルワンダに平和はない。」ルワンダのツチ系政権のロジックだ。
歴史はさらに遡る。コンゴ、ルワンダ、ブルンジは独立前、いずれも旧ベルギー領だった。後者の二つは、第一次大戦のドイツの敗戦を受け、ベルギーの信託領となった。1962年、ルワンダとブルンジが独立する際、ルワンダでは多数派のフツが、ブルンジでは国王(ムワミ)の伝統からツチが政権を取った。ルワンダからはツチ族が、ブルンジからはフツ族が近隣国にディアスポラとなって移り住むこととなる。
隣接するコンゴ東部。伝統的ツチ系住民を「バニャムレンゲ」と呼ぶ。ルワンダのフツ政権に近かったモブツはバニャムレンゲを冷遇し、のけ者とした。ローラン・デジレ・カビラはその一人だった。
話はどんどんずれていくが、ローラン・デジレ・カビラはコンゴ史の中に古くから登場する人物だ。コンゴ独立黎明期の60年代、世界は冷戦の覇権がぶつかり合っていた。その中でキューバのフィデル・カストロは、アフリカ共産主義革命の本拠をコンゴと定め、一時チェ・ゲバラがコンゴで共闘を行う。ローラン・カビラはその「同志」であった。
しかし革命の士を謳うコンゴ人たちは、夕方になると家に帰り、夜な夜な奏でる音楽でダンスを興じるというのどかさ。ゲバラは「コンゴ人に、革命はムリ」と諦めてコンゴを後にした話は有名である。
話を戻そう。そういうことで1997年に、コンゴ政権奪取のための作戦、第一次コンゴ戦争に突入する。コンゴ東部からキンシャサまで、遥か遠い、時差のある距離をローラン・カビラは勢力下に置いていく。これを支援したのがルワンダでありウガンダであった。ウガンダはヨウェリ・ムセベニ、いまも大統領。ルワンダはポール・カガメ、やはり現在も大統領だ。先述の「ルワンダ出自のツチ系ディアスポラ」にあたる。
実はこの両者、ウガンダにおいて反政府勢力として共闘した。86年にムセベニによるウガンダ、オボテ政権転覆で政権奪取。のち、94年のルワンダの大虐殺の期に、キガリに入城したのがポール・カガメである。その背後にはアングロ・サクソン連合の支援、特に星条旗の影が強くつきまどう。最後までモブツとアビャリマナを支援したフランスやベルギーのフランコフォンと対峙した。
再び1997年に戻ろう。主にルワンダに支えられたローラン・デジレ・カビラの軍は、ほとんど武力抵抗に会うことなく、キンシャサに入城したという。
キンシャサで政権を掌握したカビラは、ルワンダ、ウガンダの影響力から逃れようと、両国との関係を断ち切ろうとする。大きな「裏切り行為」だ。
これを受け、ルワンダ、ウガンダ両国は、コンゴ東部に攻め入っていく。これが第二次コンゴ戦争である。しかしその「引き金」は、単にカビラと両国の「兄弟の契り」の破断だけにとどまらない。前述の残留フツ系勢力の掃討、そしてコンゴを攻めるには、もっと大きな理由があったのだ。
あ、もうお時間?
この続きはまた近日。
追伸: 脱線の連続で読みにくくてすみません。コンゴとなるとついつい、、、。
(つづく)
前日、フランス国際ラジオ放送(RFI)は、この日にレトロスペクティブを記事にしている。そのタイトルは
1997年5月16; ルワンダがモブツ体制を転覆
16 mai 1997: le Rwanda renverse Mobutu

え?ルワンダ?
そう、ルワンダなのである。
そして今のルワンダの素顔を知る、重要な横顔でもある。
20年前のこの日、ザイール32年の独裁政治に終止符が打たれた。悪名名高き独裁者、「キンシャサのヒョウ」モブツ大統領が、この国を追われモロッコに国外逃亡した。
7ヶ月にわたる第一次コンゴ戦争をへて、ローラン・デジレ・カビラ氏が、コンゴ東部からキンシャサに入城し、実権を掌握した。彼の勢力は、'ADFL: Alliance des forces démocratiques de libération du Congo'と称した。
このブログでも何度と繰り返しているが、この背後にはウガンダとルワンダが存在し、決定的な役割を演じた。このことは、もはやアフリカではよく知られた事実である。
1994年の大虐殺以降、ルワンダはザイール領のフツ系難民キャンプに逃れた旧ルワンダ兵や民兵からの脅威にさらされてきた。国際社会の無関心の前に、ルワンダ政権はこれらフツ族キャンプの掃討が必要と考えた。特にルワンダの前政権、アビャリマナ大統領はモブツ政権と親密であった。「モブツのザイールがフツをかくまう限り、ルワンダに平和はない。」ルワンダのツチ系政権のロジックだ。
歴史はさらに遡る。コンゴ、ルワンダ、ブルンジは独立前、いずれも旧ベルギー領だった。後者の二つは、第一次大戦のドイツの敗戦を受け、ベルギーの信託領となった。1962年、ルワンダとブルンジが独立する際、ルワンダでは多数派のフツが、ブルンジでは国王(ムワミ)の伝統からツチが政権を取った。ルワンダからはツチ族が、ブルンジからはフツ族が近隣国にディアスポラとなって移り住むこととなる。
隣接するコンゴ東部。伝統的ツチ系住民を「バニャムレンゲ」と呼ぶ。ルワンダのフツ政権に近かったモブツはバニャムレンゲを冷遇し、のけ者とした。ローラン・デジレ・カビラはその一人だった。
話はどんどんずれていくが、ローラン・デジレ・カビラはコンゴ史の中に古くから登場する人物だ。コンゴ独立黎明期の60年代、世界は冷戦の覇権がぶつかり合っていた。その中でキューバのフィデル・カストロは、アフリカ共産主義革命の本拠をコンゴと定め、一時チェ・ゲバラがコンゴで共闘を行う。ローラン・カビラはその「同志」であった。
しかし革命の士を謳うコンゴ人たちは、夕方になると家に帰り、夜な夜な奏でる音楽でダンスを興じるというのどかさ。ゲバラは「コンゴ人に、革命はムリ」と諦めてコンゴを後にした話は有名である。
話を戻そう。そういうことで1997年に、コンゴ政権奪取のための作戦、第一次コンゴ戦争に突入する。コンゴ東部からキンシャサまで、遥か遠い、時差のある距離をローラン・カビラは勢力下に置いていく。これを支援したのがルワンダでありウガンダであった。ウガンダはヨウェリ・ムセベニ、いまも大統領。ルワンダはポール・カガメ、やはり現在も大統領だ。先述の「ルワンダ出自のツチ系ディアスポラ」にあたる。
実はこの両者、ウガンダにおいて反政府勢力として共闘した。86年にムセベニによるウガンダ、オボテ政権転覆で政権奪取。のち、94年のルワンダの大虐殺の期に、キガリに入城したのがポール・カガメである。その背後にはアングロ・サクソン連合の支援、特に星条旗の影が強くつきまどう。最後までモブツとアビャリマナを支援したフランスやベルギーのフランコフォンと対峙した。
再び1997年に戻ろう。主にルワンダに支えられたローラン・デジレ・カビラの軍は、ほとんど武力抵抗に会うことなく、キンシャサに入城したという。
キンシャサで政権を掌握したカビラは、ルワンダ、ウガンダの影響力から逃れようと、両国との関係を断ち切ろうとする。大きな「裏切り行為」だ。
これを受け、ルワンダ、ウガンダ両国は、コンゴ東部に攻め入っていく。これが第二次コンゴ戦争である。しかしその「引き金」は、単にカビラと両国の「兄弟の契り」の破断だけにとどまらない。前述の残留フツ系勢力の掃討、そしてコンゴを攻めるには、もっと大きな理由があったのだ。
あ、もうお時間?
この続きはまた近日。
追伸: 脱線の連続で読みにくくてすみません。コンゴとなるとついつい、、、。
(つづく)