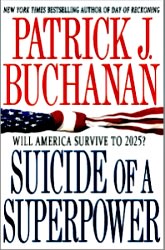王冠を賭けた恋 ウインザー公物語:
King Edward VIII Audio : MP3:
1936: British press finally break silence on Wallis Simpson affair:
THE DUCHESS OF WINDSOR ~ KISS OF FIRE ~ ANNE SHELTON:
エドワード8世とミセス・シンプソン :
有名な事件なので、以前に少し調べたことがある。微かな記憶では、相手はとんでもない女で、ウインザー公のその後の人生は不幸で惨めであった、というものだった。
今回書く事に決めて女性の顔をよく見たら、吉本新喜劇の桑原和男を真っ先に思い出した。
ご存知の方はきっとなるほど似ていると同意されるだろう。
世紀の恋と騒がれたこのカップルとは違い、同じ恋でもチャールズとカミラ夫人は、確かに気の毒だ。あのカップルにあこがれの視線を向ける英国人は非常に少ないだろう。
同じ恋なのに、ね。
今回調べて二つのことを書いておくべきだと思った。
〇Was Wallis Simpson all woman? There's been always been speculation about her sexual make-up. Now in a major reassessment her biographer uncovers new evidence
簡単に言うとシンプソン夫人が性同一障害者であるという記事である。体の肉付き、特に顔の肉付きが男なのだ、ホント桑原和男のおばあちゃんの写真と見比べたら納得していただけるだろう。納得できる噂である。
〇Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von Ribbentrop、ナチスのリッベントロップと関係を持っていたという、これは記録である。イギリスの情報をドイツに流していたとすれば、スパイの疑いさえ出てくる。エドワード8世が王冠を捨てなければならなかったのは、そのためだとも言われている。チャーチルが権力を行使する以前は、英国に親独派の勢力もかなりあったことも知っておくと良いだろう。それにルドルフ・ヘスが和平の書を携えてただひとり英国に飛んだ背景も忘れてはならない。加えてKen Ishiguroの「日の名残り」にも、親独派の英国貴族たちがたくさん出てくる。英国が一団となってドイツとの戦争を望んでいたわけではない。ヒットラーが血に飢えた野犬だったわけでもない。チャーチルが突出して対独戦を望んでいたのだ。
ヒットラーの精神分析をするよりもチャーチルが権力の座につくその背景を調べる方が、歴史の解明には役立つだろう。
・・・・・・・・・・・・・・・
今回調べてマドンナ監督の以下の映画の存在を知った。
映画『ウォリスとエドワード 英国王冠をかけた恋』予告編 :
マドンナ監督インタビュー映像 :
シネマ日記:映画感想
マドンナにはマドンナのとらえ方、映画には映画の捉え方があるということだろう。
マドンナ→映画→シンプソン夫人→歴史、という興味や関心の移動も期待してみたい。
この記事を書いたひとつの動機でもある。
西尾幹二氏のblogにこの本の紹介が出ていた。
参照:Pat Buchanan : Suicide of a Superpower :
参照:Pat Buchanan on Suicide of a Superpower :
参照:Pat Buchanan : Suicide of a Superpower:
参照:Pat Buchanan : Suicide of a Siperpower:
以前Tel Quel Japonでこの人の本を紹介したことがある。
Tel Quel Japon 過去記事:Tel Quel Japon過去記事:
上の本の翻訳者は西尾幹二氏の高校時代の
同級生、 河内隆弥氏。次回の翻訳書が
かつてTel Quel Japonで紹介した下の
The Unnecessary War by Pat Buchanan の予定らしい。
こちらの本は第二次世界大戦に関する歴史書で
興味津々であったが、Buchananの最新の上の本は
アメリカ人によるアメリカ
白人による白人の世界の不満を扱ったもので
こういう視点でものを考えるのか
という新鮮さはあったが、日本人には切実さはない。
がその分「そうか、なるほど」と気づかされる部分は多い。
・・・
最近これはなにかの手違いで買ってしまったのだが
いま手元にカレル・ヴァン・ウォルフレン著
「アメリカとともに沈みゆく自由世界」(徳間文庫)がある。
まだところどころ寝る前に読み飛ばしているだげだが
タイトルからもわかるように、上の本の内容と
多くの類似性がある。
「こんな国ではなかったはずなのに」
というのはどの国の国民も感じるものだなと、そんな気分だ。
実際どの国でも、自国の国益などを考えて
国の政治が行われている訳ではないのかもしれない、と感じる。
「おかしい」と気づいてきたことも「そうなのか」と納得
してきたことも、さほど違いはないのかもしれない。
つまり国民の納得と歴史や政治の動きとは
本来別次元のことなのかもしれない。
(こうくると国際金融資本家連合の陰謀論に帰結して
しまいそうだが、まあ、それはそれとして)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
以前開戦時に米国ではどんな曲が大ヒットしていたのか
調べたことがある。この曲だった。
(多分戦後に購入したものと思われますが、この曲
父のレコードコレクションの中にもありました)
ルーズベルトは「あなたの息子さんを戦争に送り出すことは
絶対に絶対に絶対にありません、と約束します」と言っていたのだし。
アメリカの皆さんはそれは楽しく暮らしておられたのでしょう。
しかしその後の歴史では米国民が「パール・ハーバー」で怒り狂って
立ち上がったことになっていますが、そしてまたそのアメリカ国民の激怒を
今までそれなりに納得してきましたが、
今回ウォルフレンの本のあるペイジを見てある考えが浮かびました。
ハワイはアメリカからどれだけ離れているか、
ハワイは戦争せずに単にだまくらかしていつの間にか手に入れた
(まだ正式な州でもない)
ハワイに本国からどれくらいのアメリカ人が植民していたか
(日系人及び日本人が人口の4割を占めていた)
アメリカ人は太平洋上のオアフ島が米国自治領だとそもそも知っていたか
つまりハワイが自国民の暮らす国土だという認識があったのか
などなどいろいろ考えてしまったのです。
アメリカ人が激怒するほど、パールハーバーは
本土のアメリカ人と一体化はしていなかった、という結論に達しました。
オアフ島の大海軍基地を除けば、ハワイ住民の帰属意識も
むしろ日本国よりではなかったか、と。
そして結論としてこの演説が、
アメリカ国民の我を忘れた激怒を醸造したのだ、と。
アメリカ国民はこの演説に完全にのせられたのだ、と。
つまりまたしても、今回は別の角度から
すなわちハワイからの視点で
「ルーズベルトパールハーバー陰謀論」に帰着したのでした。