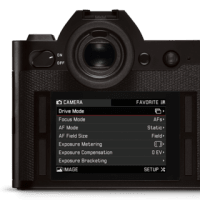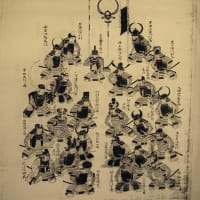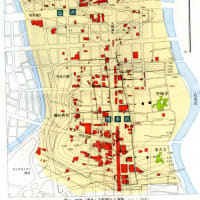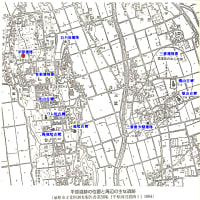|
M10 Black Chrome Body 外見は少し薄くなったが基本的には伝統のLeica Mスタイル。 しかし、その中身、すなわち心臓と脳が大幅に力をつけた。 |
|
M10 Silver Chrome Body
|
今年の1月18日ドイツで発表されたライカのMシリーズの最新機、M10がついに日本でも1月28日に発売開始となった。昨年のフォトキナでの新型Mの発表がないな、と思っていたら、今年になって急にリリースのアナウンスがあった。これは2012年10月のフォトキナで発表され翌年3月に発売となったM Type240から4年目の新型Mライカだ。例によって入荷した実機は極めて少数で、ライカショップや公認ディーラーで手に入れた人は限られていたようだ。なぜライカはいつもこうなのか? M Type240の時は、次の入荷が半年後だった。ライカショップ銀座に問い合わせると「今度は3ヶ月後くらいには入荷するから、それほどお待たせすることはありませんと」。それだけ待てば十分だろう。これもライカ商法なのか。私の商売の経験上、市場投入のタイミングと投入量は極めて重要だということ疑ったことはないのだが。注文生産ならともかく、コモディティー化した商材と「高付加価値商材」では出荷ロジックが違うのか? 会社業績は好調なのだから間違った戦略ではないのかもしれないが。M10発表時のインタビューでライカの新CEOは、これまでのライカ社のマーケティング、営業の姿勢を変え、「発売時の製品の完成度と市場投入量を改善する」と言っていたのをただ思い出しただけだ。
今回は製品名はLeica M10となった。M9の後継機という位置付けのようだ。これまでのM Type240は併売するという。じゃあM Type240のMシリーズでの位置付けはなんなのか? 動画撮影機能がついたMシリーズの派生製品だったとでもいうのか? ライカ社の説明だと、MシリーズはType240以降はTypeナンバーで系列化する、といったん決めたのだが、やはり元のMナンバーに戻すことにしたのだとか。その理由はユーザーがM240と呼ぶようになったので、混乱し紛らわしくなったからだと。どうでも良いがあんまり一貫したしたネーミングポリシーに見えない。後付けでいろいろ言い訳しているようにしか聞こえない。ライカ社の市場戦略は、ビジネスケーススタディーとして非常に興味深いものがあることはこれまでもなんども述べた。時に違和感満載だったりするのでライカを語るとどうしても、辛口のコメントから入ってしまう。それだけ「いじられやすい」カメラなのだ。孤高の人はいじられやすい。
しかし今回のM10は、非常に完成度の高いMに仕上がったと感じる。先日ライカショップで実機を手に取る機会があったが、なかなか手ごたえを感じることが出来た。あのM8登場時の、まだ試作品のまま売り出してしまったんじゃないかと思ってしまうような未熟さと、バグや???マーク満載のデジタルカメラ(また辛口!)から10年、「遅々として進んできた!」(またまた辛口!)デジタルカメラ化の進歩が、とうとう完成の域に到達した感がある。Type240でもかなり完成度が上がったと思っていたが、デジタルカメラとしての機能(特にライブビュー機能)、高感度特性、撮影・読み出し処理速度の改善、したがって撮影のサクサク感が大幅に良くなった。これまで何度も言ってきた通り、Mをデジタルカメラにする以上、デジタルカメラとしての信頼感・安定感と機能の高度化を目指して欲しい。それがようやく実現した。これは画期的だと言わざるを得ない。
世の中はミラーレス時代。プロ用機材やハイエンド機材としても使用に耐えうるミラーレス製品が続々と市場投入されてきている。こうした中、いつもMの新製品が噂されるたびに、次のライカMはレンジファインダーを無くすのでは?といわれつつ、結局はなくならない。昨年、ライカ社はMとは別のラインアップを市場に投入し、ミラーレスはSLやTL,Qなどのシリーズでカバーし始めた。したがって伝統のMはあくまでもMとしてシリーズ化してゆく。レンジファインダーとったらMじゃない。ライカのアイデンティティーがなくなってしまう。クラウンジュエルは死んでも離さない。ニコンやキャノンがプロ用機材はあくまでも光学プリズムとミラーを使った一眼レフにこだわるのと同じだ。外見も頑なにM3からのラウンドシェイプを守っている。一時期M5で弁当箱型の大きなサイズに変えて評判を落としたのに懲りたのか、M6で元に戻した。しかしデジタル化した時、M8ではボディーは厚みを増し、全体に若干大型化した。以降M9, M Type240とこのボディーサイズを継承したところ、これに違和感を感じるユーザーが思いのほか多かったという。そいう意味で、今回のM10の最大の売りは、そのボディーサイズがM9やM Type240より4mmほど薄くなって「とうとうM3のそれと同じになった」ことだという。実装技術イノベーションで伝統的なサイズにリパッケージできた。これがM10の最大の特色というわけだ。さすがライカ社は技術ブレイクスルーの使いどころが違う。ライカユーザーはそんなに保守的なのか。拘ってるなあ。
M10の特色
1)ボディーサイズが4mm薄くなった(ライカ社はこれが最大の特色だと言っているのだから、これを一番に挙げるべきなのだろう)。
2)画像エンジンがMaestro II (S, SL, Qと同じ)となり、高速でレスポンスが良くなった。特にライブビュー機能が大幅に改善した。
3)新しい2400万画素CMOSセンサー(ローパスフィルターレス)を開発し、Maestro IIとのチューニングで画像再現性(ダイナミックレンジ、高感度特性、周辺部画質など)が大幅に改善した。特に2400万画素のまま低輝度撮影の画質を大幅に改善した。色味はM9を再現したという。
私はこの三点に尽きると思うが、そのほかのType240からの変更点をいくつか挙げると、
1)ビデオ撮影機能を廃止(Mには不要というユーザが多かったそうだ。私もだが)。
2)ISO感度ダイアルを軍艦部に設けた(相変わらず露出補正ダイアルは設けない)。
3)光学ファインダーの視野率が30%広がり見やすくなった。
4)外付けEVFはTL用のものを利用し解像度が増して見やすくなった。GPS機能付き。
5)WiFi搭載、スマホアプリとの連携。
6)フレームセレクタレバーを復活。
7)水準器機能を廃止(なぜ?)。
8)背面の機能ボタン数を減らした(削除ボタンも廃止)。
9)ストラップ擦れ防止ペグを廃止(傷がついても構わない)。
10)ブラックボディーはペイントからクロームに(「剥げ」を楽しめない)。
11)バッテリーがボディーサイズに合わせ薄型になった(動画もないので小型化)。
12)バッファーメモリーを2Gに増やし、連写機能が向上(Mで連写はしないが...)。
何よりも、新しい画像エンジンMaestro IIと新CMOSセンサーでサクサク感が大幅に改善したのが一番だ。とくにライブビュー撮影でのレスポンスが良くなり、ミラーレスカメラとしての実用性が大きく改善した。Maestro IIは昨年発売されたミラーレス機であるSLとQに取り入れられており、その使用感は馴染みになっているだけに、同じ感覚でM10と向き合えるのは嬉しい。私はフレームの外側を見ながら「予想撮影する」というライカ使いの達人でもないし、ストリートフォトグラファーでもないので、結局、レンズとファインダーの視差がある不正確なフレーミングのレンジファインダーを多用することはない。もちろんクリアーな実像を光学ファインダーで見つめる喜びは共有しているが、コンパクトで良い道具感に溢れるMボディーを、きちっとしたフレーミングが取れるミラーレス機として、これまでのオールドレンズを含むMレンズ資産を活用できることが嬉しい。これはライカ社の本意ではないかもしれない。しかしせっかくライブビュー撮影機能を備えたのに、レスポンスが悪いのでは実用にならない。かといって、ライブビューを取り払ったType242に手は伸びない。そこまで私はストイックではない。デジタルカメラになった以上、最小限のデジタル化の恩恵を享受したいだけだ。惜しむらくはQのようにEVFを内蔵してくれると一番なのだが(Fujifilm X-Proのようなハイブリッドファインダーは凄いと思う)。スリークなボディーラインを楽しむカメラにプラスチック製の外付けファインダーは似合わない。
また、高性能な画像エンジンと合わせて新規に開発された2400万画素CMOSセンサー(サードパーティー製)は、画像再現性が一段と良くなった。特に階調の豊かさはもともとライカMレンズの特色だが、ボディー側もそれを支える最適プラットフォームになった。シャドウ部の情報量をキープして潰れない。撮影後の後処理にも耐えうる高品位な画像データを生み出してくれるボディだ。またISO感度は100~50,000と拡大し、画素数を減らすことなく(2400万画素のままで)高感度特性が大幅に改善してノイズが少なくなった点も特筆に値する。これはavalable lightでの撮影を重視するライカ使いには大事な進化だろう。色味は、いろいろな市場調査からM9時代のCCDセンサーのそれにしたという。具体的にはGentle&Warm。それとCosyだそうだ。巷にはMシリーズのCMOSよりもCCDの画を好むユーザーがいることは知っていたが、それほどなのか。私にはよく分からない。これは好みがあるだろう。これまでと同様ローパスレスなので高解像度である点は変わらない。ただセンサー前のカバーガラスを改良してMレンズからの入射光が受光素子に対して最適になるよう再設計されているという。やはりこうした点からもMレンズに最適のボディーはやはりMボディーだということになる。ボディーサイズの改善も重要だが、この画像エンジン(Maestro II)と、新たに開発された2400万画素CMOSセンサー。カメラの脳と心臓の大幅な進化がやはりこのM10の特色だと感じる。
ライカMは、デジタルになってもフィルム時代から長年使ってきたフォトグラファーの手に馴染む形と操作感を大事にしてきた。数字上のスペックよりも道具としての使い心地を大事にしてきた。そういう意味において、その使い心地の継続性を新しいデジタルプラットフォームの上でも実現させなければならない。デジタルカメラ化した以上、その基本性能のブラッシュアップは必須であったはずだ。今回、レンジファインダーが見やすくなって、ボディーサイズがフィルム時代のMに戻ったことはもちろん画期的であるが、それとともに、10年の試行錯誤の末に得た新しい画像エンジンと画像センサーを導入し、タフで繊細で頭の回転が速いデジタルカメラとしてのクオリティー、能力が大幅に改善したこと、これが私にはとっては一番嬉しい。
|
外付けEVF シンプルな背面ボタン配置 |
|
軍艦部左にISO感度ダイアル 電源スイッチ部はオン・オフのみで連写クリックがなくなった |
(写真はライカジャパンのHPより引用)
(参考)Leica M Type240に関する過去のブログ:
2015年10月6日:Leica M (Type240) 〜2年目の使用レポート〜
2013年4月5日:Leica M( Type240) の使用感など 〜ライカのジレンマ〜
2012年10月26日:Leica Mという画期 〜MはやはりMなのか?〜