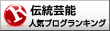箏と三味線と、両方演奏なさる方も多いが、楽器に対する志向性は、はっきり分かれるような気がする。私は箏の音色も好きだが、13本も絃がある楽器なんて、とてもとても使いこなせそうにない。…3本の糸でどんな音でも出せる、単純ながら無限の掛け算の魅力がある。それが三味線のいいところ~♪で、いつの間にか四半世紀を超えて付き合う羽目になった。
以前、はじめて地唄の曲を演奏する機会があったときに、その微妙な速度の曲運びに、大変てこずった。今でいえば、「イライラする」。まあ、確かに三十過ぎた頃だった。
長唄は江戸・東京のものだから、テンポもすっきり溌溂としている。それに対して地唄のテンポはどうにも、ゆったりしすぎて間延びしてるような感じで、参った。
しかし、それが不思議なもので、何度も弾いているうちに、その焦燥ともいえるまったり感が、この上なく快感に思えてきた。あの、ウヴィーン、イン…という揺らぎが何ともいえずいい感じに変わっていったのだ。
そのとき、東京生まれの谷崎潤一郎が、なぜあんなに上方を愛好するようになったのかが、何となくわかったような気がした。
以前、はじめて地唄の曲を演奏する機会があったときに、その微妙な速度の曲運びに、大変てこずった。今でいえば、「イライラする」。まあ、確かに三十過ぎた頃だった。
長唄は江戸・東京のものだから、テンポもすっきり溌溂としている。それに対して地唄のテンポはどうにも、ゆったりしすぎて間延びしてるような感じで、参った。
しかし、それが不思議なもので、何度も弾いているうちに、その焦燥ともいえるまったり感が、この上なく快感に思えてきた。あの、ウヴィーン、イン…という揺らぎが何ともいえずいい感じに変わっていったのだ。
そのとき、東京生まれの谷崎潤一郎が、なぜあんなに上方を愛好するようになったのかが、何となくわかったような気がした。