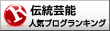旧暦の七夕も過ぎまして、いよいよ秋ですね…
酷暑に喘ぎつつ見上げる空は、そこはかとなく憂いを含んだ…そう、秋の色をしています。
しかし、21世紀市民としてはその前に、夏休みの宿題を仕上げなくてはなりません。
今年も、夏休みの自由研究のお助け番といたしまして、親子三味線体験会を行います。


※photoはこの初夏、芝増上寺御門跡のご門前を撮影させていただいたもので、記事内容とは直接関係なきものにて候。
親子でなくても、お一人でも、学生さんでなくても、構いません。
……三味線を弾いてみたい、長唄をうたってみたい…
合言葉はかくの如し、思い立ったが吉日。
日程は
下北沢教室:8月13日(火)、17(土)、24(土)、27(火)、28(水)
池袋教室:8月15(木)、29(木)、31(土)
お時間は10時~20時の間、完全予約制です。
お電話は0334680330 または♪三味っちゃおうホームページより、
ご希望時間を3つぐらいご記入の上、お申し込みください。
調整いたしますので、よろしくお願いいたします。

費用は無料です。
愛するものができた時、勇気をもって人生に立ち向かうべし…
…とはどなたのお言葉だったやら、
愛するものがないときは、何かしら愛着が持てるものを探しにお出かけになってくださいまし。
お待ちしております。

酷暑に喘ぎつつ見上げる空は、そこはかとなく憂いを含んだ…そう、秋の色をしています。
しかし、21世紀市民としてはその前に、夏休みの宿題を仕上げなくてはなりません。
今年も、夏休みの自由研究のお助け番といたしまして、親子三味線体験会を行います。


※photoはこの初夏、芝増上寺御門跡のご門前を撮影させていただいたもので、記事内容とは直接関係なきものにて候。
親子でなくても、お一人でも、学生さんでなくても、構いません。
……三味線を弾いてみたい、長唄をうたってみたい…
合言葉はかくの如し、思い立ったが吉日。
日程は
下北沢教室:8月13日(火)、17(土)、24(土)、27(火)、28(水)
池袋教室:8月15(木)、29(木)、31(土)
お時間は10時~20時の間、完全予約制です。
お電話は0334680330 または♪三味っちゃおうホームページより、
ご希望時間を3つぐらいご記入の上、お申し込みください。
調整いたしますので、よろしくお願いいたします。

費用は無料です。
愛するものができた時、勇気をもって人生に立ち向かうべし…
…とはどなたのお言葉だったやら、
愛するものがないときは、何かしら愛着が持てるものを探しにお出かけになってくださいまし。
お待ちしております。