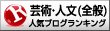蝉の声が音取となって、過ぎにし時の事どもが、前頭葉の斜め30度上方、空気の襞の間に閃く。
「こんばんは、古谷綱正です」と、穏やかながらも頼もしいおじいさんがブラウン管の向こうから夜6時のニュースを伝えるのを茶の間で見るのが、我が家の常だった。子どもの目にはおじいさんだったけれども、きっと今の私より年齢は若かったかもしれない。
テレビで伝えることは子供たちが真似をするので、きちんとしていなくてはいけない、というのが昭和の良識でありました。2018年の今、日本のテレビではニュース番組すら、スラングが飛び交っておりますね。記事の文法、てにをはさえもが、怪しい状況なのだ。
常識の判断で、という言葉があったが、インターネットがここまで普及するとわけのわからない少数意見(私もかも…)が独り歩きするような事態になってしまい、良識ある見解というものがもはや死に体になっている、という状況が、昨今見られる混沌たる世相ではなかろうか。
アメリカ自由主義の下、核家族化が進み、若者たちはたいそう羽を広げたが、これは歴史あるおばあちゃんの知恵袋の集積だった日本社会にとってはとても勿体ない、惜しむべきことだったかもしれない。
無知ゆえの不幸、とでも申しましょうか、えっと思うほどビックリする、突拍子もないニュースも増えた。
未開の新天地は気持ちのいいものだが、裏を返せば荒野なんである。
何もないから一から始めないといけない。
もったいないなぁ。先祖が試行錯誤して積み上げてきた叡知、智恵を、21世紀にもなって活かすことができないなんて。
そしてまた年寄りの意見によって世間のコンセンサスを身につけていたのが、昭和の子供たちでありました。
大人=社会だから、ぢいさんばぁさんの顔色を見ていれば、ぁぁこういったことをやれば非難の対象になるわけか…などと日常的な知識や見識、常識が身についたのだった。
地域によっても違うかもしれないが、昭和40年代に関東地方で小学生だった者には、道徳の授業は確かにあって、ただ前時代の修身というほど押しつけがましいものではなく、様々な事例のお話を、どう思うか、どうしたらよかったか、自分だったらどうするのか、子供心に考えさせるような、結論のないお噺集が道徳の教科書だったように記憶している。
さて、実は道徳の教科書に載っていたのか、世界偉人伝だったのか(そいえば「ちえをはたらかせたお話」という子ども向けの寓話集のようなアンソロジーもありました)何の本から伝え聞いた物語だったのか忘れてしまったのだけれども、教師とはどうあるべきかという命題の一つを顕したお話、というので、忘れられないのがペスタロッチ先生のエピソードなのである。
記憶に拠っているので、誤った認識、錯誤などがありましたら、ごめんなさい。ご容赦くださいませ。
18世紀半ばから19世紀にかけての、ヨーロッパのとある国でのお話です(たぶん)。
とある学校の放課後、子供たちが元気に校庭で遊んでいる。その傍らでキラリキラリと光るものを拾っている先生がいた。それを見ていた学外の者が、あの先生は落ちている硬貨を拾って私しているのではないかと邪推します。
糺されたペスタロッチ先生のポケットは、たしかに何かでいっぱいになって膨らんでいました。
でもそれは、校庭に落ちていた石やガラスの欠片、折れ釘などでした。その学校は貧しい子供たちがたくさん通ってきます。みな靴を買うことができないので裸足なのです。子どもたちが怪我をしないように、ペスタロッチ先生は見守りながら、校庭の危険なものを取り除いていたのです。……
日本国内でも学校の校庭からいろいろなものが出てきて工事が遅れ、開校できなくなった…と、つい最近何かで耳にしたような気もするが、人間の歴史とは、ついこの間まで、そんなに豊かじゃなかったのです。選挙権だってつい70年前まで女性には認められてなかったのです。人間個々人がこんなに自分の権利を主張できる世の中になったのは、ほんのつい最近のことなのに、なぜみんな選挙に行かないの…(余談でした)
過去の物語の方向性をあげつらったり、校閲・考証をするわけではないので、さて今一読すると突っ込みどころ満載のお話ではあるが、たとえ話というのは、その現象から真理をつかみ出すことを目的としているので、漫才のネタにして笑いどころを探す必要はないのである。
医療機器や化学工業の先進技術の発達たるや、驚かんばかり。文明の利器によってますます快適な生活ができるようになったのに、先祖がえりどころか、人間の質が低下しているような気がしてならない。肝心の人間が啓かれなくては、進歩どころではないではないか。
人間が生きていくうえで大切な、思想、情操というものを養わなくては、社会はしあわせにはならない。無念のうちにこの世を後にした先人たちが、浮かばれないというものである。
夏山シーズンになると、新田次郎原作、森谷司郎監督の「聖職の碑(いしぶみ)」という映画を想い出す。
その映画のCMを録りたくて、テレビの前でテレコを用意して待っていた女子高生。そのCMのナレーションを日本アニメーション「母をたずねて三千里」のマルコのお兄さん役だった曽我部和行氏が担当していたのだった。
同番組の挿入歌♪母さんがいなくても陽気に育つ子があるものさ…の歌声がとても好きだった私は、例によってオタク魂を発揮して、贔屓の声優さんの声を蒐集していたのだ。思えば生涯声フェチなのかもしれない。能の御シテ方の先生も、まず、声が佳くなくては好きになれない。
そして、今でも昭和50年代に活躍していた声優さんの声は一聞にして、どれが誰だか識別できる(なんの自慢話でしょう………)。
いえいえ、このカンは現在の職業に役立っていると申せましょうか、知恵ではなく耳を働かせたお話ですね。
行楽の日々、皆さま、本当にご無事で……
弟子ほどかわいいものはない。師匠ほどありがたいものはない。
…というのが、修業道に身を置くものすべての、偽らざる心境でありましょう。
「こんばんは、古谷綱正です」と、穏やかながらも頼もしいおじいさんがブラウン管の向こうから夜6時のニュースを伝えるのを茶の間で見るのが、我が家の常だった。子どもの目にはおじいさんだったけれども、きっと今の私より年齢は若かったかもしれない。
テレビで伝えることは子供たちが真似をするので、きちんとしていなくてはいけない、というのが昭和の良識でありました。2018年の今、日本のテレビではニュース番組すら、スラングが飛び交っておりますね。記事の文法、てにをはさえもが、怪しい状況なのだ。
常識の判断で、という言葉があったが、インターネットがここまで普及するとわけのわからない少数意見(私もかも…)が独り歩きするような事態になってしまい、良識ある見解というものがもはや死に体になっている、という状況が、昨今見られる混沌たる世相ではなかろうか。
アメリカ自由主義の下、核家族化が進み、若者たちはたいそう羽を広げたが、これは歴史あるおばあちゃんの知恵袋の集積だった日本社会にとってはとても勿体ない、惜しむべきことだったかもしれない。
無知ゆえの不幸、とでも申しましょうか、えっと思うほどビックリする、突拍子もないニュースも増えた。
未開の新天地は気持ちのいいものだが、裏を返せば荒野なんである。
何もないから一から始めないといけない。
もったいないなぁ。先祖が試行錯誤して積み上げてきた叡知、智恵を、21世紀にもなって活かすことができないなんて。
そしてまた年寄りの意見によって世間のコンセンサスを身につけていたのが、昭和の子供たちでありました。
大人=社会だから、ぢいさんばぁさんの顔色を見ていれば、ぁぁこういったことをやれば非難の対象になるわけか…などと日常的な知識や見識、常識が身についたのだった。
地域によっても違うかもしれないが、昭和40年代に関東地方で小学生だった者には、道徳の授業は確かにあって、ただ前時代の修身というほど押しつけがましいものではなく、様々な事例のお話を、どう思うか、どうしたらよかったか、自分だったらどうするのか、子供心に考えさせるような、結論のないお噺集が道徳の教科書だったように記憶している。
さて、実は道徳の教科書に載っていたのか、世界偉人伝だったのか(そいえば「ちえをはたらかせたお話」という子ども向けの寓話集のようなアンソロジーもありました)何の本から伝え聞いた物語だったのか忘れてしまったのだけれども、教師とはどうあるべきかという命題の一つを顕したお話、というので、忘れられないのがペスタロッチ先生のエピソードなのである。
記憶に拠っているので、誤った認識、錯誤などがありましたら、ごめんなさい。ご容赦くださいませ。
18世紀半ばから19世紀にかけての、ヨーロッパのとある国でのお話です(たぶん)。
とある学校の放課後、子供たちが元気に校庭で遊んでいる。その傍らでキラリキラリと光るものを拾っている先生がいた。それを見ていた学外の者が、あの先生は落ちている硬貨を拾って私しているのではないかと邪推します。
糺されたペスタロッチ先生のポケットは、たしかに何かでいっぱいになって膨らんでいました。
でもそれは、校庭に落ちていた石やガラスの欠片、折れ釘などでした。その学校は貧しい子供たちがたくさん通ってきます。みな靴を買うことができないので裸足なのです。子どもたちが怪我をしないように、ペスタロッチ先生は見守りながら、校庭の危険なものを取り除いていたのです。……
日本国内でも学校の校庭からいろいろなものが出てきて工事が遅れ、開校できなくなった…と、つい最近何かで耳にしたような気もするが、人間の歴史とは、ついこの間まで、そんなに豊かじゃなかったのです。選挙権だってつい70年前まで女性には認められてなかったのです。人間個々人がこんなに自分の権利を主張できる世の中になったのは、ほんのつい最近のことなのに、なぜみんな選挙に行かないの…(余談でした)
過去の物語の方向性をあげつらったり、校閲・考証をするわけではないので、さて今一読すると突っ込みどころ満載のお話ではあるが、たとえ話というのは、その現象から真理をつかみ出すことを目的としているので、漫才のネタにして笑いどころを探す必要はないのである。
医療機器や化学工業の先進技術の発達たるや、驚かんばかり。文明の利器によってますます快適な生活ができるようになったのに、先祖がえりどころか、人間の質が低下しているような気がしてならない。肝心の人間が啓かれなくては、進歩どころではないではないか。
人間が生きていくうえで大切な、思想、情操というものを養わなくては、社会はしあわせにはならない。無念のうちにこの世を後にした先人たちが、浮かばれないというものである。
夏山シーズンになると、新田次郎原作、森谷司郎監督の「聖職の碑(いしぶみ)」という映画を想い出す。
その映画のCMを録りたくて、テレビの前でテレコを用意して待っていた女子高生。そのCMのナレーションを日本アニメーション「母をたずねて三千里」のマルコのお兄さん役だった曽我部和行氏が担当していたのだった。
同番組の挿入歌♪母さんがいなくても陽気に育つ子があるものさ…の歌声がとても好きだった私は、例によってオタク魂を発揮して、贔屓の声優さんの声を蒐集していたのだ。思えば生涯声フェチなのかもしれない。能の御シテ方の先生も、まず、声が佳くなくては好きになれない。
そして、今でも昭和50年代に活躍していた声優さんの声は一聞にして、どれが誰だか識別できる(なんの自慢話でしょう………)。
いえいえ、このカンは現在の職業に役立っていると申せましょうか、知恵ではなく耳を働かせたお話ですね。
行楽の日々、皆さま、本当にご無事で……
弟子ほどかわいいものはない。師匠ほどありがたいものはない。
…というのが、修業道に身を置くものすべての、偽らざる心境でありましょう。