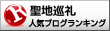これはいかん…
羽化二日目、お食事の支度もどうにか調って、気がつけば彼の者は、気ままに当家の居住空間を飛び廻り、什器のあちこちに安らい、すっかり居続けの態であった。
指をひょいと脚先に出すと、私の手に移ってくるほどに慣れてきたのだ。
これでは手乗り文鳥ならぬ手乗り鳳蝶ではなかろうか…
一昨年、国書刊行会の創業50周年フェアで『蝶を飼う男』という外国文学を入手した私は、しかし読む間がなく積読のまま放置していたが、もとより、蝶をペットにするつもりもなかった。
小学何年生だったか忘れた…ある時とても手乗り文鳥が欲しくなり…そのとき既に我が家には犬、猫、金魚、カエルなどが居たのだが、なんとか親を説得して、鳥を飼ってもよいという許可を得た。『ペットの飼い方』というハウツー本を読み込んでいたので、大概の動物の飼い方は心得たつもりになっていた。親鳥を飼い、生まれた雛を手懐ければ、私も夢の手乗り文鳥持ちになれるのだった。
…しかし、息せき切って小鳥屋さんへ駆けつけた私は、店頭に置かれていた、真っ白で嘴だけが紅いことりの番いに目と心を奪われ、文鳥ではなくその錦華鳥…キンカチョウという鳥を買ってしまった…お店の方がキンカチョウは托卵しない鳥だけど、いいですか?と親切に説明して下さり、母にも念を押されたが、私はどうしてもその白い鳥が欲しくなってしまったのだった。当初の目的の事はままよ、白くて嘴の紅い、あの美しい鳥が手に入るのだ…という悦びの前に手乗り文鳥計画は無力だった。
結局、自分の指先に小鳥をとまらせて愛玩するという夢は、もろくも崩れた。
…そんな目先の情動に惑わされがちな自分の性癖を分かっているものだから、生き物の生き死にに関わる立場には決してなるまい…と決めて、小学生以来、ペットを飼うことは無かった。第一、自分の世話さえまともに出来ない私である。

蝶や、蝶や、汝を如何にせん…
彼の身の振り方を二日目の晩に考えた。
ふと、ある夏の夕立の時間帯に羽化して、ベランダに居残っていた一頭がレモンの葉の上で風乗りサーフィンに興じていたことを想い出した。蝶は風に吹かれているのが好きなのである。
そこで、頂き物のチョコレートの白いリボンにとまったのを、ブランコのようにぶらぶら揺らしてみた。
どうやら彼もその遊びが気に入ったらしく、じっとしている。

このまま室内に居ることに慣れてしまっては、自然に帰れなくなる。しかし、外気温が10℃に満たないこの季節に、昆虫を外に出すのは死地に赴かせることに変わりない。
どこぞの温室で、早生まれのアゲハチョウを引き取ってもらえるところは無いものか知らん……
それにつけても、還暦過ぎて蝶一匹養う温室の一つも無いとは…甲斐性なしの自分ではある。
井の頭動物園にもかつては温室が在って、熱帯植物の生い茂る常夏の庭に蝶が飛び交う夢のような空間が存在していた。
昭和の終わりのバブルの頃、八景島パラダイスに蝶が棲む巨大な温室が出来たことがあった。私にはあこがれの世界で一度行きたいと、新聞記事を切り抜いて持っていたのだが、それも見果てぬ夢のまま、その施設もいつの間にか無くなってしまった。
……温室が無ければ、温暖な土地に連れて行ってあげればいいじゃない、と、異次元のマリー・アントワネットが囁く。
それだ。遠出は時間的に難しいが、関東近県で温暖な土地を探せばよいのだ。
幸い、当家のレモンアゲハは並揚羽という種族のアゲハチョウであるから、本州に於いて棲息地帯に縛りはないのである。
思いつく地名に"気温"という言葉を添えて、Google先生のワード検索にかける。
何という便利なインターネット社会になったものでしょう、今後一週間の天気と最高気温、最低気温の予報が我がたなごころの上に展開する。

三日目の昼近く、火災報知機のコードにとまっていた蝶を、彼の寝床である白いリボンで釣り上げて、そのまま、お弁当とともに引き出し式の小函に収めた。
何かしら感じるところがあるのか、ずいぶんと大人しい。
お引越し先は、伊豆半島の南端。黒潮の影響で一年を通して温暖で、何より最低気温が10℃前後。凍死の心配もない。
天城を超え、夕刻、下田についたが、曇り空からの雨が本降りになっていた。
その日の放蝶は断念して、街なかの花屋で若さまのお食事の手配を。

…出来ますものは、プリムラ、キンセンカの二種盛り、白菜の菜の花、家より持参のガーベラのようなもの、でございます。
四日目の朝も雨模様だったが、天気を待って旅程を延ばすことも出来ず、小止みの間に宿を出立した。

思いがけず菜の花が気に入った様子で、リボンと共にふたたび移動用の箱男となる。
花壇のような平坦地では雨を凌ぐのも難しいだろうから、丈のある菜の花畑はどうだろうかと、候補地をあれこれ思いめぐらす。
南伊豆町の里山は、河津桜か桃かアンズか、眼にも心にも優しい景色が広がる。


モンシロチョウほどには歓んでもらえないかも知れないけれど…嗜好に合うか気懸りながら、昨晩スーパーの野菜売り場で見つけた白菜の菜の花にとまっている彼を箱からそっと取り出し、本物の菜の花に移ってもらった。



ここなら草間の蔭で雨宿りもでき、激しい海風に遭うこともなく、明日晴れたら、気ままに飛び立つこともできるだろう、と…
自宅に戻って翌朝は夜明け前に目が覚めてしまった。
蝶々は無事に過ごしているだろうか…
西の地平に沈む間際の十三夜の月を見送る。