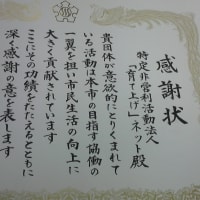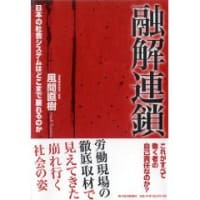| キャラクター精神分析 マンガ・文学・日本人(双書Zero) |
| クリエーター情報なし | |
| 筑摩書房 |
2011年5月14日に開催した、シリーズ若者vol.3 「若者とアイデンティティ」において
講師斎藤環先生(精神科医)の講義内容を許可いただきましたので、この場で
共有致します。
なかなか普段は「アイデンティティ」について考えることはありませんが
当日は多くの方にご参加いただき、皆でそれについて考えました。
下記、講義内容は、私が聞きながらタイプしたものですので若干の
間違いがあるかもしれません。もししっかりと、詳細までお知りになりたい
ということでありましたら、斎藤先生のご著書にもっと詳しく
書いております。
-----------------------------------------------------------------------------
今年二冊書籍を出しています。一冊は「社会的うつ病の治し方」
もうひとつは、「キャラクター分析」
臨床家として経験するのは、社会的うつの回復の過程のなかで、
人間関係が治療的に意味をもつ。それを「ひと薬」と表現しています。
そこらへんも本日は出ています。
キャラクターについてですが、漫画や映画でのキャラクターとは何かを考えたもの。
「キャラ」を日常的に使うが、そういった使い方とフィクションとしての
「キャラ」の使い方はつきつめていくと同じ。
今日の話は両方に関係がある。アイデンティティを考えるとき、キャラクター
というものは無視できない。
空間的アイデンティティとは、社会の中のポジショニングです。通常はこちら。
大切なのは時間的アイデンティティ。自分という存在の時間的アイデンティティ。
昨日の自分は、今日の自分。若者のなかには、昨日と今日が異なるひとが出てきている。
同一性。連続性は無視できない。同じということがいかに不思議かというのは哲学的問題。
科学的には解明できていない。高い精度でそのひとはそのひとであることを勘であてている。
アイデンティティの確立とは青年期の発達過程。(エリク・エリクソン)。アイデンティティとは
成熟の同義語である。現代においては。我々はそういう社会に生きている。もちろん、
それだけではないが。臨床家の間では一般化されている。
概念が生まれるときは、概念のありようが危機にさらされた時期。50年代アメリカ。
エリク・エリクソンもそこ。モラトリアムが重要。自己決定を猶予される期間。
ざっくりいえば、日本においては学生期間をさします。事実上。本当はいけないのですが。
いま、成熟年齢は若く見積もっても30歳。私は、35歳、40歳でいいと思っている。実際には
30歳を超えた学生はいっぱいいるわけですし、そういう意味ではモラトリアム期間は伸びている。
こういう流れは近代化の宿命。
近代化とは、文明が発達してインフラが整備されること。ハンデがあっても生きていける社会。
豊かになることは、教育期間を延ばす。社会の成熟化は個人の未成熟化。
成熟とは本当に価値があるのか? 成熟化にはふたつある。ひとつはほしいものを「待てる」
欲求不満耐性。もうひとつはコミュニケーション。大切なのは情緒的な文脈を相手から受けられるか。
受け取られるか。情報ではなく、情緒です。それができていると成熟化したといえる。
アイデンティティを語るのは、成熟を語るに等しい。日本には成熟を遅らせる要因がたくさんある。
少年殺人の犯罪は減っている。いまの全共闘世代の方々が思春期であったときがピーク。
その後減少。要するに犯罪者は減っている。
フリーター・ニートは増えている。これは非社会的な問題。社会とのコミットメントがない若者が
増えてきている。ニートはご存じかと思います。犯罪が減り、ニートが増えるのは、
若者の非社会化が進行している統計的事実。
非婚、未婚の問題。特に日本社会においてはシングルマザーなどへの偏見が強い。結婚とは
社会化の大前提、という考えを捨てられてない。早くとっぱらってほしい。結婚=社会化、は残念な状況。
非社会化=未成熟か。つまり、社会に対して情緒的なコミュニケーションを回避している傾向といえる。
モラトリアム期間が延びることは、アイデンティティの拡散。社会の成熟化は個人の未成熟化。
いま通過儀礼がなくなっている。強いて言えば、就職と結婚。ただし、就職は成熟の儀式として
機能しているかは定かではない。結婚、出産、家庭を持つことも通過儀礼。ただ、機能としてはもう弱い
自立のイメージも混乱している。ほかにも要因がある。地域共同体の衰退。家庭の密室化。
このような災害では一時的に共同体意識が高まるが、インフラが整備されると衰退するだろう。
インフラとは共同体ネットワークの代替物である。
いまは独身者向けのインフラが整備されてきている。ひととかかわる/助け合う必要性が少なくなっている。
共同体とはうざいもの、わずらわしいもの、おせっかいなもの。できればかかわりたくないもの。
でなければ、こんなに簡単に衰退するはずがない。
共同体そのものが若者の成熟を促すきっかけだったが、共同体が衰退すれば成熟は遅くなる。
家庭の密室化は他人があがらない。困ったことがおきても誰にも相談しない。これも密室化の傾向。
核家族化・母子密着・父親疎外が同時進行。
日本においては、家庭の軸は母子関係にある。通常は夫婦関係にある。
日本と韓国を除いて。家父長制の現代の意味は、父親が家族から疎外されていることをさす(私の定義です)。
父親は神棚に祭りあげる日本と韓国では父親疎外が進んでいる。単身赴任が一例。韓国では母子留学で
父親がお金を送金する。どうも父親の自殺が増えているらしい。
悪い意味での母子密着は、母親が子供をアイデンティファイする。自分の生きなおしを子供に求める。
母子密着がよくないということではない。父親が母親のメンテナンスをすれば母子密着はしづらい。
夫婦が仲良くすることが大事。
母子密着の回復は、ひいては若者の成熟につながる。近代的なインフラと前近代的な価値規範との葛藤もある。
インフラは世界水準。しかし、価値規範は残る。そういうギャップにより、少し変わった状況が生まれる。
自明な価値観。「就労」と「結婚」への懐疑。昔は就職するものだということが自明だった時代から、
自明性が失われました。結婚もそうです。時代の流れです。自明が選択肢になったわけです。
これから増えるのは生涯非婚率が増える。いま15%くらい。なかにはひきこもりも含まれるだろうが、
非婚率が高まる。やはり人間は社会性、関係性の生き物、というのは有効。まったくの
孤立状況に耐えられない。ここまでは先進国に比較的共通。
非社会化。社会にコミットしてもろくなことがない。ネットだけのコミュニケーションのほうが
マシかもしれない”イメージ”を持っている。実際に”いい”という話は別。
若者の非社会的傾向。若者へのレッテル・ラベリング。不登校、おたく、フリーター、
パラサイトシングル、ニート、ひきこもり。いい悪いではなく現実。たたいても意味がない。
まずは状況を理解すること。
たたくのは意味がない。たたくというのは問題を政治化すること。政治化するというのは、
問題の解決スキルを放棄してしまうこと。原発問題もあまり急いで政治化すると、
解決スキルが衰退する可能性がある。非社会性も同じ。いい悪いはおいておき、
そういう問題をどうしたらいいか考える
もともと若者政策はラストだったものが、震災もありもっと後ろになってしまう。
私は若者の問題に取り組むよう主張している。20年後には、一度も働いたことがない若者が
65歳になってしまい。何の手だても打たれていない。恐ろしいこと。
自立のイメージを語るときに、おおざっぱに言えば、欧米型は自宅から出て、アイデンティティを
確立する。日本の場合は「親孝行」。漠然とした親の期待も含まれる。それがタイムリミットを
疎外してしまっている。
日本における母子密着の最大の原因は、タイムリミットが設定されないこと。リミットの設定は、
自立・アイデンティティ形成への第一歩。アイデンティティ形成要件は自立です。
自立してなければアイデンティティはいらない。誰かにアイデンティファイされていればいい。
ヨーロッパの同居事情。イタリア70% スペイン72%。イギリス28%。スイス18%。
カソリックは儒教主義と同じで家族主義。こういう家族は同居していて当たり前。
なぜ、同居が世界でも高まっているか。経済的悪化。教育の長期化。福祉は同居のほうが手当てが
多くもらえる。そして、先ほどの宗教/家族主義の問題。私はこれを日本化にしている。
必然的にアイデンティティの拡散が起こる。もうアイデンティティは”仕方なく”起こる状況。
逆に言うと、自分をサポートしてくれる存在がいればアイデンティティは重要ではない。
そこに依存をしていけばいいからです。アイデンティティの価値は高くない。
湯浅さんは「溜め」の問題としている。溜めがなければ排除が起こる。五重の排除とおっしゃっている。
教育、企業福祉、家族福祉、公的福祉、自分自身からの排除
自己否定的な意識のこと。自分はとるにたらない、価値のない、生きるに値しない。自分からの排除。
ひきこもりもエリートサラリーマンも持ってしまう考え。そういう状況に社会がなりつつある。
ひとつの理由は社会の余裕がなくなってしまうこと。排除、疎外状況が起こっている。
いま、コミ力が高いか低いか、ということが言われている。非社会性をもたらすコミュニケーション格差。
人評価=コミ力というものが高まっている。コミュニケーション格差。学力やスポーツなどの才能には
みられない。貧しい対人評価軸になってきている。ある種の子供にとってはとてもきつい状況
コミュニケーション格差。ひきこもり系と自分探し系。おおまかにいって二つにわかれることが
自分の調査でわかった。
ひきこもり系。あまり友達が多くない。コミュニケーションが苦手。ただ、自己イメージは
しっかりしている傾向がある。
自分探し系。いわゆるリア充。友達もいる、彼女/彼氏もいる。このひとたちは自己イメージが意外と稀薄。
アイデンティティといってもいい。仲間関係に支えられていないといけない。支えられていないといけない。
このタイプはカルトにはまる傾向がある。コミ力が高いがゆえに、だまされやすい。
他のコミュニティーに弱い。自分探し系は欲求不満耐性が弱い。ひきこもり系はコミュニケーションが弱い。
結果として起こっているのは「キャラクター化」が起こってきた。詳しいのは書籍で。
キャラ=人格のサブカテゴリー。
スクールカースト。コミュニケーション格差。自生的秩序=キャラのすみわけ。携帯による媒介・助長。
コミュニケーションの円滑化。再帰的コミュニケーション
スクールカーストとは教室内身分制です。女性には覚えがあると思います。同年齢で集団をつくると、
同質集団のグルーピングが起こる。女性に多い。入れるかどうかは死活問題。
グループ間の関係がスクールカースト。
キャラクター化はグループ内で起こる。階層化があり、グループ化があり、キャラクター化が起こる。
これを応用したものはAKB48の選挙。階層をひっかきまわす。余談ですが。
カーストを決定づけるものがコミュニケーション格差。力が強いのではなく、コミ力が強い人が勝ち組。
空気をつくり、ひとをいじれる。こういうひとがエリート階層。最上位クラス
それが苦手、嫌いなひとは最下層グループ。もちろん、誇張していってますが、一致した見解。
いま、思春期以降の若者のアイデンティティの代替えになっているのがキャラです。ただし毎年変わる、
キャラ替えしなければならないので結構大変。キャラの発生とは自生的秩序。何となく割り振られるもの。
ズレることもある。
自分と異なるキャラが割り振られると、演技に疲れてしまう。そういう相談もある。キャラ疲れ。
まさにコミュニケーションが活発化する方向、ケータイ媒介によってキャラ化が助長。
キャラのいいところは、コミュニケーションが円滑化する。もう役割が決まっているから。
ただ、それ自体はキャラの確認、再帰的コミュニケーション。同じ情報の確認。つまり情報量ゼロ。
ただ批判ではない。
かなり高度なコミュニケーション。毛づくろい的コミュニケーション。挨拶も毛づくろい。
意味はない。親密さの確認。親密さの再確認。家庭内などを含め、とても大切。
キャラ化の問題。いじめの温床になりやすい。いじられキャラになると大変。キャラ替えは大変。
熾烈なバトル。いじられキャラでないPR。どうしたらいじめられないか?いじめる側に立つ。
だから終わらない。いじめは連鎖しやすい。
キャラ≒同一性の記号。すべてのキャラに共通する。問題はアイデンティティ=キャラでない。
アイデンティティはキャラの集合体。キャラはシーンごとにある。複数のキャラがあって当たり前。
キャラが多ければ、アイデンティティは獲得しづらい。古き良き同一性がそれ。
いまはコミュニケーションによってキャラを変えられないとやりにくい時代。私ですら、
ネット上、ツイッター上、などではキャラは違い。アイデンティティの稀薄化。私も拡散している
コミュニケーションが活発化した結果として、人間関係が希薄化している。コミュニケーションと
関係性は反比例する。匿名的かつ確率にさらされた存在という自意識。
自分の一番革新的なことは、一番遠いひとにしか話せない状況。かつては人間関係は同心円状であった。
いまは複数の円がランダムに交わっているイメージ。
関係性はアイデンティティーにとって重要。コミュニケーションの活発化は関係性を希薄化させ、
アイデンティティを拡散することを知ってほしい。
キャラとは取り替え可能な存在に甘んずることを意味している。アイデンティティの別軸は、
同一性と単一性(かけがいのないこと・互換性がないこと)。キャラには同一性はあるが、
単一性がない。匿名性が高まる→確率となる。
キャラとは再帰的に強化される。結果として、これが成長・成熟を疎外する。
思春期段階で成立したキャラを維持しなければならないと、成熟できない。キャラを変えると、
キャラ替えしたの?となってしまう。
ひとつの発明ではあるが、問題でもある。もうひとつ。自己同一性を維持するものは何か。
大切なのは自己愛だといわれている。維持する気力は自己愛からくる。
「社会的うつ病」の本に書いてあることだが、自己愛とはいますぐ死にたくはない。
他人を愛するときの基本にある自己愛。など人間が生きていくうえで不可欠なエネルギーが自己愛。
みんな持っている。
自己愛を破壊されてしまった人間は自殺してしまう。なぜそうならないかは自己愛があるから。
どうしたら?野心と理想。自信とプライドと言い換えてもいい。このバランスが大切。
ひきこもりが典型。プライドは高いが、自信がない。他人に頼れない。受け入れられない。
一歩踏み出せない。つまり、身動きがとれなくなる。いかに自信とプライドを
カップリングをさせられるか。その技術とはおもに他者とかかわること。
そのスキルは他者が形成する。他者の介在がないと自己愛が健全に持てない。他者の介在がないと
自己愛が分離してしまう。まれに特殊な才能のひとがいる。自信とプライドが高度にバランスをとる。
これは天才といいます。
孤独感というストレス。非常に簡単に言うと、孤独感は生活習慣病になりやすい。なぜなら
生活がだらしなくなるから。自虐的・自滅的な志向や行動に陥らせる。孤立は自己愛を崩壊させる。
医学的に考えていただいてもOK
玄田先生からのバトンとして、地域におけるアイデンティティですが、大事になるのは
「社会関係資本」ソーシャルキャピタルです。
人々の持つ信頼関係や人間関係、上下関係や利害関係から離れた横のつながりをさす。
玄田先生のいうウィークタイズですね。
資本という言葉の意味は、ひとつには経済力とは直接的な関係がないことと、人々の協調活動が
活性化されれば社会の効率が高まる、という発想が基本にある。生身性が大事。仕事以外の関係。
ネットの人間関係は希少性が少ない。たまたま出会えたということがない。ありがたみが少ないのがネット。
会いたい人に会えるから。すぐ会えるけど、すぐ終わっちゃう。これからは生身性が大事になってくる。
生身性を担保にした出会い、コミュニケーションの場が、これからのアイデンティティを考えるうえで
非常に大切。人持ち(上の千鶴子氏)、人薬が大事。女性は鬱になる割合が高いのに、男性のほうが
自殺する。女性は人薬を持っている可能性
むしろ被災地のほうが社会関係資本を構築する可能性があると、私は考えています。
-------------------------------------------------------------------------------------------
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
コーディネーターも務めていたもので、会場との1時間を超える
ディスカッションは文字化できていませんでした。
多少読みづらいのは、twitterで連続投稿していたからです。
そちらで読みたい、という方はこちらからどうぞ!
http://togetter.com/li/135351
次回のシリーズ若者vol.3 は
いま、社会的に大きな課題となっている中退問題に迫ります。
「若者と中退」中退予防戦略-学生はなぜ辞めるのか?-
お時間ございましたらぜひ、ご参加ください。
詳細は下記になります。
http://kokucheese.com/event/index/11092/











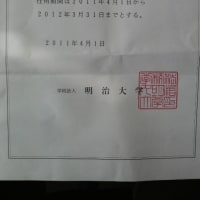
![[若者UP運営管理者研修]地域若者サポートステーション×日本マイクロソフト社](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0b/8c/5f7f0e3d3cecae6382b6648aa0055ee9.jpg)
![[SBC信越放送] 346Barの収録へ伺いました。](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/64/d5/a4dd94d9d9df04b464d8186facb86a2b.jpg)