いよいよ!
明日は壬生の花田植です。
遠くに住む親族がやってきたり、
たくさんの人達が設営作業に専念していたり、
町中がそわそわワクワクしていて、それだけで楽しいです。
ところで、今年始めてのことなのですが
明日は“見習いの飾り牛”が三田風月堂前、
教得寺の駐車場で研修?の予定。
この見習い牛は来年“道ゆきデビュー”とのことです。
神社に行かなくても牛と戯れることができるかも?!
ちなみにその見習い牛、よく鳴く子ということです。
やんちゃな子なのかしら?と、想像を膨らませるのも嗚吁愉快。
教得寺駐車場では、もはやいつでも牛をウェルカムできるよう
ほし草とレッドカーペットでお待ちしてます。

明日が今日くらい晴れますように~!
明日は壬生の花田植です。
遠くに住む親族がやってきたり、
たくさんの人達が設営作業に専念していたり、
町中がそわそわワクワクしていて、それだけで楽しいです。
ところで、今年始めてのことなのですが
明日は“見習いの飾り牛”が三田風月堂前、
教得寺の駐車場で研修?の予定。
この見習い牛は来年“道ゆきデビュー”とのことです。
神社に行かなくても牛と戯れることができるかも?!
ちなみにその見習い牛、よく鳴く子ということです。
やんちゃな子なのかしら?と、想像を膨らませるのも嗚吁愉快。
教得寺駐車場では、もはやいつでも牛をウェルカムできるよう
ほし草とレッドカーペットでお待ちしてます。

明日が今日くらい晴れますように~!










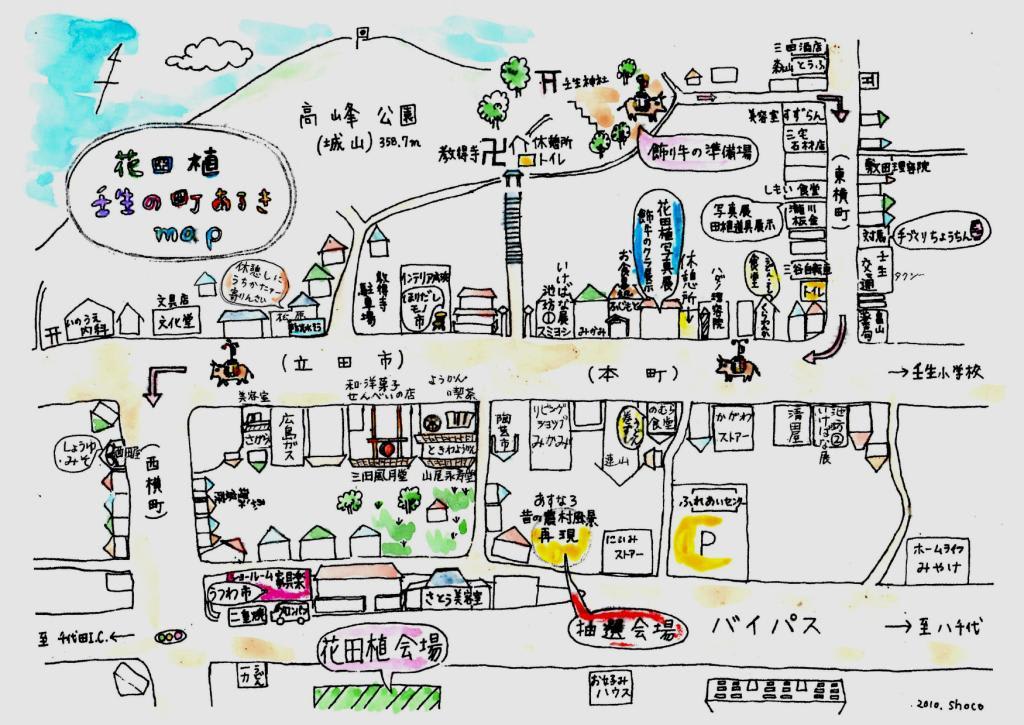

 花田植大公開
花田植大公開




 )
)

 近年少しずつ規模が縮小傾向にある壬生の花田植ですが、
近年少しずつ規模が縮小傾向にある壬生の花田植ですが、



