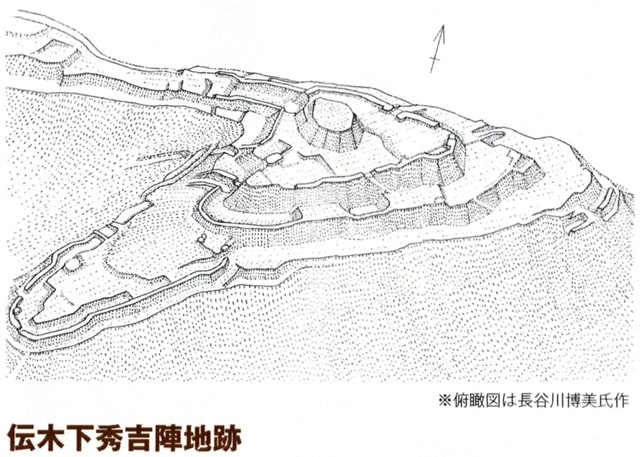お久しぶりです。コロナ禍の中、ついつい出かけることがおっくうになっていました。しかし、知人がいろいろと山城の散策を行っていることで、何かせかされているような気がして、とりあえず、滋賀県の横山城を訪ねました。
ということで、あまり下調べをせずに行ったので、いくつか失敗をしてしまいました。
出発は横山城のふもとのお寺大原観音寺です。

大原観音寺山門
山門前の池の横を通り、山に入りました。すると、すぐに道が三つに分かれていましたので、真ん中の道を行きました。

横山城の登城路(滋賀県教育委員会「近江城郭探訪」2006より)
かなり急な(私にとって)登り坂の山道でした。しかし、なかなか着きません。感覚としては、上の図の大原観音寺の北を登るコースを選んだつもりでしたが、途中で石田町からのコースとぶつかってしまいました。

峠の道
この峠の道から頑張って歩いてようやく横山城の南城が見えました。横山城は、南城と北城があり、北城から南西に曲輪が延び、Yのような形になっています。

横山城概要図(現地案内板)
曲輪の中に大きな梵鐘がありました。

南城の梵鐘
この梵鐘は、下の大原観音寺の案内板によると、以下のようです。
「昭和初期に昭道が玉泉院で僧となり、修行托鉢に毎日出かけ信者の方に懇願し、荒れた城跡の整備に力を入れ、昔を偲んで梵鐘を寄進し、三尊佛及び登山道~城跡~下山道に33体の観音様を祭られました。
この梵鐘は、昭和12年に朝日区民の大人から子供までが総出でソリに乗せ城跡まで運んだそうです。
戦時中に寺の鐘は全て軍の命令により国家に強制的に供出させられ、色々な兵器に使用されましたが、歴史ある古い観音寺の梵鐘は供出からまぬかれました。心配された城跡の梵鐘は、昭道和尚が「戦没した武士の霊と他国との戦争で戦死した軍人の霊を誰もが鐘をついて冥福を祈り追弔するための梵鐘」と強く主張され同じく供出から免れ今日に至っています。
梵鐘堂は、三十数年前に朝日区民により一度修復されたそうですが、倒壊寸前と傷みが激しくなったため改修(建替え)工事を行いました。 平成26年10月吉日」
「観音寺山を愛する会」による説明です。
この梵鐘が戦争の兵器にならずに済んでよかったと思います。人々の安全や平和を祈るための梵鐘が、真反対の人を殺傷する武器になるという、戦争の狂気を改めて見た思いでした。
ということで、あまり下調べをせずに行ったので、いくつか失敗をしてしまいました。
出発は横山城のふもとのお寺大原観音寺です。

大原観音寺山門
山門前の池の横を通り、山に入りました。すると、すぐに道が三つに分かれていましたので、真ん中の道を行きました。

横山城の登城路(滋賀県教育委員会「近江城郭探訪」2006より)
かなり急な(私にとって)登り坂の山道でした。しかし、なかなか着きません。感覚としては、上の図の大原観音寺の北を登るコースを選んだつもりでしたが、途中で石田町からのコースとぶつかってしまいました。

峠の道
この峠の道から頑張って歩いてようやく横山城の南城が見えました。横山城は、南城と北城があり、北城から南西に曲輪が延び、Yのような形になっています。

横山城概要図(現地案内板)
曲輪の中に大きな梵鐘がありました。

南城の梵鐘
この梵鐘は、下の大原観音寺の案内板によると、以下のようです。
「昭和初期に昭道が玉泉院で僧となり、修行托鉢に毎日出かけ信者の方に懇願し、荒れた城跡の整備に力を入れ、昔を偲んで梵鐘を寄進し、三尊佛及び登山道~城跡~下山道に33体の観音様を祭られました。
この梵鐘は、昭和12年に朝日区民の大人から子供までが総出でソリに乗せ城跡まで運んだそうです。
戦時中に寺の鐘は全て軍の命令により国家に強制的に供出させられ、色々な兵器に使用されましたが、歴史ある古い観音寺の梵鐘は供出からまぬかれました。心配された城跡の梵鐘は、昭道和尚が「戦没した武士の霊と他国との戦争で戦死した軍人の霊を誰もが鐘をついて冥福を祈り追弔するための梵鐘」と強く主張され同じく供出から免れ今日に至っています。
梵鐘堂は、三十数年前に朝日区民により一度修復されたそうですが、倒壊寸前と傷みが激しくなったため改修(建替え)工事を行いました。 平成26年10月吉日」
「観音寺山を愛する会」による説明です。
この梵鐘が戦争の兵器にならずに済んでよかったと思います。人々の安全や平和を祈るための梵鐘が、真反対の人を殺傷する武器になるという、戦争の狂気を改めて見た思いでした。