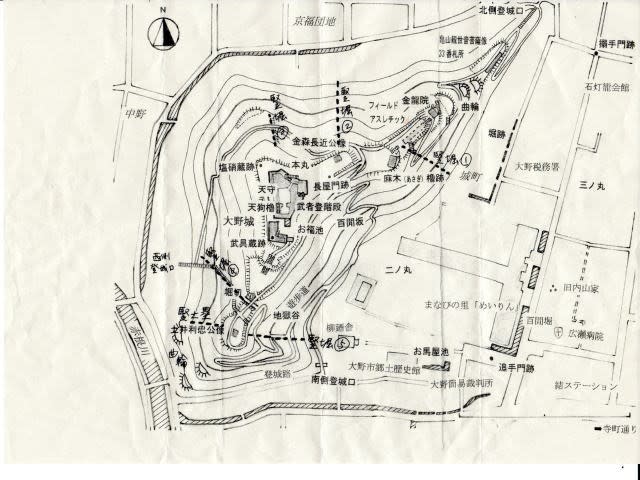さて、今回は第1回ということでしたが、テレビなどでおなじみの萩原さちこさんという方がわざわざ国吉城まで来て、案内をしてくれるというので、楽しみでした。

萩原さちこさん(ブログ「城メグリスト」より)
萩原さちこさんのブログを見つけました。 「城メグリスト」 https://46meg.com/
メグリストというのは巡る人というのをしゃれていっているのかなと思います。
そのブログで、自身のプロフィールを以下のように紹介しています。
城郭ライター、編集者。
小学2年生で城に魅せられる。日本人の知恵、文化、伝統、美意識、歴史のすべてが詰まった日本の宝に虜になり、城めぐりがライフワークに。
印刷会社、出版社、制作会社、広告代理店等の勤務を経て独立。
現在はフリーライターとして執筆業を中心に、テレビ・ラジオなどのメディア出演、イベント出演、講演、講座など行う。
(著書省略)
東京都足立区生まれ。青山学院大学卒。
公益財団法人日本城郭協会理事・学術委員会学術委員。
お城の魅力をわかりやすく楽しく伝える、がモットー。
【あいさつ文】
お城をめぐるたび、その奥深さに驚きます。
それだけ魅力たっぷりのものなのだから、 いろんな見方があって、その人なりの楽しみ方があっていいと思うのです。
「難しい」「マニアック」という先入観の壁をなくして、もっとお城を身近な存在にしたい。
今お城に興味がない方も、楽しみ方がわからない方も、気軽に、自由に、お城歩きをして欲しい。
そして、日本の宝である城を後世に残し、地域活性化につなげるお手伝いがしたい。
そんな思いでお仕事をしています。

萩原さちこさん(ブログ「城メグリスト」より)
萩原さちこさんのブログを見つけました。 「城メグリスト」 https://46meg.com/
メグリストというのは巡る人というのをしゃれていっているのかなと思います。
そのブログで、自身のプロフィールを以下のように紹介しています。
城郭ライター、編集者。
小学2年生で城に魅せられる。日本人の知恵、文化、伝統、美意識、歴史のすべてが詰まった日本の宝に虜になり、城めぐりがライフワークに。
印刷会社、出版社、制作会社、広告代理店等の勤務を経て独立。
現在はフリーライターとして執筆業を中心に、テレビ・ラジオなどのメディア出演、イベント出演、講演、講座など行う。
(著書省略)
東京都足立区生まれ。青山学院大学卒。
公益財団法人日本城郭協会理事・学術委員会学術委員。
お城の魅力をわかりやすく楽しく伝える、がモットー。
【あいさつ文】
お城をめぐるたび、その奥深さに驚きます。
それだけ魅力たっぷりのものなのだから、 いろんな見方があって、その人なりの楽しみ方があっていいと思うのです。
「難しい」「マニアック」という先入観の壁をなくして、もっとお城を身近な存在にしたい。
今お城に興味がない方も、楽しみ方がわからない方も、気軽に、自由に、お城歩きをして欲しい。
そして、日本の宝である城を後世に残し、地域活性化につなげるお手伝いがしたい。
そんな思いでお仕事をしています。