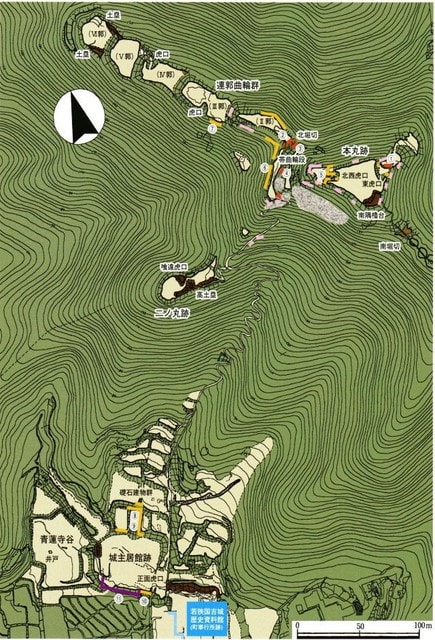国吉城歴史資料館10周年イベントの一環として、国吉城に関連するテーマでの学習会が行われました。講演内容は、武田氏に関するものでした。武田氏といっても甲斐の武田信玄の武田氏ではありません。戦国時代、同時期に若狭の守護であった武田氏のお話です。この武田氏は、国吉城の城主である粟屋氏の主君に当たります。そこで、この武田氏についても学習して、国吉城を多面的に考えようということです。

学習会の講師 有馬香織さん(右)パソコンをいじっている方は、館長の大野さん
有馬さんは、現在一乗谷朝倉遺跡資料館に務めていらっしゃいますが、もともとは、若狭歴史資料館の学芸員でした。このたび一乗谷朝倉遺跡資料館の拡張に伴い、そちらに務めることになったとのことです。
「粟屋勝久の主君・若狭武田氏の文化と力~本家の正当性~」というタイトルで、いろいろとお話をしていただきましたが、一番印象的だったのは、「若狭の武田氏こそが本家である」ということでした。
戦国時代の武田氏といえば、甲斐の武田信玄を思い浮かべ、他に武田氏という武将がいたとしても、それは傍流で、甲斐武田氏こそ本家と思ってはいないでしょうか。私もそう思っていました。しかし、今回の講演で武田氏の本流は、若狭の武田氏だということが分かりました。
武田氏は、もとは清和源氏で、新羅三郎義光(1083~1087年の後三年の役で活躍)の三男の子孫だそうです。常陸国那珂郡「武田郷」から、甲斐国、安芸国(今の広島県の一部)、そして若狭国へと「総領家」移動したそうです。
若狭武田家が本家であることの証拠は、以下のようです。
①弓箭口伝(きゅうせんくでん)
流鏑馬(やぶさめ)などの技術を武田家においては、宗家にしか伝来していない。ウィキペディアによれば、以下のように伝来されたそうです。(下の系図は講師の方の説明ではありません。)
清和天皇‐貞純親王‐源経基‐満仲‐頼信‐頼義‐義光‐義清‐清光‐武田信義‐信光‐信政‐信時‐信綱‐信宗‐信武‐氏信(安芸武田氏)‐満信‐信繁‐信栄(若狭武田氏)‐信賢‐国信‐信親‐元信‐元光‐信豊‐信時‐義統‐義親‐信恭‐信重‐信直‐細川藤孝
※青色は若狭武田家
②「大善太夫」「伊豆守」の名乗り
この名乗りも武田家宗家に伝わる名乗りだそうで、若狭武田氏は、2代信賢(大善太夫)3代国信(大善太夫)4代信親(大善太夫)5代元信(大善太夫・伊豆守)6代元光(大善太夫・伊豆守)7代信豊(大善太夫・伊豆守)8代義統(大善太夫・伊豆守)というふうに歴代受け継がれていること
以上のことから、若狭武田氏こそ甲斐武田氏、安芸武田氏の総領家ではないかと強調しておられました。
そして、若狭という地域にもっと誇りを持っていいと言っていました。
現在は、原発銀座ということで、産業がない、漁村の地域というイメージがありますが、戦国時代は、京都に近いこともあり、日本の政治文化の中心地のひとつであったようです。

学習会の講師 有馬香織さん(右)パソコンをいじっている方は、館長の大野さん
有馬さんは、現在一乗谷朝倉遺跡資料館に務めていらっしゃいますが、もともとは、若狭歴史資料館の学芸員でした。このたび一乗谷朝倉遺跡資料館の拡張に伴い、そちらに務めることになったとのことです。
「粟屋勝久の主君・若狭武田氏の文化と力~本家の正当性~」というタイトルで、いろいろとお話をしていただきましたが、一番印象的だったのは、「若狭の武田氏こそが本家である」ということでした。
戦国時代の武田氏といえば、甲斐の武田信玄を思い浮かべ、他に武田氏という武将がいたとしても、それは傍流で、甲斐武田氏こそ本家と思ってはいないでしょうか。私もそう思っていました。しかし、今回の講演で武田氏の本流は、若狭の武田氏だということが分かりました。
武田氏は、もとは清和源氏で、新羅三郎義光(1083~1087年の後三年の役で活躍)の三男の子孫だそうです。常陸国那珂郡「武田郷」から、甲斐国、安芸国(今の広島県の一部)、そして若狭国へと「総領家」移動したそうです。
若狭武田家が本家であることの証拠は、以下のようです。
①弓箭口伝(きゅうせんくでん)
流鏑馬(やぶさめ)などの技術を武田家においては、宗家にしか伝来していない。ウィキペディアによれば、以下のように伝来されたそうです。(下の系図は講師の方の説明ではありません。)
清和天皇‐貞純親王‐源経基‐満仲‐頼信‐頼義‐義光‐義清‐清光‐武田信義‐信光‐信政‐信時‐信綱‐信宗‐信武‐氏信(安芸武田氏)‐満信‐信繁‐信栄(若狭武田氏)‐信賢‐国信‐信親‐元信‐元光‐信豊‐信時‐義統‐義親‐信恭‐信重‐信直‐細川藤孝
※青色は若狭武田家
②「大善太夫」「伊豆守」の名乗り
この名乗りも武田家宗家に伝わる名乗りだそうで、若狭武田氏は、2代信賢(大善太夫)3代国信(大善太夫)4代信親(大善太夫)5代元信(大善太夫・伊豆守)6代元光(大善太夫・伊豆守)7代信豊(大善太夫・伊豆守)8代義統(大善太夫・伊豆守)というふうに歴代受け継がれていること
以上のことから、若狭武田氏こそ甲斐武田氏、安芸武田氏の総領家ではないかと強調しておられました。
そして、若狭という地域にもっと誇りを持っていいと言っていました。
現在は、原発銀座ということで、産業がない、漁村の地域というイメージがありますが、戦国時代は、京都に近いこともあり、日本の政治文化の中心地のひとつであったようです。