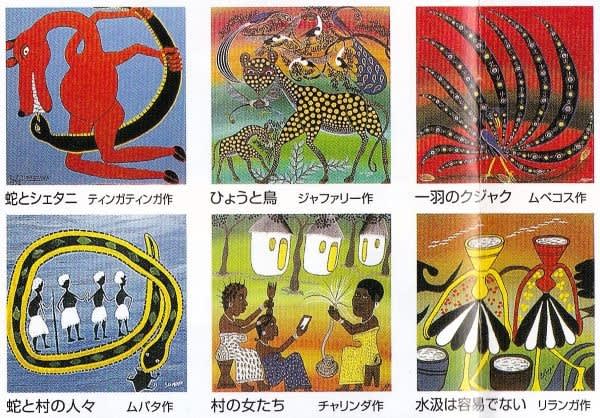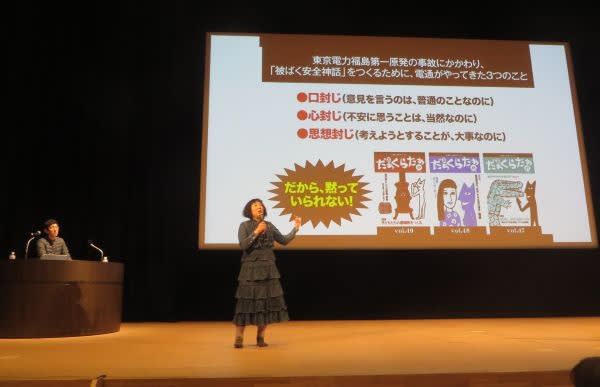道路沿いにこんもりした森、墓地かな、それとも氏神様が祀ってあるのかなと思っていました。
先日また通りかかった時に、ふと車を止めて寄ってみたところ、
「織殿神社」という由緒ある神社でした。



狭い敷地ですが巨木が何本もあって圧倒されます。
凄い瘤のある木がありました。


かつてこのあたりは麻續郷(おうみごう)と呼ばれていたそうです。
現在も、少し離れたところにある神服織機殿(かんはとりはたどの)神社では絹を織り、
神麻続機殿(かんおみはたおりどの)神社では麻を織り、神宮(伊勢神宮)に供えているそうです。
麻の栽培も細々と続けられているようです。
新たに麻畑を作る計画もあるようです。
そしてまた、かつて庶民の衣類だった藍染めの縞模様の木綿の織物の製造が
この近く(御糸)で、今も続けられているということに、ちょっと感動します。
町の物産館のような所に行くと、御糸織(みいとおり)のブックカバーや袋などの小物類が置いてあります。
松阪の手織りセンターまで行くと、御糸織の着物や帯が並び、手織り教室などもあるようです。

↑ 御糸(みいと)地区にある御糸織の工場(株・御絲織物)です。
(写真は4年前に撮ったもの)
中を覗くと、織機と藍の甕が並んでいました。
染め上がった布は、この写真の前の広い所に干すそうです。
タイミングが難しそうだけど見てみたい。