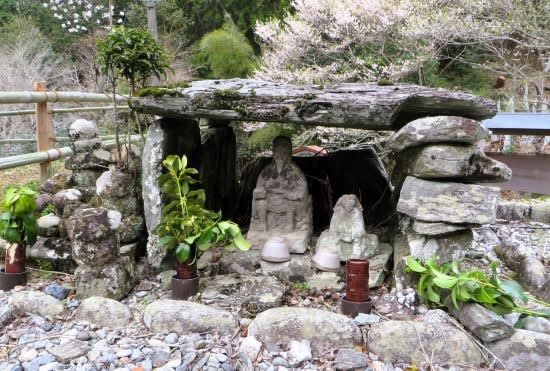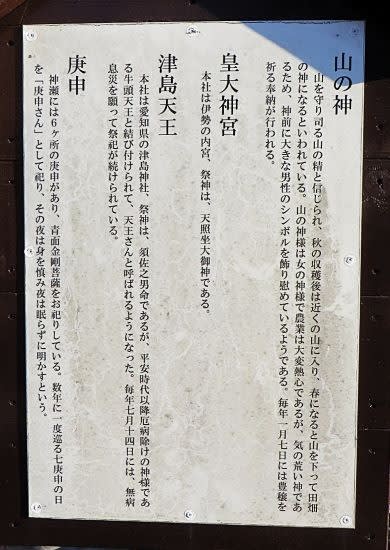京都のお寺などの観光地はサクラやモミジのシーズンは押すな押すなの人混みになります。
けれど、三重の田舎の山あいの、このあたりを訪れる人はほとんどありません。
コンビニもない、ガソリンスタンドもない、ダイソーもない、レストランもカフェもない、
公園も、自動販売機も、ドッグランもキャンプ場もない・・・
聞こえるのは鳥の声と、水の流れる音
こんなに美しい所を誰も知らない、
日本中にそんなところがどんなに沢山あることでしょう!
地元の人たちだけが、季節ごとに、身の周りの自然を愛でて楽しんでいる、
そして、草を刈り山の木の世話をして、石垣を修理し、
イノシシやシカと闘いながら、田や畑を耕し、
家の周りに花を植えている。
どうかいつまでも!と願わずにいられません。

↑ 丘の上は桜の林
Googleマップの案内で、医王寺(黄檗宗)へも寄ってみました。
↓ 医王寺には、珍しい鉄製の宝塔があります。
文字もクッキリ、平らな面もとても綺麗です。
宝篋印塔(1706年鋳造)屋根は最近設置されたものだそうです。

本堂の、前へせり出す大きな屋根の傾斜が素晴らしかったのですが、うまく撮れませんでした。
近付くとかなり傷んだ部分が目に入ります。
この本堂は荒廃していた寺を、明治時代に山林経営に成功した当時の住職が、再建したものだそうです。
けれど戦後GℍQによる農地改革で、土地を売り払い、
時の住職は寺の維持に興味がなく、手に入ったお金で贅沢三昧、
そのまま庫裡は崩れ、池も涸れ、再び荒れ果てて・・・
ということで、現在の住職さんは遠方から通っておられるそうです。

黄檗宗と言えば、京都の宇治にある大本山万福寺。万福寺と言えば「鉄眼和尚」の話を思い出します。
鉄眼和尚は、隠元和尚が中国から持ち帰った経(一切経)のすべてを桜の版木に彫って刊行(出版)、
一気に日本中にお経を広めた和尚です。
万福寺の宝蔵院には、迷路のように床から天井までの棚が並び、
鉄眼が彫った何万枚もの版木がぎっしりと積み上げられています。
今も、その版木でお経を刷ることが出来るそうです。
また漢方薬を広め、販売する、ということを始めたのも、万福寺が始まりと聞いています。
医王寺の名はそんなところからきている?のかもしれません。
*隠元和尚は、インゲン豆、レンコン、タケノコ(孟宗竹)、スイカ、そして木魚、を日本に伝えた人物として知られています。
(現在万福寺で「普茶料理」を食べることが出来ます)

昔々、この医王寺と京都の万福寺を行ったり来たりした人がいたかもしれません。
山門の方は、土台部分が修理され周りも手入れされていました。


かわいい素敵な山門です。