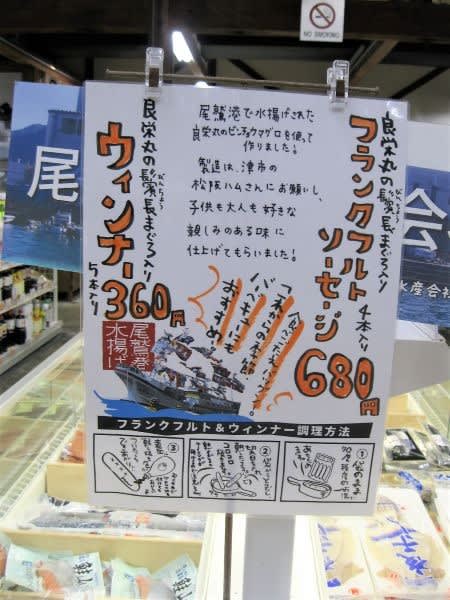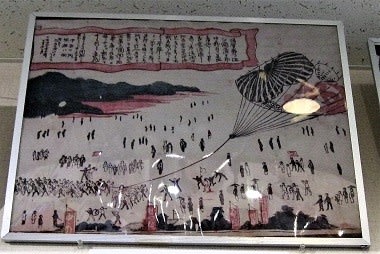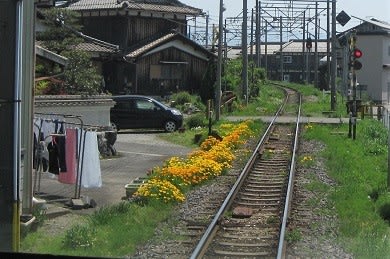海辺へ
2021-12-25 | 旅
先日買った「イワシせんべい」が美味しかったので、
その、袋の裏のシールに表記されている場所に、行って見ようということになって、
宮川の河口、同時に五十鈴川の河口でもある、伊勢湾に面する町まで、行ってきました。
「大湊」という地名のそこは、小さな島で、1本の小さな橋でつながっています。
「大湊」はかつては、伊勢と東国とを結ぶ重要な港で、
海運、商業の拠点だったそうです。
九鬼水軍の造船所があったところでもあり、鉄工所では釘や錠なども作られていたそうです。
1498年(明応7年)に明応地震による津波で1000軒の家屋が破壊されて5000人もの人がなくなったそうですが、
復活して、江戸時代には「堺」に比する港町だったそうです。
けれど、河口の土砂の堆積により、少しずつ港湾機能が衰えていったそうです。
知らなかったなー。
そして、今は寂れて、ではなくて!
古い家と、新しい家がくっついて建ち、狭い道を軽自動車が走り、
造船所?のクレーンがそびえ、鉄工所も、現役で稼働しているようです。
もちろん往時の様子とは比べるべくもないと思いますが。
また、別の日にゆっくり探索したいと思います。
小さな1本の橋の朝晩はどんな様子なのでしょう?
(地図で確かめたら、2本橋がありました。)

防波堤が高いので、
周りはすべて海なのに、
防波堤の上にのぼらなければ海を観ることが出来ません。
早くも夕暮れが迫る海は、
何とも言えない色で、粘りがあるような柔らかいような感じがしました。
海は見る度に違うなー

この辺りは海苔がいっぱい打ち上げられています。

手前の白いのはすべて貝殻です。
スーパーに寄って、鶏の骨付きモモと安いワインを買って帰りました。
鶏肉に塩コショウを擦りこみ、オリーブオイルをたっぷり塗って、
ニンニクのスライスを載せて、天火に入れて、約1時間後、
クリスマスイブの食事です。
考えてみれば、信心の無い私ですが、
食べ物だけは、年越しそばとか、雑煮とか、七草粥とか、お雛様のお寿司とか・・・
食いしん坊ということかな。

その、袋の裏のシールに表記されている場所に、行って見ようということになって、
宮川の河口、同時に五十鈴川の河口でもある、伊勢湾に面する町まで、行ってきました。
「大湊」という地名のそこは、小さな島で、1本の小さな橋でつながっています。
「大湊」はかつては、伊勢と東国とを結ぶ重要な港で、
海運、商業の拠点だったそうです。
九鬼水軍の造船所があったところでもあり、鉄工所では釘や錠なども作られていたそうです。
1498年(明応7年)に明応地震による津波で1000軒の家屋が破壊されて5000人もの人がなくなったそうですが、
復活して、江戸時代には「堺」に比する港町だったそうです。
けれど、河口の土砂の堆積により、少しずつ港湾機能が衰えていったそうです。
知らなかったなー。
そして、今は寂れて、ではなくて!
古い家と、新しい家がくっついて建ち、狭い道を軽自動車が走り、
造船所?のクレーンがそびえ、鉄工所も、現役で稼働しているようです。
もちろん往時の様子とは比べるべくもないと思いますが。
また、別の日にゆっくり探索したいと思います。
小さな1本の橋の朝晩はどんな様子なのでしょう?
(地図で確かめたら、2本橋がありました。)

防波堤が高いので、
周りはすべて海なのに、
防波堤の上にのぼらなければ海を観ることが出来ません。
早くも夕暮れが迫る海は、
何とも言えない色で、粘りがあるような柔らかいような感じがしました。
海は見る度に違うなー

この辺りは海苔がいっぱい打ち上げられています。

手前の白いのはすべて貝殻です。
スーパーに寄って、鶏の骨付きモモと安いワインを買って帰りました。
鶏肉に塩コショウを擦りこみ、オリーブオイルをたっぷり塗って、
ニンニクのスライスを載せて、天火に入れて、約1時間後、
クリスマスイブの食事です。
考えてみれば、信心の無い私ですが、
食べ物だけは、年越しそばとか、雑煮とか、七草粥とか、お雛様のお寿司とか・・・
食いしん坊ということかな。