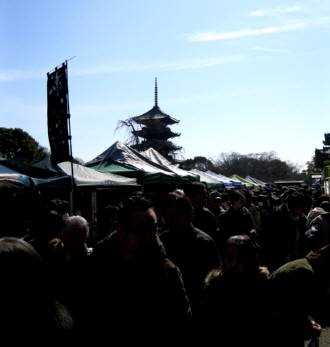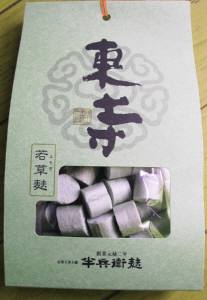京人形
2015-10-07 | 旅
自転車の時も、バスに乗って出掛けた時も、
なるべく通ったことが無い道を選びます。
若い時からそのような歩き方をしてきましたが、
京都の町なかの碁盤の目の細い通りは、
通ったことのない道、知らないところが、
無数に、まだまだいくらでもあります。

ここは、暖簾が掛っているのですが、
どこにも何も書いてありません。
でもちょうど表に出て来た年配の女性が人形屋です、と教えてくれました。
この大原女は先代が、三人官女の頭部を使って大原女に仕立てたものなんです、
と教えてくれました。

何とも優雅な大原女、美しい京人形です。
出窓の下の小さな空間に配置されている石や貝も地味に人形を引き立てています。

なるべく通ったことが無い道を選びます。
若い時からそのような歩き方をしてきましたが、
京都の町なかの碁盤の目の細い通りは、
通ったことのない道、知らないところが、
無数に、まだまだいくらでもあります。

ここは、暖簾が掛っているのですが、
どこにも何も書いてありません。
でもちょうど表に出て来た年配の女性が人形屋です、と教えてくれました。
この大原女は先代が、三人官女の頭部を使って大原女に仕立てたものなんです、
と教えてくれました。

何とも優雅な大原女、美しい京人形です。
出窓の下の小さな空間に配置されている石や貝も地味に人形を引き立てています。