ミシンは楽しい機械です。
machineの「マ」が「ミ」になったのも面白い。
昔の「鉄の匂いがする足踏みミシン」ほどではありませんが、
今も「ミシンは機械」という感じがします。
電動になり、ジグザグ機能やバック機能が出来、
自動糸通し機能もついて、感動です。
ミシンは慣れて使いこなすことが大事、また内部を掃除したり、
油を指すなどのメンテナンスも必要です。
そこのところが機械という感じがしていいのです。
ダダダダ・・・と動かすのが楽しくて、
今月の初めにハンカチでカーテンを作って以来、
時間があればミシンを動かしています。
先日アップしたミシンパッチワークの「袋」に続いて、
同じくミシンパッチワークの「クッションカバー」を2個、

中心は無地の正方形を9つつくり、
つなぎ合わせました。
スーパーの籠対応の、大きな「エコバッグ」も作りました。
裏付き、口部分は巾着仕様です。

使用しないときは、くるくる丸めてこの袋に入れて。

でも、ため込んだ布を見ているうちにやはり服が作りたい。
いつ、何を作ろうと思って買ったのか分からないけれど、
ローンのプリント生地を引っ張り出してみれば、
夏のブラウスならなんとか足りそう。
糸も各色いっぱいある。芯地もある。ボタンも大量に溜め込んでいる。
ミシン針は11号しかないけど、この布なら大丈夫そうです。
型紙を切るところから作るのは何年ぶりかな?
平面を体にフィットする立体に仕上げるために、
生地を各部品に分けて裁断します。
きちんと裁断できれば、半分以上出来たようなもの。
後はミシンで組み立てればいいのです。
久しぶりのボタンホールステッチにドキドキ、
絵画っぽいプリント生地(ローン)なので、
少々縫い目が歪んでいても、ムラがあっても目立たないのでよかった!
そんなわけで、洋裁の段取りなどを忘れてなくてよかった!

次は、ほとんど着ることがなかった夏のワンピースをブラウスに仕立て直そうかな。
machineの「マ」が「ミ」になったのも面白い。
昔の「鉄の匂いがする足踏みミシン」ほどではありませんが、
今も「ミシンは機械」という感じがします。
電動になり、ジグザグ機能やバック機能が出来、
自動糸通し機能もついて、感動です。
ミシンは慣れて使いこなすことが大事、また内部を掃除したり、
油を指すなどのメンテナンスも必要です。
そこのところが機械という感じがしていいのです。
ダダダダ・・・と動かすのが楽しくて、
今月の初めにハンカチでカーテンを作って以来、
時間があればミシンを動かしています。
先日アップしたミシンパッチワークの「袋」に続いて、
同じくミシンパッチワークの「クッションカバー」を2個、

中心は無地の正方形を9つつくり、
つなぎ合わせました。
スーパーの籠対応の、大きな「エコバッグ」も作りました。
裏付き、口部分は巾着仕様です。

使用しないときは、くるくる丸めてこの袋に入れて。

でも、ため込んだ布を見ているうちにやはり服が作りたい。
いつ、何を作ろうと思って買ったのか分からないけれど、
ローンのプリント生地を引っ張り出してみれば、
夏のブラウスならなんとか足りそう。
糸も各色いっぱいある。芯地もある。ボタンも大量に溜め込んでいる。
ミシン針は11号しかないけど、この布なら大丈夫そうです。
型紙を切るところから作るのは何年ぶりかな?
平面を体にフィットする立体に仕上げるために、
生地を各部品に分けて裁断します。
きちんと裁断できれば、半分以上出来たようなもの。
後はミシンで組み立てればいいのです。
久しぶりのボタンホールステッチにドキドキ、
絵画っぽいプリント生地(ローン)なので、
少々縫い目が歪んでいても、ムラがあっても目立たないのでよかった!
そんなわけで、洋裁の段取りなどを忘れてなくてよかった!

次は、ほとんど着ることがなかった夏のワンピースをブラウスに仕立て直そうかな。













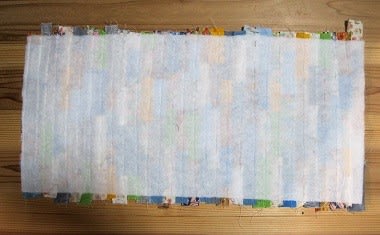



















 。
。




