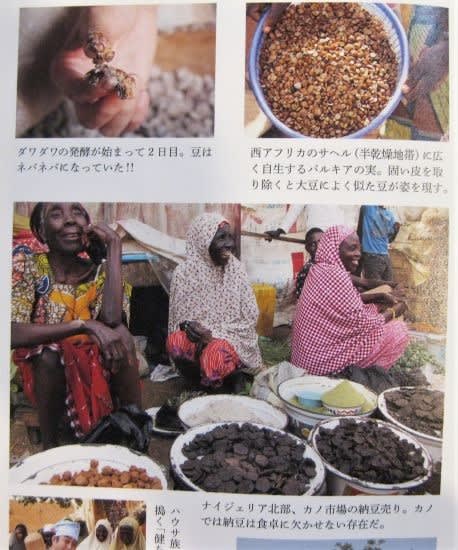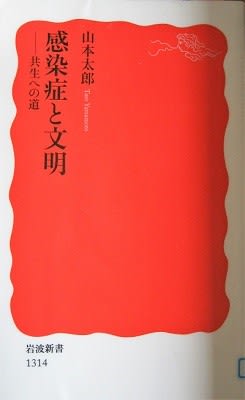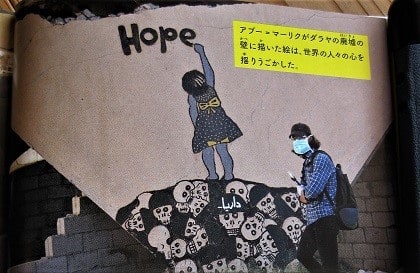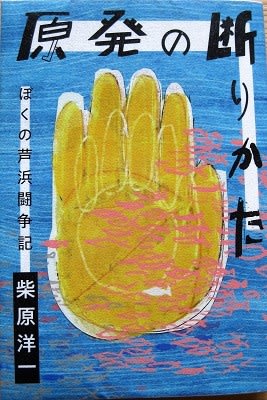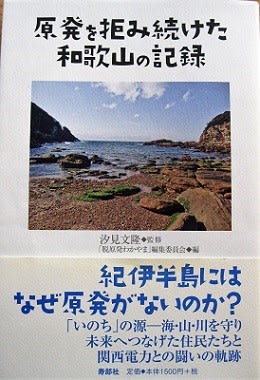日本の食生活全集24『聞き書 三重の食事』という題の
農山漁村文化協会(通称・農文協)の本を借りてきました。
地元三重県のことが知りたくて、借りてきました。
聞き書きが中心ですが、写真や図が豊富に入っていて、
パラパラめくって見るだけでも楽しい本になっています。
三重県は大まかに海岸部・平野部・山間部に分かれます。
私が棲んでいるのは平野部です。
平野部は広い田と水があり、気候も温暖で、冬は晴れの日が多く、
他の地域に比べると苦労の少ない地域と言われています。
けれど、昭和の初めころの食生活は、日常の基本は麦飯で、
そこに豆や芋などを混ぜたものでした。
山間部では芋やカボチャや菜を入れた麦の粥を朝昼晩食べていたそうです。
海岸部は典型的な半農半漁で、豊かな海産物がありましたが、
台風が来れば、漁船はもちろん、狭い耕地の作物は塩水や潮風の被害を受けてしまいます。
この本の表紙の海女たちは、夏季以外は出稼ぎに出たそうです。
海女稼ぎと言うのもあったそうで、遠く朝鮮までも、
海女が10人くらい、船頭一人の小さな船に乗って、
帆と櫂で、往復したのだそうです。
地域ごとに、それぞれ違う食生活ではありますが、
白米が特別の日のご馳走であることには変わりありません。
けれど、それぞれの地域の野山や川や海の自然の恵みを味わい、
各家庭のそれぞれの干物や漬物などがあり、工夫を凝らした食べ物がありました。
そして四季折々の、晴れの日には、日常と違った食べ物がありました。
貧しいだけではない、食べる楽しみがあったことを、
この本は伝えています。

『聞き書 三重の食事』日本の食生活全集24
農山漁村文化協会、S,62
日本の食生活全集 全50巻
農山漁村文化協会(通称・農文協)の本を借りてきました。
地元三重県のことが知りたくて、借りてきました。
聞き書きが中心ですが、写真や図が豊富に入っていて、
パラパラめくって見るだけでも楽しい本になっています。
三重県は大まかに海岸部・平野部・山間部に分かれます。
私が棲んでいるのは平野部です。
平野部は広い田と水があり、気候も温暖で、冬は晴れの日が多く、
他の地域に比べると苦労の少ない地域と言われています。
けれど、昭和の初めころの食生活は、日常の基本は麦飯で、
そこに豆や芋などを混ぜたものでした。
山間部では芋やカボチャや菜を入れた麦の粥を朝昼晩食べていたそうです。
海岸部は典型的な半農半漁で、豊かな海産物がありましたが、
台風が来れば、漁船はもちろん、狭い耕地の作物は塩水や潮風の被害を受けてしまいます。
この本の表紙の海女たちは、夏季以外は出稼ぎに出たそうです。
海女稼ぎと言うのもあったそうで、遠く朝鮮までも、
海女が10人くらい、船頭一人の小さな船に乗って、
帆と櫂で、往復したのだそうです。
地域ごとに、それぞれ違う食生活ではありますが、
白米が特別の日のご馳走であることには変わりありません。
けれど、それぞれの地域の野山や川や海の自然の恵みを味わい、
各家庭のそれぞれの干物や漬物などがあり、工夫を凝らした食べ物がありました。
そして四季折々の、晴れの日には、日常と違った食べ物がありました。
貧しいだけではない、食べる楽しみがあったことを、
この本は伝えています。

『聞き書 三重の食事』日本の食生活全集24
農山漁村文化協会、S,62
日本の食生活全集 全50巻