ほんと、久しぶりにどストレートに感動して胸が熱くなって、余韻にいつまでも浸る。
自分にそんな感性がまだ残っていたんだ、と見直したくなるくらいに。いい小説だったなあ、と。
私が手に取るのが遅すぎたのかもしれない。2010年の発行で、評判は当初からのようだったから。
地区センターの書棚に並んでいるシリーズ本を見て、何となく読んでみるかと。
何も知らないから0が最初なのだろうと「神様のカルテ0」から読み始めた。
違った、前日譚の短編集だったので改めて刊行順に「神様のカルテ」「神様のカルテ2」「神様のカルテ3」と
一気呵成に読み続けた。
それくらい力のある小説で、青臭く生真面目で端然とした登場人物たちが立場を超え考えの違いを超え、
おのれの信念のもとに医療にあたるさまが、心打ち胸熱くさせ考えさせられる。
誰もが決して声高に主張するわけでもない、誰が正しくて誰が悪いということではない。
24時間365日対応の地域医療センター本荘病院のあり方。
理不尽なことだらけの大学病院医局にも使命があり、それに向かって医師たちが邁進している。
多岐にわたる医師という仕事を、みな、それぞれの正義で立ち向かっている。
なにより登場人物すべての人たちが個性豊かに生き生きと、まるですぐそばで息をしているかのように描かれている。
シリーズ全作を通してこの小説には嫌な人が出てこない、違う、嫌な人はいるが悪い人は登場しない。
そのことがさらに物語を清々しくさせている。
御岳荘の住人。行きつけの居酒屋の亭主。
地域医療センター本荘病院で働く人たち、医師たち看護師たち患者たち。
信濃大学病院で働く同僚たち先輩の医師たち研修医看護師たち。
もちろん、一止の妻ハルさん、子供の小春ちゃんは、ときにいい人過ぎるんじゃないののというくらいに。
特に印象的な人たち。
「神様のカルテ」では、
夫を亡くし、寂しい思いばかりしてきて、孤独でそれだけの人生だったという安曇さんが、栗原一止医師と出会い、
最後の最後にこんな幸せな時間が待っていたなんて、本当に人生は分からないものです。と感謝して一止に手紙を残し旅立つ。
「神様のカルテ2」では、
大学で同級生だった辰也が本荘病院に、彼のあまりの変化に。
大狸先生と共に内科を支えていた先輩医師古狐先生との別れ。
重症患者留川トヨさんを看病していた夫の孫七さんが、
妻のために病室で歌う切々たる木曽節、孫七さんは後を追うようにその日に旅立つ。
「神様のカルテ3」では
本庄病院の新しい女性内科医の小幡医師。
命と真剣に向き合わないと感じる者に対しては、相手が医師であれ、患者であれ、非情なまでの態度を見せる
彼女が一止に言い放つ。
「ちょっとフットワークが軽くて、ちょっと内視鏡がうまいだけの、どこにでもいる偽善者タイプの医者じゃない」
きつい一言。それが一止に次のステップに進むきっかけになる。
そして、本荘病院や大学病院がある安曇野の豊かな四季の折々の風景が、
その時々の心情を映し出すかのようにカメラで写し取ったかのように描写されている。
わたしもその中に立って信州の風や音や色を味わってみたいと思うくらいに。
全シリーズのあらましはこちらに→ https://www.shogakukan.co.jp/pr/karte/
新章 神様のカルテ 最新刊 2019年2月5日初版発行
信州にある「24時間365日対応」の本庄病院に勤務していた内科医の栗原一止は、より良い医師となるため信濃大学医学部に入局する。消化器内科医として勤務する傍ら、大学院生としての研究も進めなければならない日々も、早二年が過ぎた。矛盾だらけの大学病院という組織にもそれなりに順応しているつもりであったが、29歳の膵癌患者の治療方法をめぐり、局内の実権を掌握している准教授と激しく衝突してしまう。
舞台は、地域医療支援病院から大学病院へ。
「新章 神様のカルテ」に寄せて
「神様のカルテ」を書き始めて、いつのまにか十年が過ぎた。私の歩んできた道を追いかけるように、栗原一止の物語も五冊目を数え、本作をもって舞台は大学病院へと移る。栗原は、私にいくらか似たところはあるが、私よりはるかに真面目で、忍耐強く、少しだけ優秀で、間違いなく勇敢である。そんな彼が、大学という巨大な組織の中で描きだす、ささやかな「希望」を、多くの人に届けたいと思う。
夏川草介 深夜2時半の医局にて
「新章 神様のカルテ」は、29歳で末期の膵癌を患っている7歳の女の子の母二木さん。
その治療に携わる一止医師。彼女の治療を中心に物語は展開していく。
患者は医師に命を委ねる。医師は患者によって成長する。
大学病院の医療とは、病気を治すとは、生きるとは、医師とは、携わるものとは患者とは患者の家族とは、
生死の瀬戸際に立つ一人の人間に対して視点は複層的に捉えられていて、読みながら熱くなってくる。
やはり、5作目の「新章 神様のカルテ」が10年を経たというだけあって素晴らしく、より厚みを増して読み応えがあった。










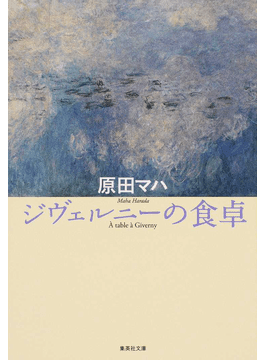 短編小説だから受賞は無理だったかもしれない、なんて偉そうだけれど。
短編小説だから受賞は無理だったかもしれない、なんて偉そうだけれど。


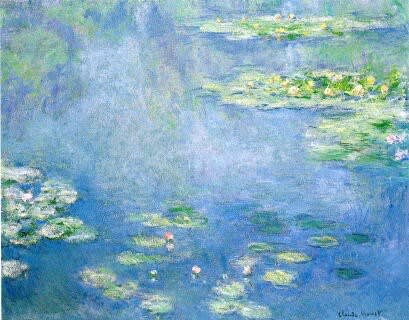

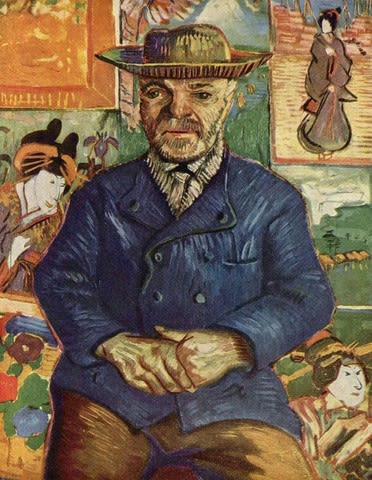
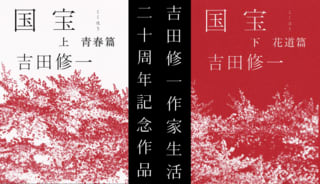
 『おおきなかぶ、むずかしいアボガド』
『おおきなかぶ、むずかしいアボガド』

 『東京會舘とわたし(上)』旧館
『東京會舘とわたし(上)』旧館 『東京會舘とわたし(下)』 新館
『東京會舘とわたし(下)』 新館 『かがみの孤城』はすっ飛ばします。
『かがみの孤城』はすっ飛ばします。

 文庫版
文庫版
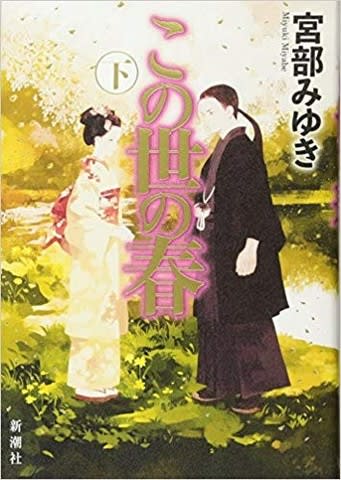
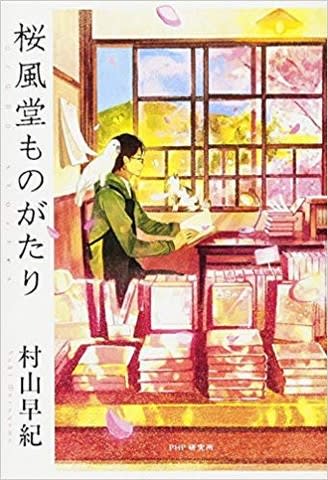 装画 げみ 装丁 岡本歌織
装画 げみ 装丁 岡本歌織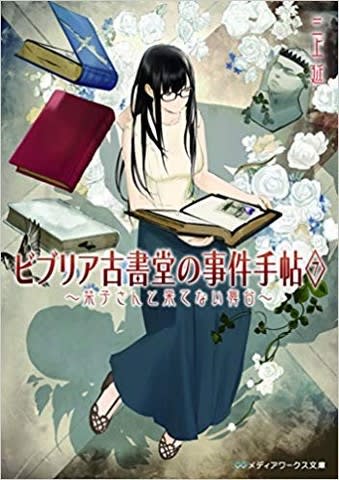 イラスト 越島 はぐ
イラスト 越島 はぐ 
 はい、面白かったです、とても。
はい、面白かったです、とても。





