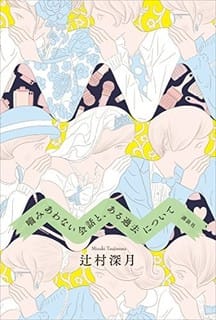「寒月六間堀」
いいタイトルだなとつくづく。
寒くて冷たい冬の夜、冴え冴えとした月が江戸の町を煌々と照らしている。
皆が寝静まったそんな夜、六間堀で事がおきる。
はたして・・・
うん、そんな情景が浮かんでくるのよ、タイトルひとつで。
『鬼平犯科帳』私はどうやら地名が入ったタイトルが好きなようだ。

平蔵はいつものように着ながしに編み笠の浪人姿で市中巡回している。
弥勒寺門前の茶店「笹や」で、若いころからの馴染みのお熊婆さんから
茶をもらってのみかけた、と何気もなく、弥勒寺の南、五間堀に
かかっている弥勒寺橋のたもとを見やって、
(や・・・・・?)
きらりと、眼が光った。
もうここら辺からすでに何がおきるのかとドキドキが始まるのよ。

平蔵は七十をこえた旅の老武士市口瀬兵衛
(垢じみた、よれよれの旅装を小柄な痩せこけた身につけ、
陽に焼けつくし埃にまみれつくした渋紙色の老眼の、目鼻立ちよりしわが目立った)
が、わなわなふるえる手でよれよれの鉢巻きをしめ、大刀を引き抜くのを注視する。
そして、尾行せずにはいられない悲壮さとあわれさを、老武士に感じてしまって。
息子の仇討ちをするというこの老人を、密偵や与力同心の手助けなく
自らひとりで助太刀することになるわけ。
その助太刀の場面の情景描写がこちら。
本所の堅川と深川の小名木川をつなぐ六間堀川南端にかかる猿子橋の西たもとは、
右が幕府の御籾蔵、左が深川元町の町家であった。
その御籾蔵の角地へうずくまっている市口瀬兵衛と仙次郎の前に、先ずあらわれたのは
長谷川平蔵である。

ドラマのワンシーンにみる映像がありありと。監督やカメラマンは腕の見せどころだろうな。
そして。その夜を池波さんが書くとこうなる。
青白い月光が、道を、家並みを、水の底に在るもののように浮き上がらせ、
寒気はきびしかった。
11巻まで読み終わったけれど、
この「寒月六間堀」のように盗賊が出てこない話は今のところない。
かように珍しい話だ。といきなり池波さんになったりして。
どの話もそうなのだが、ことのほか後味がまことにすっきりして心地良い気分に浸るわけ。
そして、しみじみとして温かいものが胸の内に広がっていくわけ。


ところで、池波さんは冒頭、平蔵に言わせている。
長くなるけれど引用しますね。好きな件なので。
火付盗賊改方の長官(おかしら)・長谷川平蔵宣以(のぶため)は、
その生い立ちが生い立ちだけに、
「四十をこえてみて、わしは、その二倍も三倍もの年月を生きてきたようにおもえる。
さればさ、もう生きているのが億劫になった」
と、妻女の久栄に、よく語りもらすことがある。
つまり、それだけ多彩な人生を体験してきたからであろうが、いまになってみると平蔵、
つくづくとこうおもうのである。
(つまりは、人間(ひと)というもの、生きて行くにもっとも大事のことは・・・・・
たとえば、今朝の飯のうまさはどうだったとか、今日はひとつ、なんとか暇を見つけて、
半刻か一刻を、ぶらりとおのれの好きな場所へ出かけ、好きな食べ物でも食べ、
ぼんやりと酒など酌みながら・・・・・さて、今日の夕餉には何を食おうかなどと、
そのようなことを考え、夜は一合の寝酒をのんびりとのみ、疲れた躰を床に伸ばして、
無心にねむりこける。このことにつきるな)
ま、私もそう思わなくもない。恐れ多いけれど。
が、私のそれは、思ったとしても平蔵さんのように、
日々命を張ってお勤めに励んでいるわけじゃないから、
どうしてもただの怠け者になって、どこの誰へともなく「申し訳ない」
と小さくなるのである。なんて。
それにしても池波さん、40代の平蔵にこんな述懐をさせるなんて。
(いや当時の40代は今とは比べ物にならないくらい老成してたものね)
ご自身にも思うところがあったのかしら、とこれは要らぬお世話。















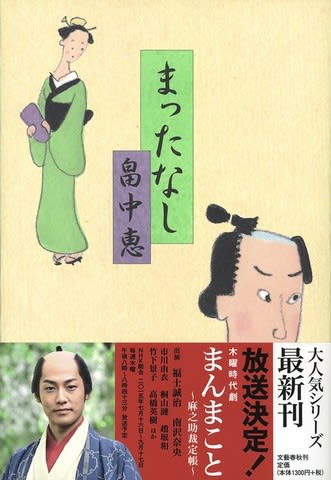










 (webより)
(webより) ロバートキャンベルさん(webより)
ロバートキャンベルさん(webより) (佐渡)
(佐渡)






 『平場の月』 朝倉 かすみ
『平場の月』 朝倉 かすみ 『美しき愚かものたちのタブロー』 原田マハ
『美しき愚かものたちのタブロー』 原田マハ 『マジカルグランマ』柚木麻子
『マジカルグランマ』柚木麻子