娘からの電話。
「ただいまチュッパがまた拗ねているんです」って。拗ねガールチュッパ。直るまでが長いのよ。
なんでもお母さんとクイズをしていたそうな。
「お母さんはシュークリームとプリンとどっちが好きでしょう?」
「プリン!」とチュッパは答えたんですって。ぶぶーっ、シュークリームでした。
とたん、チュッパは泣きだし、ひと言も言わずベッドで泣きながらの拗ねガール発揮だそうな。
そんなチュッパにと横浜年上友がクリスマスプレゼントしてくれた。ありがとう。
絵本 『つまんない つまんない』 ヨシタケシンスケさん作

ちょっとまだ難しいかもよって。大丈夫、チュッパは天才だから、と言って私が読み始めた。
なんだなんだこの5歳くらいの坊や、私じゃないの。私の心そのものだわ。おやまあ。
長くなるけれど、太字で書いてある文だけ書き写しますね。(2行3行に渡って書いてある文も1行にします)
うーん・・・なんか つまんない。
ウチの おもちゃは もう みんな つまんないし、きょうは テレビも つまんない。

ていうか・・・つまんないのって だれのせい?
どうして つまんないんだろう。 つまんないって、 なんだろう。
たとえば「ぐるぐるまきにされる」 のって すごく おもしろそうだけれど、
ずーっと ぐるぐるまきなのは つまんなそうだ。
「ずーっと なにかが おなじ」 っていうのが つまんないのかな。
いつもと どこかが ちょっと ちがうと おもしろいのかな。
ちがえば ちがうほど おもしろいのかしら。

じぶんに かんけいないと、つまんないのかな。
じぶんの おもいどおりに ならないと、つまんないのかな。
ダンゴムシって、「つまんないな」って おもうんだろうか。
(太字部分 略)
・・・っていうか 、 よのなかには 「おもしろいこと」 と 「つまんないこと」 しかないのかな。
よくかんがえたら、 「なーんにも かんがえていないとき」 ってのもあるな。
べつに おもしろくはないけど、つまんないわけでもない。
ああいうときの きもちって、なんて いえば いいんだろう。 うーん。
(太字部分 略)
いちばん つまんないのって、なんさいだろう。
おじいちゃんは 「むかしあった つまんないこと」 を はなすとき、ちょっと たのしそうだった。
つまんないことって、じかんが たつと おもしろく なるのかな。
たのしそうにしているけど、ほんとは つまんないひと、 って いるのかな。
つまんなそうだけど、じつは ちょっとたのしい、って ひとも いるのかな。
おとなは つまんないとき どうしてるんだろう。
こどもは しらない なにかが あるんだろうか。
(おとうさん) どんなに つまんないことだって、じぶんしだいで おもしろくできるんだよ?
それに、つまんないことがあるから、おもしろいことが たのしくなるんじゃないの?
(ぼうや) そのはなしは こないだも きいたから つまんない!!
最高のオチ、好き!面白い。
あははは、坊やの疑問にひとつひとつ相槌打ってあげたい、そうだよそうよねって、そんな気持ちってあるよねって。
だってその坊やは私そのものですから。
いくら天才チュッパでも、こりゃあ難しいかな。ま、そのうち分かるようになる。











 『漢方小説』
『漢方小説』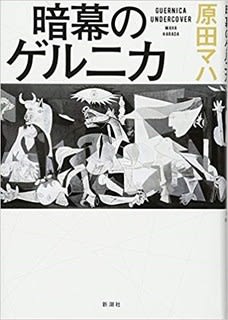


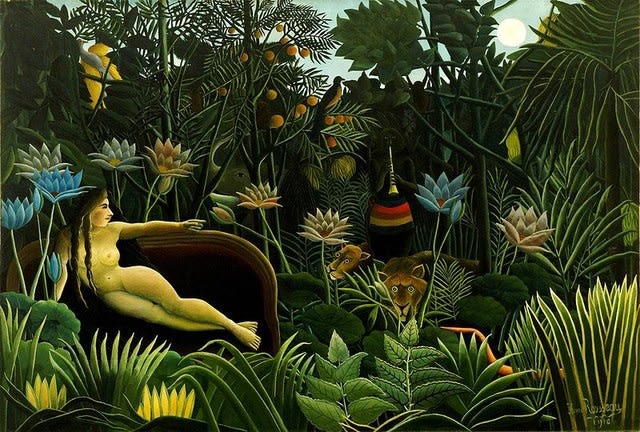

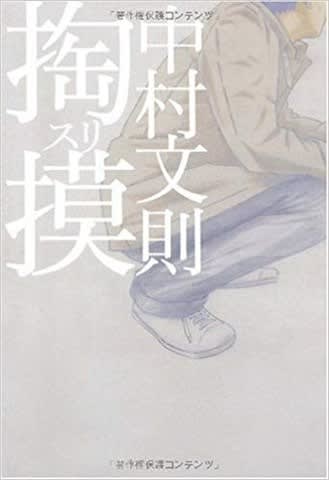

 浅田次郎さん『椿山課長の七日間』 2002年著
浅田次郎さん『椿山課長の七日間』 2002年著 『あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続』宮部みゆき
『あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続』宮部みゆき
 本の挿絵は白黒です。
本の挿絵は白黒です。





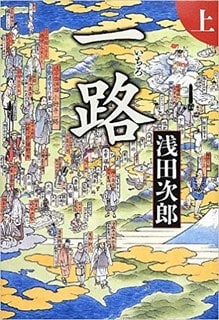
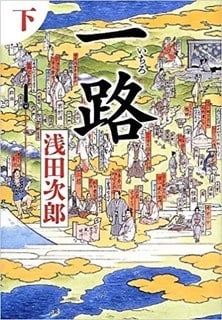

 天野節子さん『目線』
天野節子さん『目線』
 妙本寺
妙本寺 報国寺
報国寺 本覚寺
本覚寺 覚園寺
覚園寺 獅子舞
獅子舞 昨夕 18:08
昨夕 18:08 『氷の華』 天野節子著
『氷の華』 天野節子著 『午後2時の証言者たち』 天野節子著
『午後2時の証言者たち』 天野節子著 『消えた人達』 北原亜以子著
『消えた人達』 北原亜以子著



