(2024年2月27日投稿)
【はじめに】
今回のブログでは、次の参考書をもとに、古文の特徴と文法について解説してみたい。
〇藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]
藤井貞和先生は、日本文学者、東京学芸大学教授、のち東京大学名誉教授である。
古文を勉強していると、書いてあるはずの主語がよくわからなくなって、意味がとれなくなる、ということがある。それは、主語の省略によるものである。藤井先生によれば、古文において、主語が見えなくなっていることは、それが談話に近い文体であることの一つのあらわれにほかならないという。こうした古文の特徴について、詳しく解説されているのが本書である。
その他、話し言葉としての敬語、丁寧の表現、係り結びが流れるとき、謙譲表現および文法事項について、主な項目を説明しておきたい。
【藤井貞和『古文の読みかた』はこちらから】

古文の読みかた (岩波ジュニア新書 76)
藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書
【目次】
はじめに
Ⅰ 古文を解く鍵
1 古文はどのように書かれているか
2 主語の省略
3 話し言葉としての敬語
4 最高敬語から悪態まで
5 丁寧の表現について
6 係り結びとは何だ
7 係り結びが流れるとき
8 助動詞のはなし――時に関する助動詞を中心に
9 人は推量によって生きる――推量の助動詞
10 助詞の役割
Ⅱ 古文の基礎知識
11 受身について――る・らる(1)
12 ”できない”ことの表現――る・らる(2)
13 使役と尊敬――す・さす・しむ(1)
14 助動詞による尊敬表現――す・さす・しむ(2)、る・らる(3)
15 尊敬表現のまとめ
16 謙譲表現のまとめ
17 敬語の実際――二方面敬語
18 「打消」の方法――助動詞「ず」など
19 希望の表現――まほし・たし
20 仮定(ば・とも・ども・その他)と仮想(まし)
21 推量の助動詞「らし」と「べし」
22 推量の「めり」と伝聞の「なり」
23 断定の助動詞「なり」と「たり」
24 比喩をめぐって――ごとし・やうなり
25 格助詞とは――「に」を中心に
26 接続助詞とその周辺
27 副助詞いろいろ
28 係助詞とその周辺(1) ――ぞ・こそ・なむ
29 係助詞とその周辺(2) ――や・か・は・も
30 終助詞、間投助詞、並立助詞
Ⅲ 古文を読む
31 説話文
32 事実談
33 寓話
34 物語文(1)
35 物語文(2)
36 日記文(1)
37 日記文(2)
38 万葉集
39 軍記物
40 批評文
41 徒然草(試験問題から)
42 古文学習と現代語訳
付編
さくいん
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、v頁~viii頁)
さて、今回の執筆項目は次のようになる。
・主語の省略
・話し言葉としての敬語
・丁寧の表現について
・係り結びが流れるとき
・謙譲表現のまとめ
・係助詞とその周辺(1) ――ぞ・こそ・なむ
・係助詞とその周辺(2) ――や・か・は・も
・終助詞、間投助詞、並立助詞
主語の省略
〇2 主語の省略
・古文を勉強していると出会うことだが、書いてあるはずの主語がよくわからなくなって、意味がとれなくなる、ということがある。
だれが、とか、何が、とかいうことを指示してくれる主語がわからなくなったら、大あわてである。
よく探すと主語が書かれてある場合もあるけれども、多く、古文がよくわからなくなるのは、主語が書かれていないからである。
・主語が省略されるといっても、ある動作や状態の主体が存在しない、ということはけっしてない。
「書きたまふ」という一文があると、だれが、という動作主(書くという動作の主体のこと)は、主語つまり表現された語句としてはあらわれていないけれども、「書きたまふ」という表現の背後に、ちゃんと存在している。
こういうのを、主語が省略されている、という。
〇主語が省略されている場合には、二種類ある。
①簡単なケース
②複雑なケース
①主語の省略の簡単なケース
<例文>三河の国、八橋といふ所に至りぬ。(『伊勢物語』九段)
【訳文】
三河の国(今の愛知県東部)、八橋という地にやって来た。
・「至りぬ」で止まっている一文であるが、だれが至ったかというのか、主語がない。
でも、この一文の前後を見れば、動作主は明らかになる。
・ 昔、男ありけり。その男、身をえうなき者に思ひなして、京にはあらじ、東の方に住
むべき国求めにとて行きけり。もとより友とする人、一人二人して行きけり。道知れる
人もなくて、惑ひ行きけり。
三河の国、八橋といふ所に至りぬ。(『伊勢物語』九段)
【訳文】
昔、男がおったということだ。その男は、自身を必要のない者であると思い込ませて、京におるわけにはいかないだろう、東国地方に住むことのできる国探しに、といって出かけたということだ。以前からの友人たち、一人二人といっしょに行ったということだ。道を知っている人もいなくて、迷いながら行ったということだ。
三河の国(今の愛知県東部)、八橋という地にやって来た。
※教科書でよく見かける『伊勢物語』九段の冒頭である。
最初の一文に、「男」がおったということだ、と物語全体の中心となる動作主を主語のかたちで示し、つぎの一文で、「その男」が東国に出かけたということだ、とこれも動作主を主語であらわす。
ついで、友人たちといっしょに行ったということだ、とあって、「一人二人して行きけり」の動作主も、前の二文に出てきた「男」である。
⇒この文からあとは主語をいちいち「その男」とはいわない。
いわなくてもわかるから、いう必要がない。必要がなければ省略されるのである。
・「三河の国、八橋といふ所に至りぬ」の主語は、あらわす必要がないから省略されている。
動作主は主人公の男である。
※いや、ちょっと待てよ、という人がいるかもしれない。
友人たちと行動をともにしているのだから、動作主は、その男をもふくめた、ご一行様(いっこうさま)にしたほうがよくはないかな。なるほど。主語が省略されることによって、その省略された内容が、その男一人をさすか、友人をふくめた一行をさすか、広がりを生じてきた。どちらがいいと思うか。
※こうした、文の一部の省略によって内容がふくらみを生じることこそ、日本語の大きな特色なのだという。
時と場合とによりけりだが、いまの例はその男一人とも、友人をふくめた一行とも、どちらにとってもかまわない。
以上が、主語の省略の簡単なケースである。
②主語の省略の複雑なケース
・主語が、いくら探しても、文章のなかにまったく書かれていない、という場合が、主語の省略の複雑なケース。
動詞があると、その動作主はかならずあるはず、いるはずだが、その動作主が文章のなかに主語として指示されていない場合がある。
そういうケースはけっして少なくない。
<現代語の主語の省略>
「書いてごらん。」A
「書けないよ。」B
現代語でも、このように主語の省略はあらわれる。
AとBとは、それぞれ、動作主がだれであるかわからない。
あえて主語を加えると、次のようになろう。
「(きみは)書いてごらん。」
「(ぼくは)書けないよ。」
※しかし、会話文の実際に、「きみは書いてごらん」という言いまわしはありえない。
なぜなら、「書いてごらん」というのは、相手に書くことをすすめる、一種の命令法だから、当然、主語は省略される。(英語と同じである)
「書けないよ」も、強調なら「ぼくは書けないよ」ともいうが、ふつうなら「ぼくは」とわざわざいってもしようがない。これも当然省略される。
<現代語の主語の省略>
・次のような談話文もまったく同じことで、主語はあらわれない。
あらわれなくても、困ることはない。
「まだお茶も差し上げておりませんのに、もうお帰りになるのですねえ。」
※お茶を差し上げるのはこの談話の話し手、お帰りになるのは談話の相手である。
まぎれようがない。
その話し手がだれか、相手がだれか、実体はわからないが、談話のなかではまったくそれを提示する必要がない。
主語が省略されている、ということは、その文章が当事者の行為や相手の行為であることに深くかかわっている。
【古文の場合】
〇古文は、地の文といえども、きわめて談話に近い文体から成っている、といわれる。
古文において、主語が見えなくなっていることは、それが談話に近い文体であることの一つのあらわれにほかならない。
<例文~『枕草子』の一節>
まだ御格子は参らぬに、大殿油さしいでたれば、戸の開きたるがあらはなれば、琵琶
の御琴をたたさまに持たせたまへり。
(『枕草子』上の御局の御簾の前にて)
【現代語訳】
まだお格子は下して差し上げていないときに、お部屋の明かりを差しだしますと、戸の開いているところが見通しなので、琵琶のお琴を立ててお持ちになっていらっしゃいます。
※中宮定子(清少納言がお仕えしている)のことを述べている段の一節である。
談話の文体であることを見ぬいてほしい。
古文は現代でいえば、すべて談話の文体だ、ぐらいに割りきってほしい。
原文に併記した口語訳を見れば、一目瞭然。
当事者の談話だから、話題の中心である中宮定子のことを、名ざしでいうはずがない。
「持たせたまへり」と動詞だけでいうので、まぎれようがない。
・お仕えする侍女たちは、格子を上げ下げするのが役目であるが、それをわざわざ「(わたくしたちは)まだお格子は下して差し上げてもいないのに」と、談話のなかでいうはずもまたない。
※『枕草子』のこの段は、全文を読みすすめても、ついに「持た」の主語は書きあらわされていない。
その全文を次節にかかげるが、動作主は、主語としては、ほとんど書かれていない。
しかも動作主は中宮定子をふくめて、少なくとも四人いるようだ。
これを単なる地の文として読んだら、わかりっこない。
談話であると知っていれば、主語の省略されている呼吸が読みとれ、内容が理解できるようになる、と著者はいう。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、8頁~13頁、210頁)
話し言葉としての敬語
〇3 話し言葉としての敬語
『枕草子』上の御局の御簾の前にて
上の御局の御簾の前にて、殿上人、日ひと日、琴、笛、吹き、遊び暮らして、大殿油
参るほどに、まだ御格子は参らぬに、大殿油さしいでたれば、戸の開きたるがあらはな
れば、琵琶の御琴をたたさまに持たせたまへり。紅の御衣どもの、いふも世の常なる袿、
また、張りたるどもなどをあまたたてまつりて、いと黒うつややかなる琵琶に、御そで
をうち掛けて、とらへさせたまへるだにめでたきに、そばより、御額のほどの、いみじ
う白うめでたくけざやかにて、はづれさせたまへるは、たとふべきかたぞなきや。近く
ゐたまへる人にさし寄りて、「半ば隠したりけんは、えかくはあらざりけんかし。あれ
はただ人にこそありけめ。」と言ふを、道もなきに分け参りて申せば、笑はせたまひて、
「別れは知りたりや。」となん仰せらるる、と伝ふるもをかし。
(『枕草子』上の御局の御簾の前にて)
・傍線の動詞は、動作主が書かれていない。
その動作主は、少なくとも四人いるようだ。
ただしそのなかの一人は、「近くゐたまへる人」(近くにすわっていらっしゃる人)なので、この人の動作を除けば、三人の動作が、一段の全文からはついに主語を明らかにすることができない、ということになる。
・もしこれが『枕草子』であることを知らなかったら、専門家でさえ行きづまってしまう、ということはあると思う。
最低限度の知識として、これが中宮(トップクラスの皇后のことだと思ってよろしい)である定子に仕えた清少納言という侍女が記録したもの、いわゆる女房文学の一つであることは知らなければならない。もっとも、最低限度知るべき知識の量はわずかなものである。
『枕草子』は中宮定子のサロンの様子を語りつたえているものである。
・語りつたえているものだから、談話式の文体になっている。
地の文であるが、話すような口吻(こうふん)で書かれている。
だから女主人のことや、侍女たちの動作には主語が省略されている。
・主語が省略されている、上の文章のなかの傍線の動作は、したがって女主人の動作、および侍女の動作が中心になっているわけだが、それをどう見分けたらいいのだろうか。
どの動詞が女主人=中宮定子の動作をあらわし、どの動詞が侍女たちの動作をあらわしているのだろうか。
これを知るには敬語というものが手がかりになる。
おおよそのところが、敬語というものによって、判断できる。
それは古文の地の文に、敬語というものがちりばめられていて、現実の身分関係を反映しているからで、それで身分のいちばん高い中宮定子などはすぐにわかる。
・古文の地の文には、なぜ、敬語が出てくるのだろうか。
こういう疑問を持つことがだいじである。
現代の小説のたぐいを思いうかべてほしい。現代の小説は地の文と会話文とから成る。地の文には、ふつう、敬語は出てこない。会話文にだけ敬語が出てくる。
ところが、古文では、会話文に敬語が出てくるのはもちろんのことだが、地の文にもしきりに敬語が出てくる。
これは古文の地の文が、現代の小説などにみる地の文と大きくちがって、はるかに会話文に近い、談話の文体になっているからにほかならない。
これはだいじなことである。
尊敬語や謙譲語は、ふつう、人物の身分関係をあらわすために使われているものといわれていて、おおよそその説明は、それでまちがっているということはないのだが、より厳密にいうならば、実際の談話の現場でのさまざまな敬語のありかたが、書かれた文章のなかに反映している。古文は地の文といえども談話的に書かれているのだから、実際の談話の現場を反映して敬語がどんどん出てくる、というわけである。
・かならずしも身分の上下をあらわさないことがある。
現代語でも、「書いてごらん。」A
「書けないよ。」B
と、「ごらん」という敬語はよく使われるが、Aが親の言葉であったり、先生の言葉であったりして、すこしもおかしくない。その場合、Bは子どもの言葉であったり、生徒の言葉であったりする。現代の会話としてすこしもおかかしくない。
現代のような身分差が少なくなった社会でも敬語が生きるのは、敬語が、本来、談話のなかで、相手を尊敬したり、自分がへりくだることで話題をスムーズにすすませるものであったからで、それが古文では身分制度と結びついて、上下をあらわす記号であるかのようにふるまうことになった。
・決して難しいことではないので、例文の
近くゐたまへる人にさし寄りて
というところを見てほしい。
「さし寄り」は、動作主を主語としてあらわさない動詞の例であるが、その動作主とは侍女の一人、つまりこの文章の書き手である清少納言そのひとの行為をいっている。
清少納言が「近くゐたまへる人」にさし寄ったのである。
この「ゐたまへる」という言いまわしのなかの「たまへ」というのが尊敬語である。
「近くゐたまへる人」で、「すわっていらっしゃる人」という意味になる。
この「人」も侍女であるが、尊敬語を使っているから、清少納言よりも身分の高い侍女なのであろうか。けっしてそんなことはいえないだろう。中宮定子の近くにお仕えしている侍女であることと、談話的な文体であることとから、自然に敬語が出てきたにちがいない。
・「近くゐたまへる人」の「たまへ」がけっして身分の上下をあらわす記号として使われているのではない証拠に、同じ侍女の動作が、
道もなきに分け参りて申せば、
と、謙譲の表現になっていたり、
と伝ふるもをかし。
と、敬語ぬきの表現になっていたりする。
「分け参り」「申せ」の二語は謙譲語という。
この侍女が、女主人である中宮定子に向かって近づくのに、「分け参り」と、女主人にたいしてへりくだり、「申せ」と、女主人に申しあげる行為をへりくだって表現している。
女主人と侍女とは、厳然とした身分の差があるから、謙譲語を使うのは当然である。
ただし、「分け参り」と表現し、「申せ」と表現している人は、その侍女ではなくて、これを書いている清少納言そのひとである。
自分たちの女主人を心からうやまう気持ちが、自分たちの行為をへりくだらせる謙譲の表現となってあらわれたので、それが結果的に身分の上下をあらわした。
相手の身分が高くても、もし尊敬する気持ちがなくて、かげで悪口をいう場合ならば、敬語なんか使うには及ばない。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、14頁~19頁)
丁寧の表現について
〇5丁寧の表現について
・会話の文体に出会ったら、「はべり」があるかないかをたしかめてほしい。
丁寧な会話か、そうでないかを見ぬいてほしい。
※亡き桐壺更衣(桐壺帝の寵愛した女性で、光源氏を生んでまもなく亡くなった)の母君のもとへ、帝のお使いの靫負(ゆげいの)命婦がたずねてきたところである。
南面におろして、母君もとみにえものものたまはず。(母君)「今までとまりはべるがいとう
きを、かかる御使の、蓬生の露分け入りたまふにつけても、いと恥づかしうなん。」とて、
げにえたふまじく泣いたまふ。(命婦)「『参りてはいとど心苦しう、心肝も尽くるやうになん。』
と、典侍の奏したまひしを、もの思うたまへ知らぬ心地にも、げにこそいと忍びがた
うはべりけれ。」とて、ややためらひて、仰せ言伝へきこゆ。(『源氏物語』桐壺の巻)
(南正面に下りさせて、母君もまた、すぐには何もおっしゃれない。(母君)「今まで生き残っておりまするのが、まことにいやでたまらないのに、こんなお使者が、蓬屋(ほうおく)の露を分けておいでくださるにつけても、まことに恥ずかしくて。」と言って、いかにもこらえ切れないぐらいお泣きになさる。(命婦)「『おうかがいしてみると、まことにまことにおいたわしくて、心も肝も消え失せるようで。』と、典侍が奏上していましたが、風情を解し申しあげない者の心持ちにも、なるほどまことに堪えがたいことでございましたよ。」と言って、少々時間をおいてから、帝の仰せ言を伝え申し上げる。)
※このように会話文の丁寧なものには「はべり」が使われて、あらたまった感じになる。男も女も使う語である。
・上の例について、それぞれ母君と命婦とが、自分の行為について「はべり」と言っているのであるから、これは謙譲語であると考えてもよいのではないか、という意見を持つひとがいたら、なかなか鋭い。もと謙譲語であったから、区別のあいまいなところがあるのは仕方がないらしい。
北山になむ、なにがし寺といふ所に、かしこき行ひ人はべる。去年(こぞ)の夏も世におこり
て、人々まじなひわづらひしを、やがてとどむるたぐひあまたはべりき。(『源氏物語』若紫の巻)
(北山にですが、何々寺という所に、すぐれた修行者がございます。去年の夏も世間に
わらわ病みが流行して、人々が、まじなっても効きめがなくて、てこずったのを、即座に
なおす例がたくさんございました。)
※いちおう、“伺候している”“お仕えしている”という意味がはっきりしている例は謙譲の「はべり」、それ以外の、会話に出てくる例は丁寧の「はべり」であると考えてほしい。
以上は、原則である。
会話のなかでもないのに、丁寧の「はべり」が出てくることはある。
『紫式部日記』という、『源氏物語』の書き手である紫式部の書いた日記文学には、地の文のある部分に集中してたくさん「はべり」が出てくる。
※『紫式部日記』のある部分に集中して「はべり」が出てくるのは、その部分だけだれかにあてて書かれた書簡ではないかと考えられている。書簡なら会話の文体で書かれていても、おかしくない。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、28頁~30頁、211頁)
係り結びが流れるとき
〇7 係り結びが流れるとき
Ⅰ 古文を解く鍵の「7 係り結びが流れるとき」
・係り結びは文の緊張をみちびく。
文というものは、ところどころに緊張があるからすぐれたものになるので、もし緊張がなければ、だらっとした締まりのない文章になり、名文でなくなってしまう。
「ぞ」「なむ(なん)」「こそ」による係り結びは、文を緊張させるためにだけある、といっていい。
「や」や「か」は疑問をあらわすが、これによって文章に一種の逆流をもたらし、「や」や「か」のある一文を連体形で止めることによって、他の文とちがう雰囲気を作りだすから、これも文の緊張をみちびくもの、ということができる。
ところが、「ぞ」「なむ(なん)」「こそ」、あるいは「や」も「か」もそうだが、ときにその緊張が、これらの語句によってはじまったのに、途中や文の終りで、流れてしまうことがある。
【結びの消失】
〇つぎの文章は、『源氏物語』桐壺の巻のごく初めのところである。
心細い桐壺更衣の様子が描かれている。
父の大納言は亡くなりて、母北の方なむ、いにしへの人のよしあるにて、親うち具し、
さしあたりて世のおぼえはなやかなる御方々にもいたう劣らず、何ごとの儀式をももて
なしたまひけれど、取りたてて、はかばかしき後見しなければ、事ある時は、なほ拠り
どころなく心細げなり。(『源氏物語』桐壺の巻)
(父の大納言は亡くなって、母の、大納言の奥方がですね、昔かたぎの由緒ある人で、
両親が揃い、現在のところ世間からちやほやされている御方々にもたいして引けをとら
ぬよう、どのような宮廷のしきたりをも処置なさったとかいうことだが、格別に、しっ
かりした後楯(うしろだて)は、ないのだから、あらたまったことのある時には、やはり
頼るあてがなくて、更衣は心細げである。)
※「……母北の方なむ」と、係助詞「なむ」があるので、文が緊張し、結びの連体形を要求する。ところが、一文の終りは「心細げなり」と、終止形である。
連体形ならば「心細げなる」とならなければならないところ。
母北の方なむ、いにしへの人のよしある(人なる)。
という、括弧のなかにある。(人なる)という結びと呼応しているが、消えてしまったと考えられ、これを「結びの消失」という。
※ちょっと難しいことかもしれないが、文の緊張は、文脈上の実質的な述語の部分と呼応してはたらき、そこに「係り結びの法則」が成りたつのだから、文が上記のように長くつづいてゆくと、実質的な述語の部分が文末にならないために、「係り結びの法則」が成りたたなくなり、結びの消失してしまうことがある。
「結びの消失」とは、係り結びにおける「結びの消失」であって、「文末の消失」ではない。
文末のない文はありえないから、勘ちがいしないように。
【挿入句のばあい】
『源氏物語』桐壺の巻で、まえに引いた文章の直前のところに、次のようにある。
唐土にも、かかる事の起りにこそ、世も乱れあしかりけれと、やうやう、天の下にも、
あぢきなう人のもてなやみぐさになりて、楊貴妃の例も引き出でつべくなりゆくに、い
とはしたなきこと多かれど、かたじけなき御心ばへのたぐひなきを頼みにて交らひたま
ふ。(『源氏物語』桐壺の巻)
(中国にも、こうした発端からこそ、世も乱れてひどいことになったのだったと、だんだん、世間一般にも、おもしろからぬ厄介種(やっかいだね)になって、楊貴妃の例をも引き合いに出しかねないほどになってゆく事態に、まことにいたたまれない思いのすることが多くあるけれど、おそれ多い帝の御愛情のまたとないことを頼みにして、宮仕えなさる。)
※「唐土にも、かかる事の起りにこそ」と、「こそ」がある。
一文の終りは「たまふ」と終止形(連体形も同形だが)になっている。已然形の「たまへ」になっていない。でも、あわてないでほしい。
唐土にも、かかる事の起りにこそ、世も乱れあしかりけれ。
と、已然形の結びがちゃんとある。
このように、見かけ上、文中にあることがあるので、注意すること。
※和歌の場合も、
「我が庵(いほ)は都のたつみしかぞ住む世を宇治山と人は言ふなり」(喜撰法師)とか、
「八重葎(やへむぐら)茂れる宿の寂しきに人こそ見えね秋は来にけり」(恵慶法師)とか、
ふつう句読点を施さないから、係り結びの発見は注意を要する。
この二つの和歌の係り結びの結びを指摘できるだろうか?
⇒ぞ――住む(連体形) こそ――見えね(已然形)
【文中の係り結び】
〇つぎも、『源氏物語』桐壺の巻からで、さきに引用した一文のまた少し前の文である。
朝夕の宮仕へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふつもりにやありけん、い
とあつしくなりゆき、もの心細げに里がちなるを、いよいよあかずあはれなるものに思
ほして、人のそしりをもえ憚(はばか)らせたまはず、世の例になりぬべき御もてなしなり。
(『源氏物語』桐壺の巻)
(朝夕の宮仕えにつけても、他人の心を悩ますばかりいて、恨みを背負う蓄積のせいであったろうか、まことに病気が重くなってゆき、いかにも心細いようすで里下がりが多くなるのを、帝はいよいよたまらなくいとしいものにお思いになり、人の非難をも気がねなさることができず、世の中の話題にもなってしまいそうなご寵愛ぶりである。)
※これの途中に、「恨みを負ふつもりにやありけん」とあって、「けん」は終止形・連体形とも同形だが、これは連体形であろうから、「係り結びの法則」が成りたっている。
で、一文がこれで終わるかというと、句点でなく、読点が来て、下へ続いている。
一種の挿入句になっている。これも係り結びの一用法である。
「こそ」のような強い調子の係助詞の場合は、「……であるけれども」と、逆接するような感じで、文が係り結びの成りたったあとも、続くような勢いを示すことがある。
桐壺更衣の死後のことであるが、
さまあしき御もてなしゆゑこそ、すべなうそねみたまひしか、人がらのあはれに、情
けありし御心を、上の女房なども恋ひしのびあへり。
(見苦しいほどの帝のご寵愛ぶりのためにこそ、つめたくお嫉(ねた)みなさったのだが、人柄が優しく、情愛の深かったお心を、上宮仕えの女房たちも思い出しては恋しく思いあった。)
※この「しか」(「き」の已然形)は逆接するような感じである。
このようなときは、係り結びのあと、句点でなく、読点で下に文が続いているもの、と理解されている。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、38頁~43頁、213頁)
謙譲表現のまとめ
〇16 謙譲表現のまとめ
・謙譲表現をあらわす語は、①名詞、②接頭語、③動詞、④補助動詞(動詞の一種)がある。
謙譲の補助動詞には、「たてまつる」「まうす」「きこゆ」「まつる」および重要な下二段活用の「たまふ」がある。「す」「さす」をともなったいっそう謙譲度の高い「きこえさす」「まゐらす」という言いまわしもある。
・下二段活用の「たまふ」
会話主の明確な謙譲の気持ちをあらわす補助動詞の「たまふ」(下二段)がある。
『竹取物語』には見えないが、『源氏物語』などにはたくさん出てくる。
・『源氏物語』桐壺の巻から見てゆくと、
いとかく思ひたまへましかば。<未然形の例>
(ほんとに、もし、こう考えさせていただいてもよかったのなら。)
死んでゆく桐壺更衣のさいごの言葉
・もの思うたまへ知らぬ心地にも、げにこそいと忍びがたうはべりけれ。<連用形の例>
(物の心を理解させていただく方法も知らないわたくしの心地にも、まことにもっていたく堪えがたいことでございますことでした。)
帝のお使いがやってきた、靫負命婦の言葉。
・うちうちに、思ひたまふるさまを奏したまへ。<連体形の例>
(内々に、案じてさしあげておりますさまを、ご奏上くださいませ。)
お答えする母君の返事。若宮(のちの光源氏)のゆくすえを案じて、あれこれ思うことを謙譲した言いかた。
・随分によろしきも多かりと見たまふれど、そも、まことにその方を取り出でん選びに、
かならず漏るまじきはいとかたしや。<已然形の例>
(それ相応に上手にこなす女性も多くいると存じあげますけれども、さて、ほんとうに才能のすぐれた方面の人を取り出そうと選ぶと、絶対に選に漏れないというのは、非常にすくないよ。)
「帚木」の巻で頭中将が、才能の真にすぐれた女の少ないことをなげく言葉。
※以上のように、「たまふ」は会話文の中に出て、「思ふ」とか「見る」(あるいは「聞く」)という語について、明確な謙譲をあらわしている。
※会話文にほとんど出てくるので、この「たまふ」を丁寧語と見る見かたが当然ある。
まれに地の文に出てくることもある。
終止形「たまふ」は『かげろふ日記』『和泉式部日記』『源氏物語』に散見するようだが、数が少ないので、終止形の存在を認めない人もいる。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、84頁~87頁、218頁)
係助詞とその周辺(1) ――ぞ・こそ・なむ
〇28 係助詞とその周辺(1) ――ぞ・こそ・なむ
・係助詞は、荷作りのひものように、一文一文の全体にかかるようにして、きゅっきゅっとしごいて結ぶ感じのものである。
・「なむ」は係助詞として文中に使われ、文末を活用する語の連体形で結ぶ。
係助詞の「なむ」が文末に来ることもある。
よく問題になるのは、係助詞の「なむ」が文末に来た場合と、終助詞の「なむ」と、助動詞が二つ結合してできた「なむ」と、三種類の「なむ」があることであるが、識別はそんなに困難なことではない。
①係助詞の「なむ」
目も見えはべらぬに、かくかしこき仰せごとを光にてなん、とて見たまふ。(『源氏物語』桐壺の巻)
(目も見えないのでございますが、このようにおそれおおいお言葉を光にして……、とてご覧になる。)
※文中のようにみえるが、「なん」で切れて文末を省略しているもの。
②終助詞の「なむ」。動詞などの活用語の未然形につく。
いつしか梅咲かなむ、来む、とありしを、さやある、と目をかけて待ちわたるに、花も
みな咲きぬれど、音もせず。(『更級日記』梅の立枝)
(早く梅が咲いてほしい、「梅が咲いたら行くよ。」という約束だったから、そうだろうか、と、梅に目をかけてずっと待っていると、花もみな咲いていったのに、便りもない。)
※終助詞の「なむ」は、梅に「咲いてほしい」と願望する気持ちをあらわす。係助詞の「なむ」とは別の語である。
③完了の助動詞「ぬ」と推量の助動詞「なむ」との結合が「なむ」になる。
もとの御かたちとなりたまひね。それを見てだに帰りなむ。(『竹取物語』御門の求婚)
(もとの御姿になっておくれ。せめてそれだけでも見て帰った、ということにしよう。)
④他に、ナ変活用の動詞が「死なむ」「往(い)なむ」となるので、注意すること。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、136頁~139頁)
係助詞とその周辺(2) ――や・か・は・も
〇29係助詞とその周辺(2) ――や・か・は・も
●「や」は、係助詞にもなれば、間投助詞にもなれば、並立助詞にもなる。
間投助詞の場合、文中にも文末にもあらわれ、疑問や反語の意味を持たない「や」が間投助詞。
あな恐ろしや。春宮(とうぐう)の女御のいとさがなくて、桐壺更衣の、あらはにはかなくもてなされにし例(ためし)もゆゆしう。(『源氏物語』桐壺の巻)
(ああ恐ろしいこと。東宮の女御(皇太子の母親である女御のこと)がじつに意地悪で、
桐壺更衣が、露骨にいたぶられ、死に至らされた前例も忌まわしく……。)
※ちなみに、「古池や蛙飛び込む水の音」(芭蕉)などの「や」も間投助詞である。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、140頁~142頁)
終助詞、間投助詞、並立助詞
〇30 終助詞、間投助詞、並立助詞
・終助詞は文末にあって、禁止・願望・詠嘆・強意などをあらわす。
間投助詞は文中あるいは文末にあって、語勢を強めたり、感動をあらわしたりする。
並立助詞は語句と語句とを並立させるものである。
・間投助詞は、「や」「よ」「を」が代表的なものである。
「を」は文中にも、文末にもあらわれ、感動を示す。
さりとも、あこはわが子にてをあれよ。(『源氏物語』帚木の巻)
(それにしても、おまえはわたしの子で、まあ、いなさいよ。)
必ず、雨風やまば、この浦にを寄せよ。(『源氏物語』明石の巻)
(きっと、雨風が止んだら、須磨の浦に、まあ、舟を寄せよ。)
※古文に出てくる「を」は、格助詞や接続助詞の「を」が大部分で、間投助詞の「を」はきわめて珍しいものである。
(藤井貞和『古文の読みかた』岩波ジュニア新書、1984年[2015年版]、144頁、148頁~149頁)












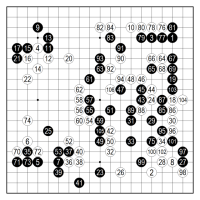
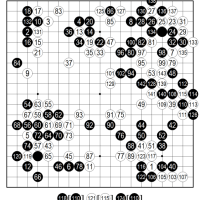
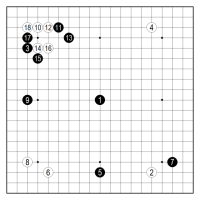
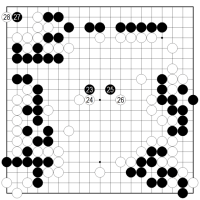
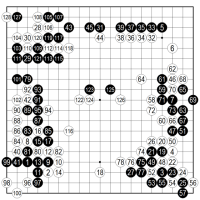
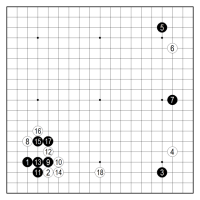
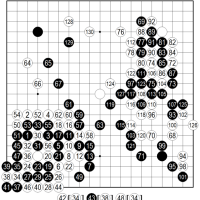
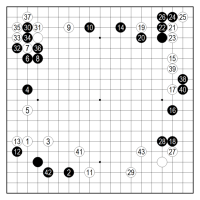
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます