
中学生の頃は星新一らのSF小説に夢中になったものですが、その後はしばらく遠ざかっていました。久しぶりに手に取ったSFが神林長平の長編「魂の駆動体」(ハヤカワ文庫)です。日経ビジネスオンラインに掲載されていたあるコラムがこの作品に言及していたのを見て関心を持ち、アマゾンで取り寄せて読んでみました。
この小説は近未来の前半と、人類が滅んだ後の遠い未来の後半から構成されています。
前半は、人類は肉体を捨てて意識のみ存続させる装置を開発、永遠の命を得ようとしている時代です。この時代ではクルマというものは事故の危険性を回避するため公道での運転は禁止され、移動したい人は無人運転されているクルマを呼び止め、行き先まで運転することもなく無人運転に身を委ねることがルールになっています。
肉体を捨てて意識のみの存在になることを拒絶する老人が、ある日朽ち果てたクルマを発見し、かつて夢中になっていたクルマを自らの手で作ろうと決心し、元エンジニアの老人と共に理想のクルマを開発しようと設計図を書き始める、というのが前半のおおよそのあらすじです。
後半は、鳥のように翼を持ち自由に飛翔することができる翼人たちが地球を支配する時代が舞台です。翼人たちは滅亡した人類の文化に関心を持ち、遺跡で発見した設計図をもとにクルマを作ろうとするのですが。。。というあらすじで、前半との関係が終盤に明らかになります。
この作品では、クルマというものは人間にとって単なる移動手段ではなく、「身体を運ぶと同時に、魂をも駆り立て、駆動するもの」として捉えられています。私はクルマは運転しませんが、人間にとってクルマは特別な存在であることは理解できます。でなければここまでクルマというものが進化し多様な商品を生み出すには至らなかったと思います。
ちなみに作者は工業高専卒業なので、自動車部品や技術について具体的かつ詳しく描写されています。他の作品でもメカの描写が詳しく、その点でもSFファンたちから高い評価を得ているそうです。私は少々ストーリーが冗長であるようにも感じたのですが、この作品はクルマ好きな人は非常に共感を持って読むことができるでしょう。
この小説は近未来の前半と、人類が滅んだ後の遠い未来の後半から構成されています。
前半は、人類は肉体を捨てて意識のみ存続させる装置を開発、永遠の命を得ようとしている時代です。この時代ではクルマというものは事故の危険性を回避するため公道での運転は禁止され、移動したい人は無人運転されているクルマを呼び止め、行き先まで運転することもなく無人運転に身を委ねることがルールになっています。
肉体を捨てて意識のみの存在になることを拒絶する老人が、ある日朽ち果てたクルマを発見し、かつて夢中になっていたクルマを自らの手で作ろうと決心し、元エンジニアの老人と共に理想のクルマを開発しようと設計図を書き始める、というのが前半のおおよそのあらすじです。
後半は、鳥のように翼を持ち自由に飛翔することができる翼人たちが地球を支配する時代が舞台です。翼人たちは滅亡した人類の文化に関心を持ち、遺跡で発見した設計図をもとにクルマを作ろうとするのですが。。。というあらすじで、前半との関係が終盤に明らかになります。
この作品では、クルマというものは人間にとって単なる移動手段ではなく、「身体を運ぶと同時に、魂をも駆り立て、駆動するもの」として捉えられています。私はクルマは運転しませんが、人間にとってクルマは特別な存在であることは理解できます。でなければここまでクルマというものが進化し多様な商品を生み出すには至らなかったと思います。
ちなみに作者は工業高専卒業なので、自動車部品や技術について具体的かつ詳しく描写されています。他の作品でもメカの描写が詳しく、その点でもSFファンたちから高い評価を得ているそうです。私は少々ストーリーが冗長であるようにも感じたのですが、この作品はクルマ好きな人は非常に共感を持って読むことができるでしょう。












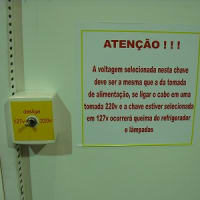







しかし、レクサスは技術的にはもっと静かな走行を実現できるのに、心地よいエンジン音にこだわるドライバーのためにわざとトヨタは車内の静粛性を落としているという話をどこかで読んだことがあります。
電気自動車が普及すると、オプションでわざとガソリンエンジンやディーゼルエンジンの合成音をつけるドライバーも出てくるかもしれませんね。