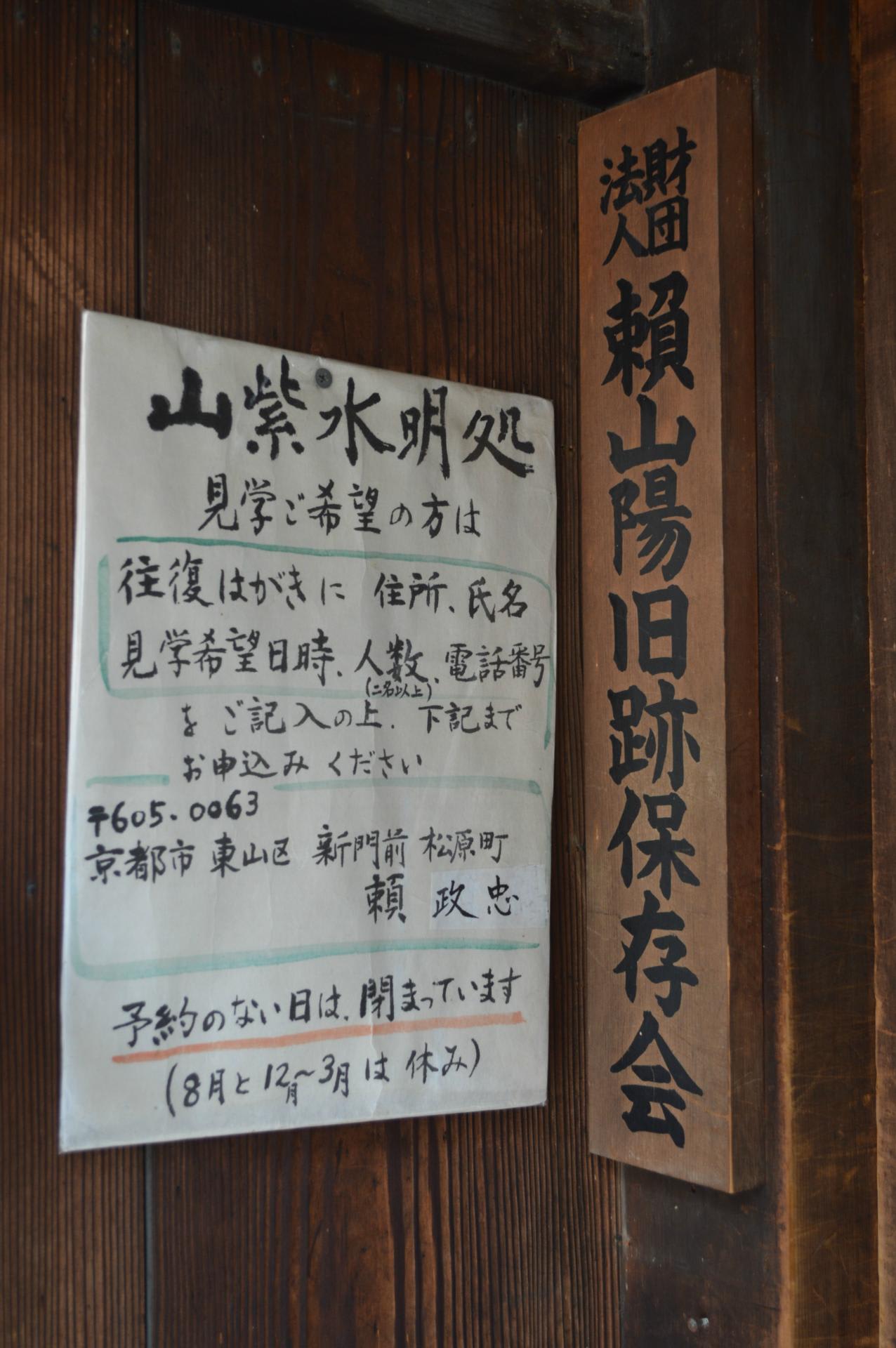周防国出身の大村益次郎(村田蔵六,1825~69)は,
緒方洪庵等に医・蘭学を学んだ後,江戸に出て幕府の講武所教授等を歴任した。
のち長州藩に仕え軍制改革を指導した。
農民や町人の兵式訓練の必要を説き,
第2次長州征伐・戊辰戦争において卓越した指揮を行った。
新政府では兵部大輔として近代兵制の樹立に尽力したが,
明治2(1869)年9月4日関西の軍事施設視察時に反対派浪士に襲われ,
11月5日大阪で没した。
この石標は,大村が襲撃された宿所の跡を示すものである。
なお碑文には「十番路次」と記すが,
当時の史料や大村の伝記には「二番路次」と記している。

大正拾五年四月 陸軍少将山口鹿太郎建之

関連記事 ➡ 遭難碑