
2024年の画像から。
アサマイチモンジ。
涸沼周辺で撮影。

矢印の紋が、列の中心付近にきます。

こちらは2017年に撮影したイチモンジチョウ。
小さな白い紋(後縁から4番目)が、中心より外側にずれています。

RDB:
絶滅危惧ⅠA類:東京都
絶滅危惧Ⅱ類:千葉県、神奈川県
準絶滅危惧種:埼玉県、島根県
分類:
チョウ目アゲハチョウ上科タテハチョウ科タテハチョウ亜科
翅を広げた長さ:
45~61mm
前翅の長さ:
24~38mm
分布:
本州
平地~山地
成虫の見られる時期:
5~10月(年1~4化)
※茨城県内:山地6~9月・年2化、平地5~10月・年3化
幼虫で冬越し
エサ:
幼虫・・・スイカズラ、キンギンボク、タニウツギ、ヤブウツギ、ニシウツギ、ハコネウツギ、ツキヌキニンドウ、クロミノウグイスカグラ、ウグイスカグラなど
成虫・・・ウツギ、ヒメジョオン、ノイバラ、シシウド、トリアシショウマ、ミヤマイボタ、イボタノキ、ノリウツギ、チダケサシ、ウド、クリ、イタドリ、リョウブ、スイカズラ、ソバなどの花の蜜
♂は湿地で給水することがあるが、汚物や腐果に来ることは稀。
その他:
翅表は黒褐色の地色で、前・後翅にかけて縦の白色点紋列がある。
前翅の白色紋列の中央付近の白色紋が小さくならず、中心からずれない。
(イチモンジチョウは小さくなり、外側にずれる。)
前翅の白色紋列の後縁寄りの二つが、内側にずれる。
(イチモンジチョウでは後縁寄り三つがほぼ揃う。)
前翅表中室の白紋は明瞭。
(イチモンジチョウでは不明瞭。)
後翅裏面の白帯の翅脈は白くない。
(イチモンジチョウは白い。)
♀はやや大きく、翅形が丸みを帯び、白紋が発達する。
タテハチョウ科では唯一の日本特産種で、本州(青森~山口)のみに分布する。
本州中部における垂直分布は0~1000mで、高山帯には分布しない。
イチモンジチョウとの混生地では1週間ほど羽化が早い。
滑空して緩やかに飛び、すぐに下草や地上に、翅を広げて止まる。
山地の渓流沿いの林や平地の河川敷林の明るい林縁に生息。
イチモンジチョウと比べて分布ははるかに局地的。
食草スイカズラの分布に強く抑制される傾向が見られる。
卵は風の当たらない孤立したスイカズラに多い。
葉表先端または葉縁に1個ずつ産付する。
卵色は黄白色。
(イチモンジチョウは灰色。)
幼虫はほぼ1年じゅう見られる。
幼虫は葉表で生活し、葉の中脈を残して食べる。
1齢期は葉に切れ込みを入れるように食べ、中脈の先端に葉の小片と自分の糞を積み上げて、3~5mmの塔を作る。
糞は直接塔の先に排出される。
虫体にも糞が付着し、糞を綴って、隠れ場所あるいは自分の替え玉を作る。
3齢幼虫は、食草の基部を中脈から内側に巻いて巣を作り、その中に潜んで越冬する。
終齢幼虫の体長は約27~35mm。
頭部は褐色、胴部は緑色。
各節の背面に、刺のついた突起が一対ずつある。
本種の幼虫はイチモンジチョウの幼虫よりも突起が長い。
一番後ろの突起よりその前の突起の方が長い。
(イチモンジチョウでは同じ長さ。)
体側に黄白色の筋が走る。
蔓や葉裏などで垂蛹となる。
参考:
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)
学研の図鑑LIVEポケット幼虫(学研プラス)
学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)
検索入門チョウ①(保育社)
原色日本昆虫生態図鑑Ⅲチョウ編(保育社)
かたつむりの自然観撮記
日本のレッドデータ検索システム
虫ナビ
昆虫エクスプローラ
芋活.com
アサマイチモンジ。
涸沼周辺で撮影。

矢印の紋が、列の中心付近にきます。

こちらは2017年に撮影したイチモンジチョウ。
小さな白い紋(後縁から4番目)が、中心より外側にずれています。

RDB:
絶滅危惧ⅠA類:東京都
絶滅危惧Ⅱ類:千葉県、神奈川県
準絶滅危惧種:埼玉県、島根県
分類:
チョウ目アゲハチョウ上科タテハチョウ科タテハチョウ亜科
翅を広げた長さ:
45~61mm
前翅の長さ:
24~38mm
分布:
本州
平地~山地
成虫の見られる時期:
5~10月(年1~4化)
※茨城県内:山地6~9月・年2化、平地5~10月・年3化
幼虫で冬越し
エサ:
幼虫・・・スイカズラ、キンギンボク、タニウツギ、ヤブウツギ、ニシウツギ、ハコネウツギ、ツキヌキニンドウ、クロミノウグイスカグラ、ウグイスカグラなど
成虫・・・ウツギ、ヒメジョオン、ノイバラ、シシウド、トリアシショウマ、ミヤマイボタ、イボタノキ、ノリウツギ、チダケサシ、ウド、クリ、イタドリ、リョウブ、スイカズラ、ソバなどの花の蜜
♂は湿地で給水することがあるが、汚物や腐果に来ることは稀。
その他:
翅表は黒褐色の地色で、前・後翅にかけて縦の白色点紋列がある。
前翅の白色紋列の中央付近の白色紋が小さくならず、中心からずれない。
(イチモンジチョウは小さくなり、外側にずれる。)
前翅の白色紋列の後縁寄りの二つが、内側にずれる。
(イチモンジチョウでは後縁寄り三つがほぼ揃う。)
前翅表中室の白紋は明瞭。
(イチモンジチョウでは不明瞭。)
後翅裏面の白帯の翅脈は白くない。
(イチモンジチョウは白い。)
♀はやや大きく、翅形が丸みを帯び、白紋が発達する。
タテハチョウ科では唯一の日本特産種で、本州(青森~山口)のみに分布する。
本州中部における垂直分布は0~1000mで、高山帯には分布しない。
イチモンジチョウとの混生地では1週間ほど羽化が早い。
滑空して緩やかに飛び、すぐに下草や地上に、翅を広げて止まる。
山地の渓流沿いの林や平地の河川敷林の明るい林縁に生息。
イチモンジチョウと比べて分布ははるかに局地的。
食草スイカズラの分布に強く抑制される傾向が見られる。
卵は風の当たらない孤立したスイカズラに多い。
葉表先端または葉縁に1個ずつ産付する。
卵色は黄白色。
(イチモンジチョウは灰色。)
幼虫はほぼ1年じゅう見られる。
幼虫は葉表で生活し、葉の中脈を残して食べる。
1齢期は葉に切れ込みを入れるように食べ、中脈の先端に葉の小片と自分の糞を積み上げて、3~5mmの塔を作る。
糞は直接塔の先に排出される。
虫体にも糞が付着し、糞を綴って、隠れ場所あるいは自分の替え玉を作る。
3齢幼虫は、食草の基部を中脈から内側に巻いて巣を作り、その中に潜んで越冬する。
終齢幼虫の体長は約27~35mm。
頭部は褐色、胴部は緑色。
各節の背面に、刺のついた突起が一対ずつある。
本種の幼虫はイチモンジチョウの幼虫よりも突起が長い。
一番後ろの突起よりその前の突起の方が長い。
(イチモンジチョウでは同じ長さ。)
体側に黄白色の筋が走る。
蔓や葉裏などで垂蛹となる。
参考:
茨城の昆虫生態図鑑(メイツ出版)
ポケット図鑑日本の昆虫1400①(文一総合出版)
学研の図鑑LIVEポケット幼虫(学研プラス)
学研の図鑑LIVE新版昆虫(学研プラス)
検索入門チョウ①(保育社)
原色日本昆虫生態図鑑Ⅲチョウ編(保育社)
かたつむりの自然観撮記
日本のレッドデータ検索システム
虫ナビ
昆虫エクスプローラ
芋活.com










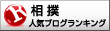
















なかなか出会う機会のない蝶だと思います。
数少ないチャンスを生かして素晴らしい!