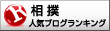マダラガガンボのメス。
日本産ガガンボ中、最大級。
こっちはオス。
両者の違いは・・・
腹端の形。
メスは先が尖る。
オスは尖らない。
※マダラガガンボとしましたが、極めてそっくりな近縁種がおり、オスの第9腹節の突起の有無などを確認せねばなりません。
この画像で判定することは出来ないため、同定間違いの可能性もあります。
分類:ハエ目 長角亜目ガガンボ科
体長:28~38mm(最大で50m . . . 本文を読む
ヒメセアカケバエ。
複眼が小さいのでメス、ですね。
春には良く観る虫なんですが。
秋に観るのは初めてですね。
分類:ハエ目トゲナシケバエ科
体長:8.5~11mm
分布:北海道、本州、四国、九州
平地~山地
成虫の見られる時期:3~6、9~10月
幼虫で冬越し?
エサ:成虫・・・花の蜜、腐った果実など
幼虫・・・腐食物
その他:通常、春に発生するが、秋に発生するこ . . . 本文を読む
ミナミヒメヒラタアブのメス。
腹の先が複雑な模様になっていますね。
分類:ハエ目ハナアブ科ヒラタアブ亜科
体長:8~9mm
分布:本州、四国、九州
平地~丘陵
成虫の見られる時期:4~10月
成虫で冬越し
エサ:成虫・・・花の蜜や花粉
幼虫・・・アブラムシ
その他:胸部はメタリックな暗い銅色で、縦条がある。
胸部の周囲は黄色く縁どられる。
オスの腹 . . . 本文を読む
ナガハリバエの一種のオス?
コンボウナガハリバエのような、そうでないような?
ネット上では、コンボウナガハリバエ以外は全部、「ナガハリバエの一種」としているようなので、右へ倣い(笑)
複眼が接近しているので、オスと判断しました。
脚が長いです!
腹の各節には、白い粉で覆われた部分があります。
腹に生えた剛毛が、ハリバエの一種と主張しています。
ハリバエの仲間なら、何某かの昆虫に寄生すると思われ . . . 本文を読む
ホシメハナアブのメス。
複眼に星を散りばめたような模様。
背中には細い五本の縦条。
腹には3対の横帯。
分類:ハエ目ハナアブ科ハナアブ亜科
体長:11~13mm
分布:北海道、本州、四国、九州
平地~丘陵
成虫の見られる時期:4~11月(年1化、新成虫は9月~)
成虫で冬越し
エサ:成虫・・・花の蜜、腐敗物
幼虫・・・水中の腐植質
その他:複眼に星を散りばめた模様 . . . 本文を読む
ミスジミバエ(シマミバエ)。
胸に三本の黄色い縦筋があるのが特徴。
複眼は赤いが、光の反射によって緑色に見える。
翅の前縁、翅の先の一部、支脈の一部が黒い。
別名:シマミバエ
分類:ハエ目ミバエ科ミバエ亜科
体長:10~12mm
分布:本州、四国、九州
平地~低山
成虫の見られる時期:3~10月
成虫で冬越し
エサ:成虫・・・腐った果実、昆虫の排泄物
幼虫・・ . . . 本文を読む
ハエ目イエバエ科ハナレメイエバエ亜科の一種?
眼が緑色で、オレンジ色に反射するのがキレイで撮ったのですが。
写真が不鮮明で満足な同定が難しい上、KONASUKEの技量、資料ともに少なく。
ハナレメイエバエ亜科の一種と思われますが、違っているかも知れません。
ハナレメイエバエ亜科は、小昆虫などを食べるようです。
. . . 本文を読む
ブランコヤドリバエ。
蛹達を入れておいたケース内に発生しました。
ガァ~ン!(泣)
多分、以前、拾ってきたカシワマイマイの蛹の中にいたと思われます。
マイマイガ類の幼虫を「ブランコケムシ」と呼ぶんですが。
若齢幼虫が、糸でぶら下がる様子から名づけられました。
このハエは、それに寄生するということで、「ブランコヤドリバエ」。
まぁね、昆虫を飼っていれば、必ず遭遇する場面ですよ。
こうやって寄生 . . . 本文を読む
ミドリバエ。
胸が緑色のハエ。
翅は黒褐色で、わずかに透けるようだ。
複眼の間が空いているので、メス。
成虫は花の蜜をなめる。
幼虫の生態は不明。
まだ見つかっていないという話も。
分類:ハエ目クロバエ科ツマグロキンバエ亜科
体長:約9mm
分布:本州、四国、九州
平地~山地?(どちらかというと山地性?)
成虫の見られる時期:5~9月
成虫で冬越し?
エサ:成虫・・ . . . 本文を読む
コウカアブ。
分類:ハエ目ミズアブ科
体長:13~28mm
分布:全国
平地~山地
成虫の見られる時期:5~10月
越冬形態?
エサ:成虫・・・糞?
幼虫・・・腐敗した有機物
その他:成虫はゴミ捨て場や畜舎などに多い。
参考:ポケット図鑑日本の昆虫1400②(文一総合出版)
虫ナビ
. . . 本文を読む
マダラガガンボ類の交尾。
資料が少ないので、ちょっと同定に自信が持てません。
翅の模様が違うのは、個体変異の範囲内なのか、そうでないのかの判断がつきません。
ハエ目ガガンボ科。
. . . 本文を読む
キイロホソガガンボの交尾。
分類:ハエ目ガガンボ科
体長:12~14mm
分布:日本全国
垂直分布?
成虫の見られる時期:5~10月
越冬形態?
エサ:成虫・・・花の蜜
幼虫・・・植物の根
その他:胸の背面に、黒い3本の筋がある。
触角の基部の1・2節が黄色、その先が黒褐色。
腹部各背板に黒斑がある。
類似種のエゾホソガガンボでは、腹部第8 . . . 本文を読む
カビのハエたハエがたくさん?
こんな風に、カビがハエたハエは時々、見かけるけど。
ハエカビの仕業らしい。
ハエカビはハエを殺してしまい、気門(昆虫が息をする穴)から出てくるという。
ハエの腹が白くなっているのは、外に出てきたハエカビ、ってことだな。
しかし、こんな風に、一本の植物(ここではナズナ)に沢山のハエが付いているのは初めて観た。
どういう仕組みで、こうなるのだろう?
ハエカビは胞 . . . 本文を読む
ヒラタアブの仲間の幼虫。
移動の仕方を知りたかったので、連続写真にしてみました。
まずは体を目いっぱい伸ばして
お尻を持ち上げ、前に出す
それを体の前へと
伝えて行く
そして頭を前の方に伸ばして
再び後ろから
前へと
伝えて行く。
動画だとかえって、どうなってるのか分からないかもね。
ハエ目ハナアブ科ヒラタアブ亜科。
. . . 本文を読む
セアカキノコバエ。
居るのはニワトコの木。
たくさんアブラムシがいるところに
群れています。
何かを舐めている様子。
どうやら、アブラムシが排出した甘露を舐めているようです。
角状管から、直飲み?
ところで、写真を整理していて気付いたんですが。
メスばっかりの気が。
オスは腹が全面黒い。
これは、今年、確かめてみなければ。
別名:セアカクロバネキノコバエ
分類:ハエ目クロバネキノコバ . . . 本文を読む