
茶臼山山頂では新緑の森林浴を楽しみながら、姉川の合戦場を見下ろすビューポイントを堪能頂いた後、稲の苗が植えられた田園風景に溶け込んだ史跡を巡るウォーキングを堪能いただけます。
 平成25年6月29日(土)8:30~
平成25年6月29日(土)8:30~ 北郷里公民館 滋賀県長浜市東上坂町976-7
北郷里公民館 滋賀県長浜市東上坂町976-7
- [自動車]北陸自動車道長浜ICから車で5分
- [駐車場]有


 龍ヶ崎砦(茶臼山古墳群)遠景
龍ヶ崎砦(茶臼山古墳群)遠景  横山城遠景
横山城遠景


 遠藤直経の戦場墓碑:元亀元年、遠藤直経は姉川の合戦で岩手城主竹中重治の弟重矩に討たれた。
遠藤直経の戦場墓碑:元亀元年、遠藤直経は姉川の合戦で岩手城主竹中重治の弟重矩に討たれた。






⑥龍ヶ鼻の砦郡
 [地図をみる]
[地図をみる]
この背後の山である龍ヶ鼻は、姉川合戦の直前に、織田信長や徳川家康が本陣を敷いた砦跡です。元亀元年(1570)6月19日、浅井長政を攻めるため、織田信長は大軍を率いて近江に入りました。21日から浅井氏の居城小谷城を攻めましたが、その構えが固いとみるや、わずか1日の攻撃で兵を返しました。
24日にはこの龍ヶ鼻に陣を移し、徳川家康もそこへ合流して、南方の横山城の攻撃を行います。信長や家康の陣跡は、ここから東へ約300メートル程登った龍ヶ鼻砦跡(標高187メートル)や、そこへの途中、茶臼山(ちゃうすやま)古墳(滋賀県指定史跡、前方後円墳)の後円部にあたる龍ヶ鼻陣所付近にあったと見られます。
合戦の当日にあたる28日未明、浅井・朝倉軍が姉川北岸に前進したのを見て、織田信長は「陣杭の柳」に、徳川家康は「岡山」に、それぞれ本陣を移し合戦が行われました。



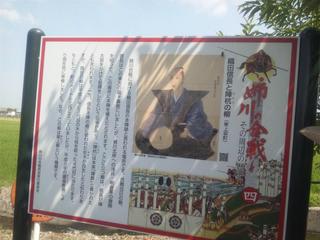





この背後の山は、元来「岡山」といいましたが、姉川合戦の時に徳川家康が陣を敷き、戦いに勝ったことに因んで「勝山(かつやま)」と呼ばれるようになったとされます。
徳川家康軍は激戦の末に朝倉軍を敗走させ、それにより劣勢の織田軍も盛り返し、勝利を得たと伝えられています。江戸時代以来「流岡(ながれおか)神社」が鎮座していましたが、明治41年に上坂神社(東上坂町)に合祀されました。
この「流岡神社」には織田信長が勝利祈願をしたとの社伝があり、境内の大杉の上部が枯れているのは、合戦の折、両軍の矢が飛びかって枝を折ったためと伝えられています。一方、上坂神社には織田信長が寄進した金燈籠(かなどうろう)が現存しています。



上坂氏館
戦国時代に京極氏・浅井氏の家臣であった上坂(こうさか)氏の館跡です。上坂氏は、室町時代から北近江の守護であった京極氏の有力家臣で、戦国時代には上坂家信・信光が出て、京極氏執権として湖北統治の実権を握りました。さらに、伊賀守意信(おきのぶ)は浅井氏に仕え、天正元年(1573)の浅井氏滅亡後は、その子正信が秀吉の弟・羽柴秀長の家臣として各地を転戦しています。
関ヶ原合戦の際、西軍となり敗れたことで帰農、正信は父意信の弟信濃守貞信から屋敷跡を受け取っています。上坂氏は中世以来江戸時代に至るまで、姉川から取水し北郷里地区を灌漑する「郷里井(ごうりゆ)」の管理者として知られ、姉川上流や北岸の村々との争いに際しては、その代表者として臨みました。
館跡は土塁と堀に囲まれた複数の城館からなり、今も「いがんど」(伊賀守屋敷)や「しなんど」(信濃守屋敷)の地名や土塁の一部を残しています。また、江戸時代の絵図(「上坂家文書」)にみえる「丸之内」の跡が、この児童遊園に当たります。

























今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。



















