
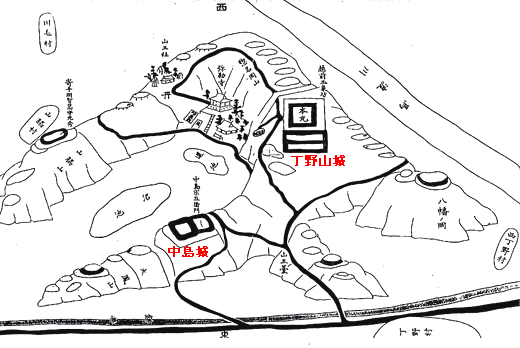 滋賀県城郭分布調査より『東浅井郡志』(丁野山古砦図)を転載
滋賀県城郭分布調査より『東浅井郡志』(丁野山古砦図)を転載
お城のデータ
住所地:長浜市(旧・東浅井郡湖北町)小谷丁野町 map:http://yahoo.jp/bbxo8l
区 分:山城
現 状:山林
築城期:織豊期
築城者:浅井備前守亮政
標 高:170m 比高:60m
遺 構:曲廓・土塁・堀・堀切・竪堀・説明板
駐車場:駐車場(日本硝子独身寮の)に!
訪城日:2016.2.20
お城の概要
丁野は小谷城浅井氏の発祥の地と言われています。丁野山城も永正十五年(1518年)に浅井備前守亮政によって築城とされます。天正元年(1573年)の織田信長の小谷城攻略時に、ここには浅井氏を加勢に来た越前朝倉氏が立て籠もりましたが、織田勢に攻められ落城しました。 <現地案内板より>
この山は低い山で丁野山城まででも比高は60m程度。5分で尾根の鞍部に出て、右側のピークが中島城(80m先)、左のピークが丁野山城(330m先)です。 ここは2006年大河ドラマの功名ケ辻のおかげで、二つの城跡ともに周囲の木々が伐採され、大変見学しやすくなっています。おまけに時期的に下草も無くなおいい感じでした。城址は岡山山頂にあり、大嶽城を小型にした印象です。主郭は20m四方ほどで主郭周囲に 堀が巡り、南北双方に副郭のピークとその先に堀切、それに続く竪堀がある。
丁野山城は主曲輪を中心として南側と北側に袖曲輪といった連郭式の曲輪配置で、主曲輪は約30m×25mで曲輪の周囲は横堀を巡らし、南側尾根と北側尾根には堀切を配している。
北側の曲輪からは北国脇往還道を挟んで小谷山は目前で、小谷城の支城として築城されたことが容易に推定できる。
 丁野から、丁野城を見上げる
丁野から、丁野城を見上げる




























お城の歴史
丁野山城は永正15年に浅井亮政が小谷城の西、北国脇往還道を挟んだ岡山の山頂付近に築いた城で、天正元年(1573)には浅井長政が岡山の東尾根に中島城を築き、丁野山城の支城とした。
信長公記 巻六 元亀四年
12、追撃 大筒・丁野攻破らるるの事
信長公に通じた浅見対馬は、8月12日みずからが守る大嶽下の焼尾へ信長公の人数を引き入れた。その夜はことのほか風雨が激しかったが、信長公は虎御前山の本陣に嫡男信忠殿を残し、みずから馬廻を率いて大雨の中をずぶ濡れになりながら大嶽へ攻め上がった。大嶽には斎藤・小林・西方院らの越前衆五百ばかりが番手として籠っていたが、信長公直々の攻撃の前にたまらず降伏した。
降伏した越前兵は、すべて討ち果たされて当然のところであった。しかし夜の闇に加えて折からの風雨が敵方の視界をさえぎり、当の朝倉義景がこの大嶽陥落を気付いていないおそれがあった。そこで信長公は降兵たちの命を助けて朝倉本陣へ向かわせ、彼らに大嶽が落去してもはや戦勢を支えがたくなった事実を知らせさせた。このとき信長公は、このまま一挙に朝倉義景の陣所を抜く考えを固めていた。
信長公は大嶽に塚本小大膳・不破光治・同直光・丸毛長照・同兼利らを置くと、すぐさま丁野山(湖北町小谷丁野)の攻撃にかかった。ここには越前平泉寺の玉泉坊が籠っていたが、これもまたたく間に降伏して退散した。
大嶽・丁野の要害が落ちた今、信長公は朝倉勢が今夜のうちにも越前へ退却を始めると読んだ。そして先手の諸将へその旨を伝え、敵勢退却のときを逃さぬよう覚悟せよと再三にわたって命じた。しかしそれでも信長公は焦りと苛立ちを抑えきれず、13日夜ついにみずから先駈けをして越前衆陣所へ攻め入った。
このとき先手として越前勢に近く布陣していたのは、佐久間信盛・柴田勝家・滝川一益・蜂屋頼隆・羽柴秀吉・丹羽長秀・氏家直通・安藤守就・稲葉一鉄・稲葉貞通・稲葉典通・蒲生賢秀・蒲生氏郷・永原筑前・進藤山城守・永田刑部少輔・多賀新左衛門・弓徳左近・阿閉貞征・阿閉孫五郎・山岡景隆・山岡景宗・山岡景猶ら歴々の諸将であったが、信長公よりの度々の下命にもかかわらず油断しきっていた。そこへ信長公先駈けの報が伝わってきたため、彼らはあわててその後を追った。そして地蔵山①でようやく信長公に追いつき、神妙な顔で御前に並んだ。信長公は「数度も申し含めたにもかかわらず懈怠するとは、なんたる曲事か。この比興者どもめが」と彼らを激しく叱責した。
「朝倉始末記の越州軍記 義景地蔵山へ陣替之事」に丁野山の記述がある。
元亀四年八月十日ニ、「信長殿大ヅクノ城・丁野ノ城ヲ可被攻」ノ由ゾ聞ヘケル。依之、義景ヤナガセヨリ地蔵山ヘ着陣アリ。其時ノ大ヅクノ番手ノ衆ニハ、小林・斉藤民部丞巳下、纔ニ(わずかに)四、五百計ナリ。
丁野ノ城ノ番手ニハ平泉寺玉泉坊・宝光院以下是五百計ニ過ザリケリ」
朝倉義景が着陣した地蔵山というのは木之元地蔵(浄信寺)と推定され、丁野山に籠もっていた平泉寺玉泉坊とは福井県勝山市平泉寺の波多野玉泉坊である。
朝倉始末記の記述から、元亀4年当時、丁野山城には浅井氏を支援する朝倉氏の軍勢が立て籠もっていたことが判るが、朝倉氏の本城である一乗谷城、およびその周辺の城にも横堀は使われておらず、おそらくは天正11年の賤ヶ岳の戦いにおいて秀吉軍が北国脇往還道(現国道265号線)の監視、押さえのために、小谷山の支尾根の山崎丸、福寿丸と共にこの丁野山城を改修したものと考えられる。
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。
















 公民館前に
公民館前に











 副曲輪をみる
副曲輪をみる

















 駐車場(日本硝子独身寮の)に!
駐車場(日本硝子独身寮の)に!