
所在地:滋賀県東近江市山上町 map:http://yahoo.jp/FlqJ_p
遺 構:和南川が前堀カ、切岸、石材等
区 分:丘陵
築城者:小倉氏
築城期:室町期
目 標:山上小学校
訪城日:2013.4.23















山田城は、和南山から嘴状に突きだした支尾根の先端部を利用した城だ。 西と北側は急斜面で、西を流れる和南川と北を流れる愛知川が堀の役目を果たし、西側にある八幡神社から見ると比高もあり、築城に適した要害の地と云える。
現在は、山上小学校の旧敷地となっていて、城の遺構は何も残っていない。 八幡神社から小学校への登る「肥後坂」(旧小学校敷地東側)辺りが城跡の雰囲気を残していた。


歴史
山田城は、室町時代に山上城主小倉氏によって築かれた。 小倉氏は、小掠荘・柿御園荘に勢力をもっていたが、応仁の乱後に山上城を拠点とし、出城の山田城や八尾城を築い。
さくら -小倉殿の戦いー より 小牧山へ
中略(抜粋)
夜が明けても、鳥居平城周辺では合戦が続いていた。
翌日、なお長寸城と鳥居平城の間で激戦が繰り広げられていたが、その分、愛知川沿いは比較的安心で、お鍋の一行と共に高野へ向かった。
「ご夫君が右近大夫殿に従うとすれば、それは八尾城が、山田城と山上城に近すぎるためです。両城から攻められることを恐れてのこと。でも、山田城の左近助殿がご本家側になれば、ご夫君もご本家側になられるかもしれません」
左近助は和南山の戦いでは静観していた。本家側ではなかったが、右近大夫に加勢したわけでもない。
お鍋は納得したのだ。「先ず高野に帰って、ご夫君を説得するのです」「息子の命がかかっているのですもの。必ず説得します」 お鍋は強く頷いた。
「右京亮様は、八尾城でございます。山田城への攻撃のために──」
八尾城に着いた時にはすでに宵の口で、戦支度は万端整っている。これは攻撃を止めさせることは不可能ではないかと、第六感が語っていたが、焦りがそれを否定していく。
結局、翌日、右京亮は山田城を攻撃した。 右京亮に山田城を攻めさせたのは右近大夫だが、それには理由がある。
長寸城の本家側はしぶとく、鳥居平城に何度も仕掛けてきていた。そして、蒲生家がいつ参戦してくるかわからない。
右近大夫は確実に味方を確保しなければならなかった。鳥居平城を一旦諦めてでも。いつまで経っても態度をはっきりとさせない左近助を脅す目的で、山田城を攻撃させたのである。
まさしく右京亮が、山田城を攻撃しては誘ってきていた時分。 山田城が随分破壊された後であった。
**********************
翌日は突然の激戦となった。
永源寺が突然、高野に繰り出してきたのだ。 永源寺の僧兵を率いているのは、九居瀬城主の小倉行国。永源寺は六角家に深く帰依されているから、謀反人は許せないのである。 攻められたら、応戦するしかない。右京亮は永源寺の兵に当たる。
右近大夫は永源寺に攻めて行くと、焼き討ちを開始した。永源寺はびっくりし、慌てて高野館から引き上げると、消火に奔走。その後はなりをひそめてしまった。
右近大夫は勢いのまま、行き先を近くの相谷城に変更し、一気に押し寄せて行く。
相谷城の面々はろくに戦わずに敗走。残された城兵たちは降伏した。
その兵たちに、今度は九居瀬城を囲ませ、右近大夫の本隊はついに小倉城へ向かって行った。
右京亮が行く前に、右近大夫が小倉城攻撃を開始してしまうだろう。「とりあえず、八尾城に行こう」 いったん高野を捨て去って、八尾城で陣を立て直すことにした。
小倉城にはすでに、右近大夫が永源寺焼き討ち、相谷城を落とし、さらに九居瀬城への包囲などが伝わっている。
左近助は山田城を右京亮に攻められたために、兵をそちらにも多く割いていたため、小倉城はやや手薄気味である。
右近大夫についに取り囲まれたこと、そして、右京亮が永源寺と戦ったことなど、すでにお鍋の耳にも達している。右京亮が永源寺と戦になったのは、やむを得ない状況だったわけだが、そこは正確には伝わらないのが戦場だ。
「織田家家臣・滝川一益の手のものにござる。お助けに参りました」音もなくお鍋の傍らに寄った。(忍の者?)「主・滝川は甲賀の人なれば、ご存知やに存じまするが?」 しかし、今、織田家家臣と言ったような。
「相谷城の面々が敵に降伏、寝返って九居瀬城を包囲し──永源寺と戦った高野の面々は八尾城に籠もった──なるほど、右近大夫に囲まれても、この城に助けに来る軍勢は一つもないわけか。仕方ない……」 左近助は覚悟を決めたらしい。
ついに開戦となり。しばらくして小倉城は落城寸前にまで追い込まれる。城主・左近助の命は風前の灯火であった。小倉良親と言う人がいる。彼は相谷城にいたが、辛くもそこから逃走して、小倉城に向かおうとしていた。小倉城の現状を知る由もなかった。
今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。






















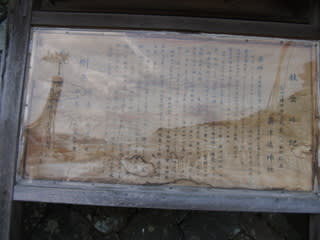


 北斜面の雛壇状縄張
北斜面の雛壇状縄張 南斜面の大岩の間を埋める石積み
南斜面の大岩の間を埋める石積み 織田 信長
織田 信長 豊臣 秀次
豊臣 秀次













 安養寺
安養寺













