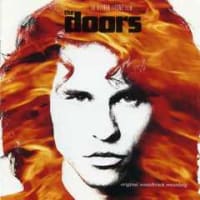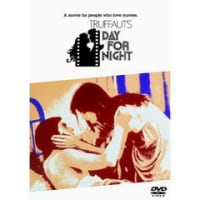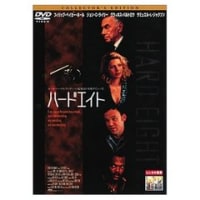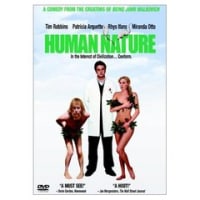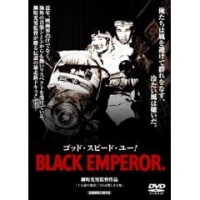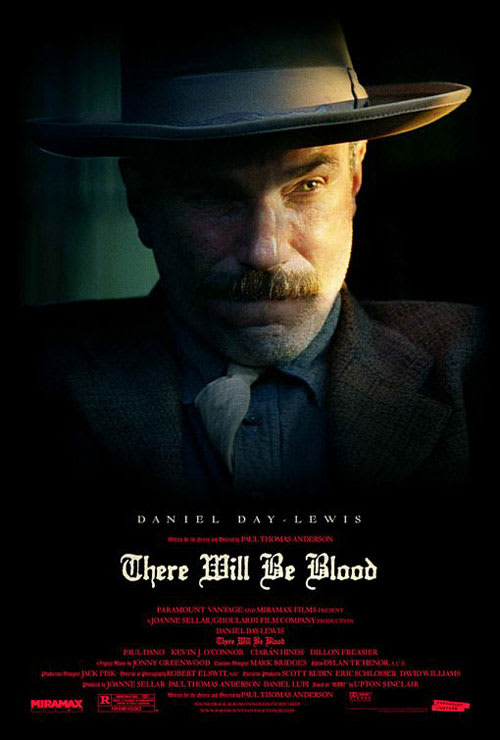
ゼア・ウィル・ビー・ブラッド(THERE WILL BE BLOOD)
2007
ポール・トーマス・アンダーソン(Paul Thomas Anderson)
傑作。
凄まじい158分の密度。
映画館に行かなかったのが悔やまれます。行けば良かった。何故行かなかったのか。
映画を見続けるということは、こういう作品に出会う為の旅と言ってもやぶさかではありません。
素晴らしかった。
結局何を描いていたのかというのがラストに暴かれるタイプの映画ではなく、全編を通して全てがタイトルに直結する映画です。
まぁ、英語はからきしなんですが、なんとなくそういう気になってます。
深読みするまでもなく『石油』と『血』が人が招くしがらみの比喩として描かれ、そのしがらみによって人は頑なになり関係は狂っていく。
潤滑油という言葉にあるくらい滑りをよくするはずの『油』を敢えてくさびとし、人と人の繋がりの最も根源的な『血』も『めんどうな』こととモチーフにしたポール・トーマス・アンダーソン監督の選球眼には舌を巻きます。
これは日本語的な言語感覚とは言い切れないでしょう。全世界的に油は滑るものだし、血(家族)は社会の最小構成単位です。
結局、どこにもここにも血も油もある、と。
「There wil be blood」を超日本語的な意訳すれば『僕等はみんな生きている』ということでは。
『手のひらを太陽に~』のアレです。あの歌ってポジティブなことだけを唄っているわけでは無いと思うのです。歌詞のラストにある『友達なんだ』の後を想像させる教育を。そこで終わらない教育を。
人は皆生きている、そして悲しいこともある。じゃぁ、貴様はどうあるべきか、と。
友達だったらその形式だけで全てが赦されると思うなよ、と。
その友達という関係は契約ではないのだ、と。
話しがずれました。
生きているからそこに油もあるし血もある。その意味は一つではなく、けれども、血もあり油もあることで生きていると言うことを証明できるのでは。
一つの説教クサイテーマを描くのではなく、根本的な原罪(?)を抱えた人間の生き様を顕すポール・トーマス・アンダーソン監督。
思えば、今までの作品でもそうだったのかもしれません。
今までは、ある一つのモチーフを借りていました。そこで描かれているのはチンコがデカイだけのポルノ男優だったり、モテない弟だったり、ギャンブル好きだったり、モテるための伝道師だったり、もうなんだか分からないくらいに壊れた人々だったり。
突飛なモチーフからドラマを生み出してそこに人生を描く、というものでしたが、本作はどうも違う気がします。
ゴールドラッシュから石油長者という浮世離れしたお話ですが、それがなんとなく万人にも当てはまってしまうような感覚。
既にモチーフが何であろうと構わないという風格すら漂います。
下手したら「スター・ウォーズ」に出てくるエンドアに住むイウォークが主人公でも構わないのでは、と思わせる手腕。
ここまで判りやすく咀嚼してテーマを描ける監督が他にいるのでしょうか。
だいたい、テーマとモチーフが直結していて、ネタバレしまくる人が殆どです。
ポール・トーマス・アンダーソン監督の場合は途中で判った気になっても、さらに、次々と覆い被せてくる。映画が終わるまで飽きさせない。終わってからも考えざるを得ない。
前作までは判りやすいカタルシスを提示して終わっていました。
本作は全然無し。むしろ判りにくすぎ。カタルシスはどこにもない。けれど、これが良いんです。好き。
ここで物語が終わることに納得いかない人は観る姿勢が調ってないだけ。文芸を読んで解決しないから怒るのと同じです。
モンモンとすることの楽しさ。
本来、こういう気持ちのために映画とか文学とか音楽とか絵画とかは存在するのでは。
希に見る傑作です。
是非とも。
ここまで言っておいてナンですが、過剰な期待は禁物です。
決して全ての人の指針になる気持ちの良い作品ではありません。
しかし、ある種の人にとってはもの凄く指針となりうる傑作です。