
LE TUBA ENCHANTEE
JOHN FLETCHER
(KING FIREBIRD COLLECTIOIN KICC-472)
小生、管楽器奏者については詳しくないのですが、このCDで演奏しているジョン・フレッチャーは、かなり有名なチューバ奏者のようですね。
1941年生まれのイギリス人で、かのフィリップ・ジョーンズ・ブラス・アンサンブルにも参加していました(PJBE解散後は、ロンドン・ブラスを結成)。しかし、1987年には、脳卒中で急逝しています。
このCDは、『蚤の歌―魔法のテューバ』という邦題で、日本で録音したもの。
前半は、チャイコフスキー(『くるみ割り人形』組曲から小序曲。テューバ四重奏曲版ということですが、フレッチャー1人の多重録音なんでしょうね)、エルガー(『朝の歌』)、ヴァグナー(『タンホイザー』から「夕星の歌」)、ムソルグスキー(「蚤の歌」)、モーツァルト(『フィガロの結婚』より「もう飛ぶまいぞこの蝶々」)といった編曲もの。
まあ、編曲ものもそれなりに面白いのですが、実際の聴き所は、後半のウォルター・ハートレー『無伴奏テューバのための組曲』とパウル・ヒンデミット『テューバとピアノのためのソナタ』、ジェニファー・グラス『テューバとピアノのためのソナティネ』でしょう(W. Hartley は1927年生まれのアメリカ人作曲家。J. Glass については、どのような音楽家なのかデータがありません)。
テューバの音色の多様性を楽しむには、ハートレーの作品が無伴奏なだけに一番でしょうし、20世紀音楽における管楽器のありかたのようなものは、ヒンデミットの作品がよく現しています(1955年作曲)。J. Glass の作品は、おそらくヒンデミットより新しいのではないかと思われます。いわゆる現代音楽に含まれるのでしょう(とは言え、十二音技法的ではない)。
このように、CD後半では三者三様のテューバ音楽が聴けます。
これにヴォーン・ウィリアムズとヴァン・ホルンボー(→こちらを参照)の『テューバ協奏曲』などがあれば、ほぼテューバ音楽の全容が掴めるでしょう。
なぜか、今日(8月23日)は涼しかったので、テューバ音楽となりました。
もし、管楽器の音色を暑苦しく感じる方がいらっしゃったら、ご免なさいであります。










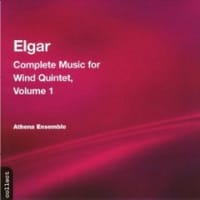
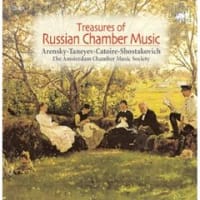
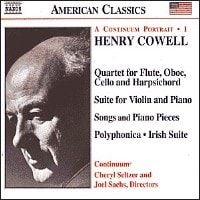

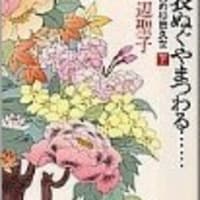
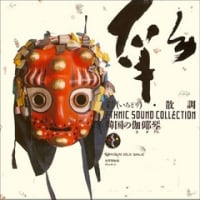
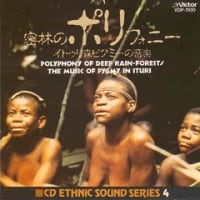
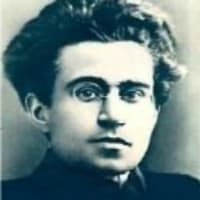
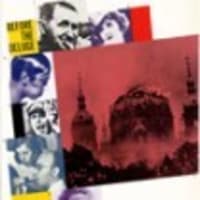
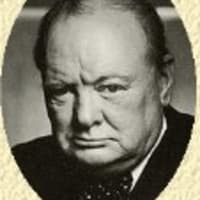
それにしても多重録音ってスゴイですねぇ。本人のテクより録音技術が優秀になってるのかな?(^w^)
大好きなのはやっぱりRVWの協奏曲ですねぇ。特にあの第二楽章は最高にマロンチック。
ところで主さま、テューバとスーザフォンの一番の違いってご存じでしょうか? 答えは、振り回すかしないか。
当然知ってらっしゃる? こりゃまた失礼を(*^_^*)
悪しからず。
ここの部分で「音楽ブログ」になってしまったのは、
ご紹介するだけの本がなかったからなのね。
大体10冊読んで、取り上げられるのは
1~2冊あればいい方なんです。
ここのところ、
「ばかやろう~、金返せ!」
とやや下品なことを言いたくなるような本ばっかりで
ご紹介できなかったんです。
困ったときのCD頼み、ということで
ご容赦賜りたいと存じます。
では、また。