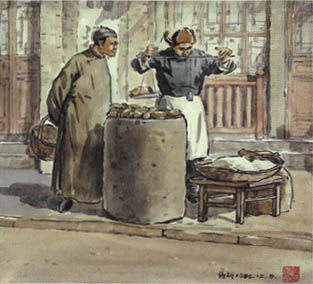■ 富察敦崇這段文字介紹臘八粥十分詳尽。第一是米、豆、果料極為斉全,白糖、紅糖如算一様,則共十六様之多,即生料八種,都是“八”,符合臘八“八宝”之数。因為這様的粥,臘八日叫:“臘八粥”,平時則叫“八宝粥”,所以配料都有八様之多。第二是経夜経営,天明即熟,這不禁喚起許多人童年的記憶,是十分美妙的。作母親的催孩子早点睡,説道:“快睡吧,明儿早点起来喝臘八粥;太陽一出,再喝,要紅眼睛 …… 快睡吧,宝貝!”
・生料 sheng1liao4 未加工の原料。原材料
富察敦崇のこの文章は臘八粥をたいへん詳しく紹介している。第一に米、豆、果実はいろいろな種類が揃っていなければならず、白砂糖と黒砂糖を同じものとすれば、全部で十六種類にもなる。煮る材料が八種類で、“八”であるので、臘八“八宝”の数に合っている。このような粥は、臘八の日は“臘八粥”と呼ぶが、日常は“八宝粥”と呼ぶので、入れる材料は八種類もあるのである。第二に夜通し準備をし、夜明けには煮えていることで、これは多くの人の子供時代の記憶を呼び起こすことを禁じ得ず、たいへん麗しい。母親が子供に早く寝るよう促し、こう言う。「早く寝なさい、明日の朝は起きたら臘八粥を飲むのよ。お日さまが昇ってから飲んだら、眼が赤くなってしまうわよ……早く寝なさい、おりこうさん。」
■ 這様,便帯着甜蜜而温暖的憧憬入夢了,一大早,起来,吃這碗一年一度的香甜而美妙別致的臘八粥,這種生活的情趣,不是也像西方儿童在睡夢中等待聖誕礼物那様美好嗎?
・憧憬 chong1jing3 憧憬。あこがれ
このように、甘く温かい憧憬を抱いて眠りにつき、翌朝早く起きて、この、年に一度の甘く麗しいことこの上ない臘八粥を食べるという、こういう生活の情緒は、西洋の子供達が眠りの中でサンタのプレゼントを待つあの幸福と同じではないか。
■ 第三是分饋親友,不得過午,這也是極有情趣的礼物。北京過去有一種緑盆,是一種上了緑琉璃瓦釉子的瓦盆。有的人家,用這種盆,盛上紅艶艶的粥,上面用雪花綿白糖洒成“寿”字、“喜”字、“福”字等等,再洒上一点青絲、紅絲。如此,亮晶晶的緑釉器皿、紅艶艶的粥、雪白的糖、鮮艶的青絲、紅絲,相映成趣,送到親友家中,真是絶妙的藝術品,充満了歓楽的藝術生活情趣,却毫無庸俗、雕琢的富貴気息,這才是真正的色、香、味、形、器兼備,又加豊富情趣的精美食品。
・亮晶晶 liang4jing1jing1 ぴかぴか光る
・雕琢 diao1zhuo2 (玉を)彫り刻む
第三に、親戚や友人に贈り、昼を過ぎてはならない、ということで、これもたいへん情緒のある贈り物である。北京では昔、一種の緑色の鉢があり、緑の瑠璃瓦の釉薬をかけた焼き物の鉢であった。家によっては、こうした鉢に、赤く艶やかな粥を入れ、その上に綿あめを散らして“寿”、“喜”、“福”の字を描き、さらに青や赤の糸状の飴を散らした。このようにして、ぴかぴか光る緑釉の器、赤く艶やかな粥、真っ白な砂糖、鮮やかな青や赤の飴が、互いに引き立てあい、親戚や友人宅に贈り届けると、本当に絶妙な芸術品で、楽しい芸術生活の情緒が満ちあふれ、少しも俗っぽいところがなく、彫り刻まれた富貴の息吹により、これこそ本当に色、香、形、器を兼ね備えているだけでなく、それに豊な情緒が加わった精緻な食品である。
■ 不過富察敦崇所説臘八粥中不宜用蓮子、扁豆、薏米、桂元等,用則傷味的説法,据我所知,其説似不尽然。桂元肉一般是不放的,放了稍有苦味。蓮子、薏米仁一般都是放的,有的還放芡実(即鶏頭米),這在《天咫偶聞》、《民社北平指南》等書均有記載。都足以証明《燕京歳時記》之説,并不尽然。
・芡実 qian4shi2 オニバスの実。江南地方では、“鶏頭米”と言う。
しかし、富察敦崇の言う、臘八粥の中にはハスの実、インゲン、ハト麦、龍眼などを入れるのはよくなく、入れると風味を損なうという説については、私の知っているところでは、必ずしもそうではない。龍眼は一般には入れない。入れると少し苦みが出る。ハスの実、ハト麦は入れることが多く、更にオニバスの実(鶏頭米)を入れる場合もある。これは《天咫偶聞》、《民社北平指南》などの書に書かれている。こうしたことから、《燕京歳時記》の説明は必ずしも正しくないことが証明できるだろう。
■ 在清代皇宮中仍然継承了明代的伝統,十分重視煮臘八粥的。道光帝愛新覚羅旻寧有一首《臘八粥詩》,收在《養正書屋全集》中,詩是七古,并不好,但作為史料,亦可見旧時風俗和宮廷生活之一斑,現引在下面:
一陽初復中大呂,谷粟為粥和豆煮;
応節献佛矢心虔,默祝金光済衆普。
盈几馨香細細浮,堆盤果蔬紛紛聚;
共嘗佳品達妙門,妙門色相伝蓮炬。
童稚飽腹慶升平,還向街頭撃臘鼓。
・七古 qi1gu3 七言古体詩
・一斑 yi1ban1 一端。全体の一部分
・一陽復始 天地の陰陽の二気が、毎年冬至になると、陰が尽き陽が再び生じることから、春が再びやってくることを表す
・大呂 da4lv3 夏暦の十二月の別称
・妙門 miao4men2 仏教や道教で、細かな教理を悟るこつ。或いは仏門のこと。
・蓮炬 lian2ju4 蓮の花の形のロウソク
・升平 sheng1ping2 天下太平
・臘鼓 la4gu3 旧暦の12月に太鼓を打ち鳴らし、春の訪れを促す、昔の風習。
清代の宮中では明代の伝統が継承され、臘八粥を煮ることが重視された。道光帝愛新覚羅旻寧は《臘八粥詩》を作ったが、これは《養正書屋全集》に収められている。詩は七言古体詩で、出来はあまり良くないが、歴史資料であり、昔の風俗や宮廷生活の一端を垣間見ることができる。以下に引用すると:
陰が尽き再び陽が生じてまた十二月がやって来た。米や粟を粥にし、豆といっしょに煮る。
節句に合わせて仏にお供えをし、心から敬虔を誓い、陽の光が民衆を救済してくれるのを祈る。
良い香りがあたりに漂い、お盆一杯の果物や野菜が次々と集まって来る。
共にこの佳品を味わい、悟りの境地に到ろう。仏門では眼で見える姿形は蓮の花の形のロウソクに伝わるという。
子供達はもうお腹一杯になり、天下太平を喜び、また街に向けては迎春の太鼓が打ち鳴らされている。
■ 従詩中可以看出,重点是説臘八粥是佛教的食品,是清素的。但流伝至民間,在一般家庭中,已失去它佛教的意義,成為一種歳時節令,富有生活情趣的精美節日食品了。但在宮廷中,它的宗教意義還是很重的,而且還有政治意義。《京都風俗志》説:“黄衣寺僧,亦多作粥。”清代后来定制,臘八粥是帰雍和宮的喇嘛熬的,就是黄衣寺僧。《光緒順天府志》記云:
臘八粥,一名八宝粥,毎歳臘月八日,雍和宮熬粥,定制,派大臣監視,蓋供上膳焉。其粥用粳米雑果品和糖而熬。民間毎家煮之,或相饋遺。
詩から分かるのは、その重点は、臘八粥は仏教の食品だということで、精進ものである。しかし民間に伝わり、一般の家庭の中では、仏教の意義は失われ、一種の季節の風物詩になり、生活情緒に満ちた美しい節句の食品になった。しかし宮廷では、その宗教的意義はまだ重く、また政治的な意義もあった。《京都風俗志》に言う:「黄衣の寺僧は、多くは粥を作る。」清代には後に、臘八粥は雍和宮のラマ僧が作るものと定められた。つまり黄衣の寺僧である。《光緒順天府志》の記載に言う:
臘八粥は、一名を八宝粥と言い、毎年12月8日、雍和宮で粥が作られ、そのように定められ、大臣が遣わされ監視する。蓋し皇帝の御膳に上るのであろう。その粥はうるち米と様々な果実と砂糖で作られる。民間でも家々で粥が煮られ、また贈り物にされる。
■ 《燕京歳時記》也記云:
雍和宮喇嘛,于初八日夜内,熬粥供佛。特派大臣監視,以昭誠敬。其粥鍋之大,可容数石米。
・石 dan4 容積の単位、石(こく)1石=100升。/但し、昔の俸禄高を示す時の発音はshi2である。たとえば“二千石”などと言う場合。
《燕京歳時記》の記載でもこう言っている:
雍和宮のラマ僧は、八日の夜に、粥を作りお供えをする。特に大臣が派遣されて監視し、それによって皇帝への忠誠と敬意を明らかにする。その粥を作る鍋の大きさといったら、一度に数石の米が入るほどである。
■ 従這両則記載中,可以看出,清代宮廷対于臘八粥多麼重視,還要派大臣監視熬粥,現在想起来,似乎是很滑稽的事情了。但要想到当年那許多喇嘛,準備果料,囲着那可容数石米的大銅鍋,在油灯盞的照耀下,忙乱着熬粥,穿貂褂、帯朝珠、大紅頂子、海龍暖帽的大臣隆重地旁辺監視焼粥,這種朦朧的歴史画面,不是具有十分神秘感的嗎?現在感到很難想像的東西,在当年都是生生的事実,而且是持続了上百年的事実,于今則頗為渺茫了。現在雍和宮又重修開放了,如果那口大鍋還在,熬一鍋臘八粥,給中外游客当点心吃,不也是很有趣味的、很名貴的一種甜点嗎?
・則 ze2 [量詞]条文を数える
・渺茫 miao3mang2 渺茫(びょうぼう)としている。ぼんやりしてはっきりしない
この二つの記載の中で、分かることは、清代の宮廷が臘八粥をたいへん重視していたことで、大臣まで派遣して粥を作るのを監視させたというのは、今想像してみると、いささか滑稽なことである。しかし当時はたくさんのラマ僧がいて、果実や材料を準備し、何石もの米が入る大きな銅鍋を囲んで、燈明の明かりの下、忙しく粥を煮、テンの前掛け、珠のネックレス、赤い帽子飾り、ラッコの防寒帽を身に付けた大臣が厳かに傍らで粥を炊くのを監視しているという、朦朧とした歴史の一場面は、たいへん神秘的な感じがしないだろうか。現在では想像し難いことが、当時は紛れもない事実で、しかも百年以上も続いた事実であるなんて、今となってはぼんやりして理解できない。現在、雍和宮は修復されて一般公開されているので、もしあの大鍋がまだ残っているなら、臘八粥を作って、国の内外からの旅行客に振舞ったら、たいへんおもしろいし、名物になるのではないだろうか。
■ 一粥之微,几百年中,由宮廷到民間,由宗教寺廟到普通世俗人家,都那麼認真,那麼重視,熬得那様精美,那様富有情趣,記載在那麼多的文献中,這正是我国悠久的歴史文化精髓的一点一滴啊!這還不値得加以称道、介紹和宣揚嗎?
一杯の粥の機微が、数百年を経て、宮廷から民間へ、仏教寺院から一般家庭に伝わり、こんなにも真剣に、こんなにも重んじられ、作られた粥は精緻で、情緒に富み、あんなにもたくさんの文献に記載された。これは正に我が国の悠久の歴史文化の神髄の一点一滴ではないだろうか。これでもなお賞賛し、紹介し、宣伝するに値しないと言えますか?
【出典】雲郷《雲郷話食》河北教育出版社 2004年11月
にほんブログ村
にほんブログ村
人気ブログランキングへ