最新の画像[もっと見る]
-
 鴻風俳句教室四月句会
2年前
鴻風俳句教室四月句会
2年前
-
 濃霧
3年前
濃霧
3年前
-
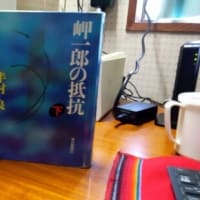 岬一郎の抵抗上・下(半村 良著)
4年前
岬一郎の抵抗上・下(半村 良著)
4年前
-
 😴鴻風俳句教室六月句会 池窪弘務
4年前
😴鴻風俳句教室六月句会 池窪弘務
4年前
-
 😊今日の一句
4年前
😊今日の一句
4年前
-
 😊今日の一句
4年前
😊今日の一句
4年前
-
 今日の一句
4年前
今日の一句
4年前
-
 今日の一句
4年前
今日の一句
4年前
-
 😊🤔今日の一句
4年前
😊🤔今日の一句
4年前
-
 『死者の書』原作折口信夫・漫画近藤ようこ(2)
4年前
『死者の書』原作折口信夫・漫画近藤ようこ(2)
4年前
 鴻風俳句教室四月句会
2年前
鴻風俳句教室四月句会
2年前
 濃霧
3年前
濃霧
3年前
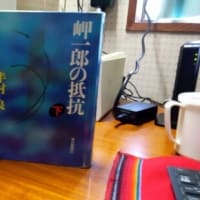 岬一郎の抵抗上・下(半村 良著)
4年前
岬一郎の抵抗上・下(半村 良著)
4年前
 😴鴻風俳句教室六月句会 池窪弘務
4年前
😴鴻風俳句教室六月句会 池窪弘務
4年前
 😊今日の一句
4年前
😊今日の一句
4年前
 😊今日の一句
4年前
😊今日の一句
4年前
 今日の一句
4年前
今日の一句
4年前
 今日の一句
4年前
今日の一句
4年前
 😊🤔今日の一句
4年前
😊🤔今日の一句
4年前
 『死者の書』原作折口信夫・漫画近藤ようこ(2)
4年前
『死者の書』原作折口信夫・漫画近藤ようこ(2)
4年前
「想」創刊号 感想
●積さんの俳句、詩、短編
句は花鳥風月に人間存在のはかなさを歌うか花鳥風月を愛でる感じ。
「位相」というのは俳句にはふさわしくないと思いました。形而上的な臭いのする言葉は詩文おいてはアピール度が弱いと思います。哲学の伝統のない日本人には難解すぎる。
詩、短編はよくわからぬ。何かのアナロジーなのでしょうが!?
己の中に、何かの己がものでない者の存在を感じることをいっているのかな。
●「僕と魔女と」
えんえんと情景のことを書くのは、もっと主人公なりの行動に伴って説明したほうが、読者を引き付けるのではと思う。確かに「場」の説明は必要であるが、何かもう少し工夫がないと興味が失せる可能性が高い。物語の伏線として意味もあるのでしょうが解り難いですね。人の会話を所々で入れるといいのでは。
ところで、小説の意図や作者の意図とは関係ないものかもしれませんが、また、釈迦に説法かもしれませんが、人が人を食う程、江戸時代の天災がひどかったのは封建体制が、また、商品経済が関係するのであって、天災の大きな被害は自然の避けられぬ運命ではない。これは江戸時代の旅行者の記事にもその種のことは書かれている。餓死した人々の怨念はこの体制に向けられるべきでしょう。ただ、かれらはそのことに気付かせられないようにコントロールされていた。江戸時代は耕地面積が8割増加したが、人口はほとんど変わらなかった。戦国時代はむしろ人口が増えていたとする説もある。歴史学の文章ではないが、この視点も小説や物語にあってよいだろう。
死者とのつながりを持とうとするところは読者の共感を呼ぶでしょう。主人公の思春期の生のピークと死を対比するアイデアは悪くないですね。映画「おくり人」がアカデミー賞をとったことだし。
霊をみるのはほどほどに、現実をみて、どうするかを考えていくのが供養であるように思う。死者を弔うのが生人のためであるなら。
視霊者は田口ランディ作品の主人公よりスウェーデンボルグのほうがわかりやすいと思ってしまいます。
●「敦賀」
最後は救われた気がします。
もっと情緒的な物語にするなら、店長も主人公も死なせて、ロボットだけを残すのも良いかもしれません。
ロボットを媒介にして、人の絆を描くアイデアはいいですね。犬猫のペットを話題にして人が関係みたいなものを作りますから。
近未来SFかファンタジーかわからないけど、読者は現実とどう折り合いをつけるか。現実にないものや、ない現象について考え、思いを巡らすのはかなり強烈で、それはミステリヤーやポルノを上回る興奮を無意識にも意識にも与え読者をひっぱっていく。物語は嘘であるが、嘘を通して真実を感じさせないで、その強烈さにドーパミンが出てきて、その読んでいるときはいいが後にから考えると、興奮が終わると、何も残らない可能性がある。SF小説ばかり読んでいた自分の高校生時代からの疑問です。