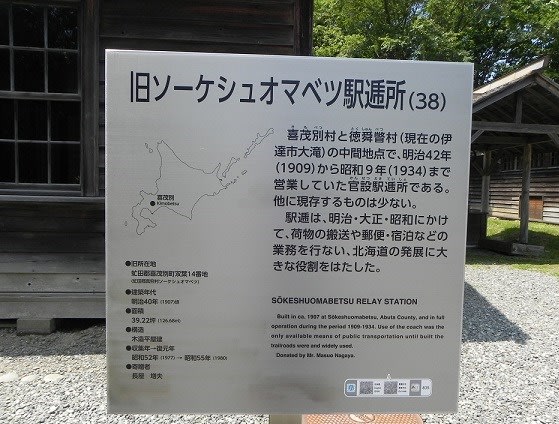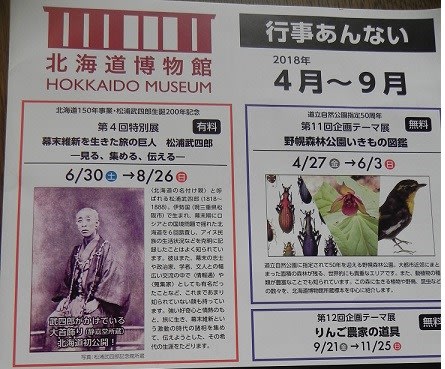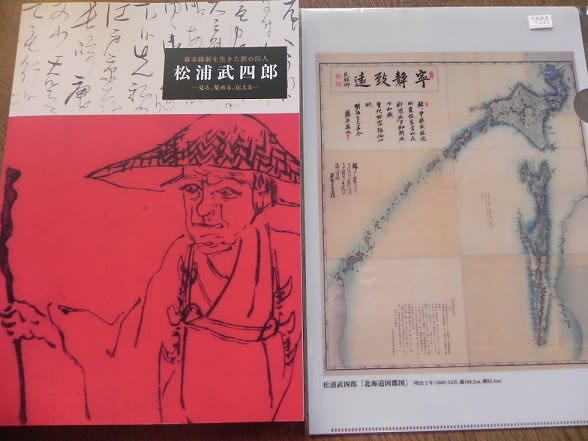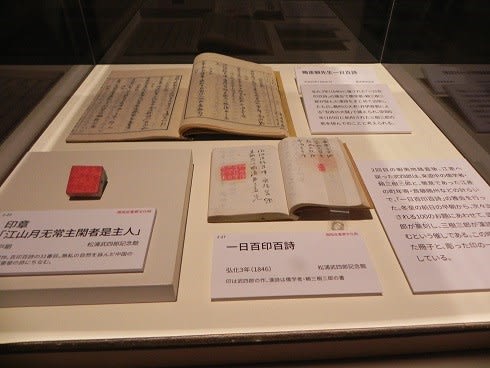北海道開拓の村には廻りきれないほどの歴史的建造物や文化的な遺産といえるような場所もあった。
(1)旧札幌農学校寄宿舎
札幌農学校(現在の北海道大学)は明治9年(1876)現在の時計台付近に開学し、明治36年現在の北海道大学の構内へ移し、寄宿舎も新築され、「恵迪寮」と命名されたもの。


(2)旧有島家住宅
日本近代文学史上の代表的作家の一人である有島武郎、明治11年(1878)~大正12年(1923)が明治43年(1910)5月から翌年7月頃まで住んでいた建物。
旧所在地は札幌市白石区菊水1条17丁目
一般住宅にも上げ下げ窓などの洋風意匠を取り入れ始めた頃の建物であるとのこと。


(3)旧島歌郵便局
「北海道で今のような郵便物の取り扱いが始まったのは明治5年。
島歌には明治19年に郵便局がおかれた。この頃の島歌は鰊や昆布の漁が盛んだったため、人の出入りが多く郵便物の取り扱いも多かったという。

(4)旧近藤医院
「明治33年に函館病院から古平病院内科医長として近藤清吉が招かれた。古平の大火で病院が焼けてしまい、大正8年に新しく建てたもの。
彼は患者がいれば例え夜中であっても走りまわったという。
時にはお金の無い人にも治療費は一握りの野菜や魚でも診ていたという。(まさに古平の赤ひげ先生・・・と私は感じた。)


(5)旧廣瀬写真館
「大正の終わりから昭和33年まで岩見沢市で営業していた。ガラスの屋根からは自然光がスタジオに入っていたという。

(6)旧小樽新聞社
「小樽新聞社は明治27年(1894)に創刊され函館新聞、北海タイムスとともに道内の代表的新聞社の一つであった。
この建物は木造の骨組みに札幌近郊で産出する札幌軟石で外壁に積み上げられた構造で、明治期石造建築の特徴を示している。」


(1)旧札幌農学校寄宿舎
札幌農学校(現在の北海道大学)は明治9年(1876)現在の時計台付近に開学し、明治36年現在の北海道大学の構内へ移し、寄宿舎も新築され、「恵迪寮」と命名されたもの。


(2)旧有島家住宅
日本近代文学史上の代表的作家の一人である有島武郎、明治11年(1878)~大正12年(1923)が明治43年(1910)5月から翌年7月頃まで住んでいた建物。
旧所在地は札幌市白石区菊水1条17丁目
一般住宅にも上げ下げ窓などの洋風意匠を取り入れ始めた頃の建物であるとのこと。


(3)旧島歌郵便局
「北海道で今のような郵便物の取り扱いが始まったのは明治5年。
島歌には明治19年に郵便局がおかれた。この頃の島歌は鰊や昆布の漁が盛んだったため、人の出入りが多く郵便物の取り扱いも多かったという。

(4)旧近藤医院
「明治33年に函館病院から古平病院内科医長として近藤清吉が招かれた。古平の大火で病院が焼けてしまい、大正8年に新しく建てたもの。
彼は患者がいれば例え夜中であっても走りまわったという。
時にはお金の無い人にも治療費は一握りの野菜や魚でも診ていたという。(まさに古平の赤ひげ先生・・・と私は感じた。)


(5)旧廣瀬写真館
「大正の終わりから昭和33年まで岩見沢市で営業していた。ガラスの屋根からは自然光がスタジオに入っていたという。

(6)旧小樽新聞社
「小樽新聞社は明治27年(1894)に創刊され函館新聞、北海タイムスとともに道内の代表的新聞社の一つであった。
この建物は木造の骨組みに札幌近郊で産出する札幌軟石で外壁に積み上げられた構造で、明治期石造建築の特徴を示している。」