様々なメタ(76)社会学系(21)
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
TITLE: アメリカ人のメタ認知
書籍名;「情の技法」[2006]
初回作成日;2022.2.17 最終改定日;
「情」について、「情の技法」(慶応義塾大学出版会[2006])の冒頭の「はじめに」には、次のように書かれている。
『「情」という言葉の指すものが、半ば自動的、無自覚的に扱われがちであり、明確な姿を取ることなしに広い領域に渡るものだからである。我々は日々を暮らしてゆく中で、他者の、あるいは自己の心のさまざまな働きを感じ取る。「情」とは、言わばそうして知覚された心の作用を総称する言葉だと考えることができるだろう。「情」の「技法」を論ずることは、たとえるなら、意識することなく繰ることのできる母語の「技法」を、改めて一から論ずることに近い。』(p.ⅰ)とある。

さらに続けて、『知は既に体系化された形で人々の間に存在し、それに参加し、支え、新たな展開を担うことへと、意欲ある人々を誘っている。 しかし「情の技法」を論ずる際に、同様な状況は期待できない。無論、さまざまな領域、特に芸術の世界においては、技巧を開発し伝承する過程において、「情の技法」とも呼ぶべきものの確立と継承が行われてきた。しかし一般化された「情」そのものの姿が、体系化されたものとして我々の眼前に存在しているわけではない。「情」を理解するためには、さまざまな領域での具体的な「技法」を個別に諭じ、積み重ねて行くこと、またそれを手がかりとして、正面から「情」の姿と働きを捉えるべく試行錯誤を繰り返すことが必要であろう。この論文集はそうした 試みのーつである。』(p.ⅱ)
随分と難解な文章なのだが、「情」というものを学際的に捉えてみようとのことらしい。
具体的には、この書の内容は慶応大学文学部での授業(2003-2004)の内容を基に執筆されたとある。それだけでも、十分にメタと云えるのだが、その中で「メタ認知」を強調した章があった。題名は「反知識人とは何か」となっており、内容は「反知性主義のアメリカ文学思想史」になっている。
米国での初期の移民と独立の歴史から現代に至る歴史は、『ヨーロッパ系の知性主義が、紆余曲折を経て反知性主義の伝統と表裏一体になってゆく足取りを辿ることである。』(p.14)とある。たまたま最近の4年間に亘って、米国を支配した「トランプ主義」も、この仲間かもしれない。つまり、アメリカの反知性主義は、文学から始まって、政治の世界にまで広がっている。
トランプの熱烈な支持層として、キリスト教福音派が有名になったが、ここでは、次のように書かれている。『キリスト教徒の中では、「精神Mindと心情Heart, 情緒Emotionと知性Intellectの緊張関係」はさほど珍しくないのであり、知性を中心に理論を重視する向きと、知性を感情や熱狂よりも劣るものと見なす向きとが、たえず衝突し合っていたことから説き起こす。そして、アメリカの地が、その初期には、ヨーロッパの不満分子や非抑圧者を数多くひきつけ、当時宗教的な「熱狂主義」enthusiasmと批判された預言者たちにとって理想の国となったこと、熱狂主義の根本は個人が教会を媒介せずとも直接神と語り合う衝動であることが、確認される。それでは、このような思想はどのように歴史的発展を遂げたのか。』(p.15)から、文学史の具体的な説明が始まっている。
文学の話はさておいて、反知性主義は米大陸の西部開拓史の中で力を得てゆく。そして、南北戦争の敗北による奴隷解放などで、その力を失うが、第2次世界大戦でノルマンジー上陸作戦を成功させたアイゼンハワー将軍が大統領になると、一気に力を盛り返すことになる。そこで、『複雑怪奇ではなく単純明快を求めるのは、アメリカ的反知性主義の伝統』(p.19)ということになる。
そして、『いってみれば情緒と思われてきた素材を、すべて形式面で活かしていく仕事である。プロテスタンティズムの倫理が資本主義の精神を構成したと定式化したのはマックス・ウューバーであったが 、同じように、簡潔明快な「かたち」の中には、これ以上分割できず、破壊できず、いつまでも存在しうるものを切望する「きもち」が巧妙に刷り込まれている。』(p.19)となる。このことは、種々雑多な移民の集団の中では、
「簡潔明快なかたち」しか、あり得なかったことを示している。
そして結論としては、ソローの文学を引き合いに出して、次のように述べている。
けだし、「ソロー」とは、『ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(Henry David Thoreau、1817年 - 1862)は、アメリカ合衆国の作家・思想家・詩人・博物学者。自身の没後に『メインの森』(1864年)や『コッド岬』(1865年)などの旅行記や、自然誌エッセー、日記、書簡集等、数多くの作品が出版されている。ソローの作品は、人間と自然との関係をテーマにしたものが多く、自然文学、今で言うネイチャーライティングの系譜に位置づけられる。多くの著作に現在の生態学に通じる考え方が表明されており、アメリカにおける環境保護運動の先駆者としての評価も確立されている。日本においてもアウトドア愛好家などに信奉者が多い。
』Wikipediaより。
文末は、『すで充分にアメリカという名の森を生きているだろう。反知性主義はたしかに「情の技法」の典型であるように見える。だが、反知性主義すら体系化するメタ知識の方法論こそは、アメリカ的知識人の最も本質的な条件を成すように思われることもまた、否定することはできない。』(p.21)で終わっている。
「メタ知識の方法論」が、反知性主義すら体系化したということは、トランプ政権によって見事に証明されている。
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
TITLE: アメリカ人のメタ認知
書籍名;「情の技法」[2006]
初回作成日;2022.2.17 最終改定日;
「情」について、「情の技法」(慶応義塾大学出版会[2006])の冒頭の「はじめに」には、次のように書かれている。
『「情」という言葉の指すものが、半ば自動的、無自覚的に扱われがちであり、明確な姿を取ることなしに広い領域に渡るものだからである。我々は日々を暮らしてゆく中で、他者の、あるいは自己の心のさまざまな働きを感じ取る。「情」とは、言わばそうして知覚された心の作用を総称する言葉だと考えることができるだろう。「情」の「技法」を論ずることは、たとえるなら、意識することなく繰ることのできる母語の「技法」を、改めて一から論ずることに近い。』(p.ⅰ)とある。

さらに続けて、『知は既に体系化された形で人々の間に存在し、それに参加し、支え、新たな展開を担うことへと、意欲ある人々を誘っている。 しかし「情の技法」を論ずる際に、同様な状況は期待できない。無論、さまざまな領域、特に芸術の世界においては、技巧を開発し伝承する過程において、「情の技法」とも呼ぶべきものの確立と継承が行われてきた。しかし一般化された「情」そのものの姿が、体系化されたものとして我々の眼前に存在しているわけではない。「情」を理解するためには、さまざまな領域での具体的な「技法」を個別に諭じ、積み重ねて行くこと、またそれを手がかりとして、正面から「情」の姿と働きを捉えるべく試行錯誤を繰り返すことが必要であろう。この論文集はそうした 試みのーつである。』(p.ⅱ)
随分と難解な文章なのだが、「情」というものを学際的に捉えてみようとのことらしい。
具体的には、この書の内容は慶応大学文学部での授業(2003-2004)の内容を基に執筆されたとある。それだけでも、十分にメタと云えるのだが、その中で「メタ認知」を強調した章があった。題名は「反知識人とは何か」となっており、内容は「反知性主義のアメリカ文学思想史」になっている。
米国での初期の移民と独立の歴史から現代に至る歴史は、『ヨーロッパ系の知性主義が、紆余曲折を経て反知性主義の伝統と表裏一体になってゆく足取りを辿ることである。』(p.14)とある。たまたま最近の4年間に亘って、米国を支配した「トランプ主義」も、この仲間かもしれない。つまり、アメリカの反知性主義は、文学から始まって、政治の世界にまで広がっている。
トランプの熱烈な支持層として、キリスト教福音派が有名になったが、ここでは、次のように書かれている。『キリスト教徒の中では、「精神Mindと心情Heart, 情緒Emotionと知性Intellectの緊張関係」はさほど珍しくないのであり、知性を中心に理論を重視する向きと、知性を感情や熱狂よりも劣るものと見なす向きとが、たえず衝突し合っていたことから説き起こす。そして、アメリカの地が、その初期には、ヨーロッパの不満分子や非抑圧者を数多くひきつけ、当時宗教的な「熱狂主義」enthusiasmと批判された預言者たちにとって理想の国となったこと、熱狂主義の根本は個人が教会を媒介せずとも直接神と語り合う衝動であることが、確認される。それでは、このような思想はどのように歴史的発展を遂げたのか。』(p.15)から、文学史の具体的な説明が始まっている。
文学の話はさておいて、反知性主義は米大陸の西部開拓史の中で力を得てゆく。そして、南北戦争の敗北による奴隷解放などで、その力を失うが、第2次世界大戦でノルマンジー上陸作戦を成功させたアイゼンハワー将軍が大統領になると、一気に力を盛り返すことになる。そこで、『複雑怪奇ではなく単純明快を求めるのは、アメリカ的反知性主義の伝統』(p.19)ということになる。
そして、『いってみれば情緒と思われてきた素材を、すべて形式面で活かしていく仕事である。プロテスタンティズムの倫理が資本主義の精神を構成したと定式化したのはマックス・ウューバーであったが 、同じように、簡潔明快な「かたち」の中には、これ以上分割できず、破壊できず、いつまでも存在しうるものを切望する「きもち」が巧妙に刷り込まれている。』(p.19)となる。このことは、種々雑多な移民の集団の中では、
「簡潔明快なかたち」しか、あり得なかったことを示している。
そして結論としては、ソローの文学を引き合いに出して、次のように述べている。
けだし、「ソロー」とは、『ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(Henry David Thoreau、1817年 - 1862)は、アメリカ合衆国の作家・思想家・詩人・博物学者。自身の没後に『メインの森』(1864年)や『コッド岬』(1865年)などの旅行記や、自然誌エッセー、日記、書簡集等、数多くの作品が出版されている。ソローの作品は、人間と自然との関係をテーマにしたものが多く、自然文学、今で言うネイチャーライティングの系譜に位置づけられる。多くの著作に現在の生態学に通じる考え方が表明されており、アメリカにおける環境保護運動の先駆者としての評価も確立されている。日本においてもアウトドア愛好家などに信奉者が多い。
』Wikipediaより。
文末は、『すで充分にアメリカという名の森を生きているだろう。反知性主義はたしかに「情の技法」の典型であるように見える。だが、反知性主義すら体系化するメタ知識の方法論こそは、アメリカ的知識人の最も本質的な条件を成すように思われることもまた、否定することはできない。』(p.21)で終わっている。
「メタ知識の方法論」が、反知性主義すら体系化したということは、トランプ政権によって見事に証明されている。












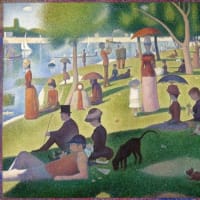
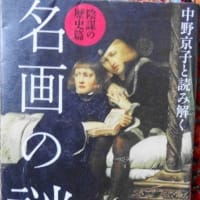


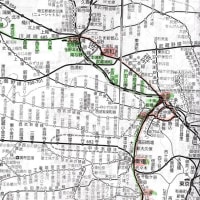


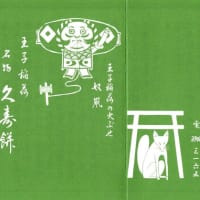
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます