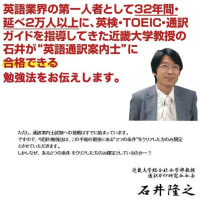2020年度<合格体験記>(19)(英語)

●英語(第2次口述試験専用メルマガ特別会員、無料動画利用者、教材利用者)
①受験の動機
動機としては色々あるのですが、直接的な動機は、3年ほど前に学生時代に留学していた時にステイしていたホストファミリーが日本に旅行に来た時に、京都、奈良などの観光地を案内して回った際に、英語はもちろん日本文化の知識の乏しさに愕然とし、これを機に自国のことをもっと勉強しようと思ったことがきっかけでした。
その時はただ案内しただけで、ガイド的なことは今思えばほとんどできなかったのですが、案内したり紹介したりすることが大変でも楽しかったので、そういう資格があると知って挑戦してみようと思いました。
②第1次試験対策
<英語>免除⇒2019年度受験時(73点)自己採点
受験しようと思ってからあまり時間がなかったので、取り急ぎ過去問をひたすら解きました。しかし、過去問を初めに解いた時に、自分が日本文化・事象を説明する日本語の語句の内容をきちんと理解していないこと、問題に掲載されている写真の場所がわからなかったりと、そもそも日本文化や事象についてよく把握していないことを自覚し、これではこの試験では点数をとれないと感じました。
ほかの教科も知識不足を自覚していたので、ひとまず英語に関しては、語研が出版している直前対策問題集を購入してひたすら問題に取り組み、その中で日本文化・事象に関する新たな知識、英単語、英語での表現方法などを覚えていきました。結果、英語の筆記試験は運もあってぎりぎり通過という感じだったと思います。
<第1次筆記試験【問題】>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<英語力診断テスト>
http://www.hello.ac/guide/clinic/index.php
<日本地理>免除⇒2019年度受験時(86点)自己採点
地理を真面目に勉強するのは中学以来だったので、どこから手を付けてよいかわからなかったのですが、まずは過去問で何が出るかを知るべきと思い、ハローより過去問をダウンロードしてひたすら解きました。
最初はあまりにできなくて、知らない地名ばかりで愕然としましたが、出題されるものが観光地と結びついていることなどが推察されたので、過去問を解きながら、都度地図で確認したりガイドブックで確認したりして覚えるようにしました。
その際、今までに自分が訪れたことのある場所は思い出しやすく、また、周辺地理も関連付けやすかったので、既知情報と関連づけて覚えるようにしたら、覚えやすくなりました。
何か良い資料はないかと本屋を探索したときに「なるほど知図帳日本2019/ニュースと併せて読みたい日本地図」という大判の本があり、一般常識や最近の情報を知るのと同時に日本地理も確認出来て大いに役に立ちました。試験前には、ハローの白地図や問題を総復習的に使い、事前確認とお守りとして受験会場に持参しました。
<第1次筆記試験【解答例】>(2004年~2019年)
http://www.hello.ac/geo.kaitourei.2004.2019.pdf
<項目別地図帳>
http://hello.ac/geography/map.pdf
<都道府県別地図帳>
http://hello.ac/map.prefectures.pdf
<日本歴史>免除⇒2019年に歴史検定2級を取得、また、2020年1月にセンター試験を受け、日本史で89点取得
日本史は、中学以来全く勉強したことがなく、実は全く興味を持たずにきた分野だったので、2019年度の一次試験を受ける際にも一番のネックでした。
ほぼ白紙状態から始めたと言っても過言ではなく、過去問を最初に解いた時はあまりにわからなくてちょっとこの試験に挑戦するのは無理なのではないかと思ったほどです。
とりあえず、ほかの教科もままならず時間がなかったので、2019年度一次試験受験にあたっては、ハローの過去問、資料をひたすら読み込み、また、全体像を把握するためにいくつか参考書を買って臨みました。しかし結果は不合格、この出題傾向が続くとしたら私は来年も受からないだろうと思ったので、気持ちを切り替えて免除を取りに行こうと考え、続けて歴史検定2級とセンター試験に臨むことにしました。
少し時間ができましたし、特にセンター試験は正攻法の問題が出るとわかっていたのでそちらに標準を絞り、山川の日本史の教科書、資料集、日本史ノート、日本史用語集を買い、大学受験の時のように教科書を読み込む方法で覚えていきました。また、センター試験過去問20年分(赤本1冊)をやりこみました。
歴史検定のほうが問題としては記述もありますし、難易度が少し高いように思われましたが、おそらくギリギリで合格、センター試験は最後のセンター試験ということもあって初出題資料もありびっくりしましたが、安心して確実に点を取ることができました。
共通試験もセンター試験の傾向が続くとしたら、正当な問題が出やすいですし、ひねってあるように見えても、
落ち着いて考えれば解答が導き出せるようになっていると思われるので、私はこちらを受験して免除を取るほうが
確実で労力も少なくてすむと思います。
ただ、受験に関しては、当たり前ですが現役高校生に交じって受けることになるので、私はかなりの覚悟が必要でした。地方での受験でしたので、女子大での受験で同じ教室には現役女子高生しかおらず恥ずかしいのなんの、大学の門でエールを送る保護者や塾の先生に間違われそうでした・・・でも、確実にいくならば、恥を忍んでもこちらを受けたほうが確実性が高く、その分の甲斐はあると思います。
<第1次筆記試験【問題】>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<第1次筆記試験【解答例】>(2004年~2019年)
http://www.hello.ac/his.kaitourei.2004.2019.pdf
<日本史の時代区分と各文化の特徴>
http://hello.ac/timeline.pdf
<特訓1800題>を使い倒せ!
http://blog.goo.ne.jp/gu6970/c/56e18e234050ec5f9ab991de649627c2
<一般常識>免除⇒2019年度(33点)自己採点
⇒今後のことを考えて2020年1月のセンター試験の現代社会を受験、90点取得。
もともと一般常識に出題される内容に関することは強かったので、過去問を解いて確認、ハローの傾向と対策、そしてハローから入手した観光白書を読み込んで臨みました。
当たり前といえば当たり前ですが、出題はやはり観光業界や観光関連、動向についての問題が多かったので、観光白書とハローの資料がとても役に立ちました。
こちらは合格したので迷ったのですが、今後のことを考えて日本史を受けるついでにセンター試験の現代社会も受験して5年分の免除をとりました。
センター試験の現代社会に関しては、対策として1冊にまとまった良い対策問題集がたくさんあり、私は書評を見て選んだ1冊をガッツリやって、あとは最新の情報だけアップデートする形でこの点数を取りました。
一般常識の問題は、問題数が少ないため間違うと損失が多いと感じられましたので、センター試験と傾向が変わらないとすれば、本試験よりは、共通テストで受験したほうが点数は取りやすいだろうと私は思います。
<第1次筆記試験【問題】>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<第1次筆記試験【解答例】>(2004年~2019年)
http://www.hello.ac/gen.kaitourei.2004.2019.pdf
<一般常識>の傾向と対策<決定版資料>
http://www.hello.ac/2020.gen.pdf
<令和2年年度観光白書(要旨)
http://hello.ac/2020.hakusho.gaiyou.pdf
<通訳案内の実務>(不明)
2019年度に受験した際に、おそらく一問の差で不合格となったと思われましたので、観光白書を読み込み、ハローの傾向と対策をきちんと網羅していけば試験対策としては間違っていないと思い、そのやり方を2020年度も踏襲しました。
ただ、2019年度は科目が多く、こちらに時間をあまりさけなかった自覚があったので、20年度は観光白書を隅々まで網羅し、関連法案が出そうだと予測し、関連法案の適応箇所をネット上からダウンロードしてチェックし、できる限り覚えました。
また、直前のハローの予想なども逐一チェックしてアップデートしていきました。2019年度に比べると、20年度の試験問題は難易度が上がったように感じました。問題量が増えた上に詳細なことまで出題していたので、隅々まで資料に目を通して覚えたことが役に立ったと思います。
問題数が増えたことで、試験時間がとても短く感じられ、見返すのも正直ギリギリでした。なので、来年度も今年度を踏襲した試験問題が出るとするならば、観光白書は流し読みせず細かいと思ってもきっちり読んで、法案に関しては重要な条文は暗記するくらいでいると、問題にもパッと答えられるのではないかと思います。
<第1次筆記試験【問題】>
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/18b0340041ceb26d8959b2c775736ffe
<第1次筆記試験【解答例】>(2018年・2019年)
http://www.hello.ac/jitumu.kaitourei.2018.2019.pdf
<通訳案内の実務>の傾向と対策<決定版資料>
http://www.hello.ac/2020.jitumu.pdf
<観光庁研修テキスト> → http://hello.ac/kankouchou.kenshuu.siryou.comment.pdf
③第2次試験対策
20年度の一次試験は通訳案内の実務のみだったので、一次試験は合格できるだろうとふんで9月から二次試験対策を行っているスクールに週一で通いました。
なぜならば、私は日常の機会において英語をアウトプットする機会が全くなかったためその必要があると思ったのと、あがり症の自覚があったのでとにかく人前で話すこと、ましてやプレゼンなど自己練習だけでは到底本番に耐えられないと思ったからです。
そのため、基本的にはスクールのカラキュラムに沿って準備を進めました。(スクールでは、プレゼン、通訳問題、シチュエーション問題の演習が網羅され、毎週、20近いプレゼン課題の宿題が出るので、授業日までにそれを自分で調べて文章をつくり、当たったテーマで発表していました)
プレゼンテーマは多岐にわたりますが、スクールで日本伝統文化、観光地、現代用語、等々とカテゴリーを分けて出題されたので、まずはそれらをこなし、関連するもので気になる事象ができたら都度、資料を読んで理解しプレゼンを作っていくようにしました。
2分間のプレゼンでは、150~200ワードのプレゼン内容が適切といわれましたが、私は英語でのプレゼンに慣れていない自覚があったので、プレゼンは100ワード+αくらいで確実に話せそうな長さで作成していました。
一番のネックは外国語訳で、逐次通訳をしたこともなかったので、スクールでの演習は役に立ちましたが私はそれでは到底足りていなかったので、いろいろ検索して試験に向けた逐次通訳の演習問題を出しているサイトをみつけ、そこから問題を入手して練習していました。
慣れてきてからは、2013年度くらいからの過去問をすべて人に録音してもらい、それを聞いて時間を図って通訳する練習をひたすら一人で行いました。
ハローの動画は、日常生活で動画を見ることに時間をさけない状況にあったので、音声のみ使用し、2次対策セミナーの音声を移動やちょっとした隙間時間にいつもイヤホンで聞くようにしていました。多岐にわたるテーマが取り上げられていたので、とても勉強になりました。
また、先生がご推奨されていたflashcardを購入、ダウンロードして単語、300選を寝る前に暗記時間として活用しました。
●プレゼンのテーマ
①一期一会
②熊野古道
③ラーメン(2018外国語訳)(←これを選択しました)
プレゼンは、「ラーメン」を選択しました。これは、スクールでも一度自分で作成していたものだったので、それを懸命に思い出してプレゼンしましたが、緊張のあまり記憶が飛んだりして自分としては不出来だったと思っています。
●私のプレゼン
内容:ラーメンの定義、スープの種類と説明、日本で独自の進化を遂げた料理であること、種類は色々あるがメジャーな3種は旭川ラーメン、喜多方ラーメン、とんこつラーメンであること、全国各地に美味しくて有名なラーメン店がたくさんあるので、それを食べるためだけに日本中を旅行するファンも多い、機会があったら是非食べてみてください、といったものだったと思います。

●プレゼンの後の試験官との質疑応答
(試験官)あなたはどのラーメンをおすすめしますか?
(回答)私は個人的に醤油ラーメンが王道で好きなので、先ほど話した喜多方ラーメンをおすすめします。現地までいかなくても、醤油ラーメンを食べることはできます。
(試験官)このあたりでおすすめのお店はあるかしら?
(回答)(大阪は私のなじみの土地ではないので全くわからなかったので)このあたりでは色々ラーメン屋さんがありますが・・・王将はどうでしょうか?チェーン店ではありますが、美味しいラーメンを提供していますし、よく見かけるお店ですし、値段も手ごろです。
●外国語訳の日本文(手洗い)
日本では神社にお参りする前に、身を清めるために、手水舎(てみずや)で手を洗います。元々、日本人はきれい好きで、よく手を洗いますが、小学校でも、子供たちに手をこまめに洗うように指導しています。特に今年は、新型コロナウイルスの流行を抑える一つの有効な手段となっていた。

<シチュエーション>
ショッピングセンターなどにハンドドライヤーや紙タオルがなかったので困った、という話だったので、
●外国語訳の後の試験官との質疑応答
(回答)
コロナの現状況下で、感染防止のためにハンドドライヤーなどが使えなくなってしまっています。しかし、日本人は子供のころから手洗いの習慣があって外出時にはハンカチやハンドタオルを持ち歩いているのです。
こんな状況なので、どこの公共施設においてもハンドドライヤー等は使えないと思いますので、ご提案なのですが、これを機に、ハンカチやハンドタオルをご購入するのはいかがでしょうか?
いろんなデザインのものがありますし、お土産にもなりますし、お気に入りのものが選べるのではないかと思います。
(試験官)それはいいですね。このあたりで買えるところはあるかしら?
(回答)この試験会場の近くでですか?
(試験官)そうよ、そう。
(回答)残念ながらこの近くには先ほど話したようなデパートなどのショップはないのですが、コンビニエンスストアがあります。日本のコンビニではハンカチやハンドタオルも売っているので、そちらで見てみるのはどうでしょうか?
「日本的事象英文説明300選」
https://blog.goo.ne.jp/gu6970/e/1c2c0c0d82c19d1e7ad24fda018d2154
「通訳案内の現場で必要とされるトラブル対応方法」
http://hello.ac/troubleshooting.pdf
<プレゼンテーション・外国語訳>質疑応答予想問題60題
http://www.hello.ac/yosou60dai.pdf
第2次口述試験対策<切腹鉄板予想問題70題>
http://www.hello.ac/teppan70.pdf
<2次セミナー>の資料と動画(2018年度受験用)
<2次セミナー>(その1)の資料 http://www.hello.ac/2018.10.14.2nd.seminar.koukai.pdf
<動画>
<2次セミナー>(その3)の資料 http://www.hello.ac/2018.11.17.seminar.conbined.pdf
<動画>
<2次セミナー>(その1)の資料 http://www.hello.ac/2018.10.14.2nd.seminar.koukai.pdf
<動画>
<2次セミナー>(その3)の資料 http://www.hello.ac/2018.11.17.seminar.conbined.pdf
<動画>
④ハローのセミナー、メルマガ、動画、教材などで役に立ったこと
動画を拝聴する時間はとれませんでしたが、二次対策では特に<特訓セミナー>の音声とフラッシュカードをフル活用しました。
また、直前に入りました二次試験対策専用メルマガにおいて先生が公開してくださる情報はすべてチェックし、過去問頻出の本もハローから購入して対策にあて、先生が予想された箇所に関してはすべてチェックして
何度も確認をしました。
私は午後からの受験だったので、試験会場への移動中に当日の試験速報もチェックして、みんな頑張ったんだ・・・と思い自分を奮い立たせました。
先生のきめ細やかなメルマガにはどれだけ励まされたかわかりません。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
※(ご参考)第2次口述試験受験対策専用メルマガのバックナンバー
https://e7.wingmailer.com/wingmailer/backnumber.cgi?id=E660
⑤今後の抱負
現状がいつまで続くかわかりませんが、合格したと言ってもスキルが全然足りていないのはよくわかっているので、まずは自分の思いや説明すべき事象を正確に英語で伝えられるスキルを上げる練習を続けていこうと思っています。
そして、研修などにもできる限り参加してスキルを身に着けて、願わくば今年、もしくは来年にはお相手が一人でもガイドデビューできたらと思っています。
この試験勉強を通じて、日本文化の良さをたくさん発見できて自分でも面白かったと思ったので、
そういった思いをお客様に持ってもらえるようなガイディングができるようになり、体力が続く限り続けていきたいと思っています。
以上