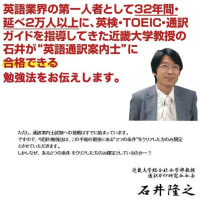2019年度<合格体験記>(5)(中国語)
「ハローの教材を基本に勉強しました!」
●中国語(メルマガ読者、無料動画利用者、教材利用者)
①受験の動機
恥ずかしい動機ですが、友人が数年前にトーイックで800点少しの点数を取り、「もう少しで通訳案内士の一次試験が免除になる点数だった(当時は840点)」と話しているのを聞いて、え、そんなに簡単なの、とびっくりし、それなら中国語で取ってみようと思ったこと。
②第1次試験対策(各科目毎に、他の受験者に参考になるようにできるだけ詳しくご記入ください)
<中国語> → 免除
免除条件を調べるとHSK6級180点以上、とあったので過去問などをして受験してみたところ194点とれた。本当のところは240点目標、210点はほしいと思っていたので不満はあったが、とりあえず免除になったので、ま、いいかと受験はこの1回のみ。
中検1級も免除だが、こちらは通訳案内士所の難しさどころではないといううわさだったので、HSKに。日本人だと読解や作文などかなり有利に受けられる。
<日本地理>(免除) →昨年合格。昨年はハローの教材と白地図、地図帳を使用した。かなり不安だったが、80点程度とれた。
<日本歴史>(免除) →センター試験8割程度。高校では世界史をとり、受験も世界史。日本史は留年寸前の成績でした。社会人になってから、司馬遼太郎、吉川英治などの小説を愛読するようになり、ほぼその知識で受験。過去問は数年分した。
<一般常識>(免除) →昨年合格。8割程度。センターの現代社会を受けたが、7割余りで免除にならず。ハローの予想問題を中心に勉強。仕事で総務関係の仕事をしていた時期があり、その知識が役立った面も。新聞などにも目を通した。
<通訳案内の実務>(免除)昨年合格。ハローの資料と環境省の研修資料を数回読み込んだ。45点程度とれた。初めてと言うこともあり、簡単だったのかと感じた。
③第2次試験対策
昨年は撃沈。記憶の限りだと中国語訳はすごくあやふやなことしかいえず、3題から一つ選ぶものでは、太陽光発電を準備していたにもかかわらず、なぜか準備をしていなかった除夜の鐘を選び、30秒も話すとなにも言えなくなり、その瞬間に終わったと感じた。なぜ除夜の鐘を選んだのかと、帰り道後悔しきりだった。おそらくあがっていたのだろう。
今年はカプセルホテルを選択。こちらは一応は前もって文章を作ったことがある題材。なんとか形にもっていけた。中国語訳は花火がどうのこうの、といった内容。花火を中国語でなんというかとっさにでてこず焦った。それでも3分の2くらいはなんとか訳せた。ただ途中で「いさぎよさ」を訳せなくなり、そこでギブアップ。後から思えば、説明調でもいいから何かいえたはず、とこちらも後悔。その後の質疑応答では、花火を見に行ったが人が多すぎて見られない、どうしますか、という内容。少し遠くの離れたところに案内するから、そちらで、というようなことを答えた。試験官からは「どうしても近くで見たい」と言われたが「危ない、迷子になったりけんかに巻き込まれたりしたらどうするの」とか答えた。
試験官は昨年と同じ方(大阪会場)。昨年は少し怖そうに思えたが、今年は優しそうな方に感じた。合格する自信はなかったが、やはり出来が昨年よりは良かったのかも。
勉強は、とりあえず100位の題材を自分なりに中国語に訳し、それをオンライン中国語の先生にみてもらって直してもらった。昨年はとりあえず100程度を訳し、本番へ。今年は新しいものは作らず、100をブラッシュアップしたのみ(時間が余りなかった)。あと、今年は1からと思い、発音の勉強を初心者になってやり直した。これがよかったのかも、と感じている。今年だめだったら、もう一度地理や一般常識などの勉強をする気力がおきず、あきらめようと思っていたので、合格した時は本当にうれしかった。
④ハローのセミナー、メルマガ、動画、教材などで役に立ったこと
地理はハローの教材を基本に、少し古い部分は自分なりに更新して勉強した。地図帳をかたわらにおいて、ハローの白地図なども参考にした。
一般常識もハローの教材や直前予想を中心に勉強した。
実務もハローの教材が頼りになった。
その他二次の勉強の進め方など非常に参考になった。
⑤今後の抱負
とりあえず定年になったら本格的に通訳で食べて生ければと考えています。あと数年、可能なら英語もとりたいです。
中国語のブラッシュアップももちろん続けていくつもりです。
以上