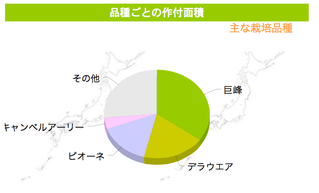海藻の話も海藻学の話も面白い。今日は、日本の海藻学の
草分けというか開拓者として活躍した岡村金太郎(1867-
1935)のこと。
明治期に東京大学に入学以来、46年間海藻研究まっしぐら。
日本の海藻の約半数の正体を明らかにしたそうなんだけど、
その植物図というのか海藻図がとても美しい。
国立科学博物館のサイトには、その原画が345枚保存されて
いて、数十枚はネットで見ることができる;

アナダラス(マサゴシバリ目)

ウスバアオノリ(アオサ目)

ツルアラメ(コンブ目)
植物画としても一級品だそうだ。1907年から1937年に
かけて執筆した『日本藻類図譜』として出版。関係者に
とって未だにバイブルとか。制作費の関係から白黒印刷。

明治期に菌類の世界で活躍した南方熊楠(1867 -1941)
の『菌類図譜』を彷彿すると思ったら、二人は同い年。
熊楠の方がちょっと長生きしたみたい。

二人は手紙のやり取りもしていたみたいで、植物の危機
について憂いていたそうだ。
草分けというか開拓者として活躍した岡村金太郎(1867-
1935)のこと。
明治期に東京大学に入学以来、46年間海藻研究まっしぐら。
日本の海藻の約半数の正体を明らかにしたそうなんだけど、
その植物図というのか海藻図がとても美しい。
国立科学博物館のサイトには、その原画が345枚保存されて
いて、数十枚はネットで見ることができる;

アナダラス(マサゴシバリ目)

ウスバアオノリ(アオサ目)

ツルアラメ(コンブ目)
植物画としても一級品だそうだ。1907年から1937年に
かけて執筆した『日本藻類図譜』として出版。関係者に
とって未だにバイブルとか。制作費の関係から白黒印刷。

明治期に菌類の世界で活躍した南方熊楠(1867 -1941)
の『菌類図譜』を彷彿すると思ったら、二人は同い年。
熊楠の方がちょっと長生きしたみたい。

二人は手紙のやり取りもしていたみたいで、植物の危機
について憂いていたそうだ。