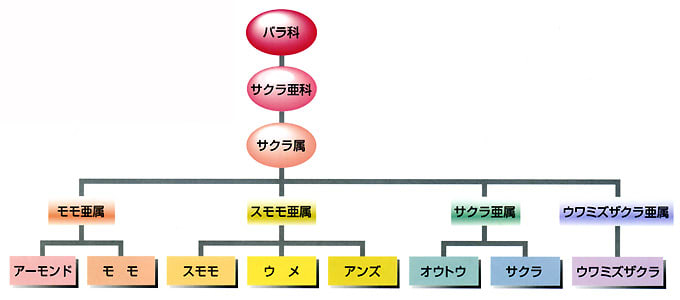スーパーの紀伊國屋で、りんごの試食をやっていた。8種類
のりんごが切ってあったので、そそられた。順番に食べて
いくと違いがわかる。
新しい品種「紅いわて」がとても美味しかった。りんごが
出回るには、ちょっと早いから、この時期においてってこ
とだけど。

硬さがあって噛みごたえがあり、甘いけど適度な酸味があ
る。岩手のりんごは「ふじ」が主流だけど、出荷時期が遅
いので、9月下旬に成熟期を迎える優良品種の開発を行った
そうだ。
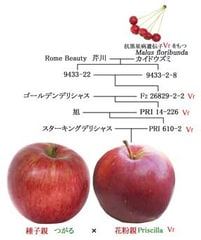
岩手県農業研究センターによる開発で約20年。そう簡単にはで
きないんやね。
出荷が始まったのが2011年というと、すごい促成栽培が可
能なのかって思うと、種から育てるのではなく、接ぎ木で
栽培するそうだ;

IBC岩手放送の番組より。2012年10月。写真も。
なるほど。それで、いろんな品種が生まれているわけだ。
千秋、秋陽、秋映なんて、初めて見るような林檎をこの
時期スーパーでみかける。
☆
「紅いわて」が「ふじ」より優れているのは、褐変しに
くい特徴があるとか。すりおろした比較写真がわかりや
すいし、なんか印象的な写真。数十分位では殆ど色の変
化がなさそう。「ふじ」はすぐ変わってる。

皮を剥いたらすぐ食べたから、色の変化は気にならないw
千雪って品種は1日たっても色に変化がないとは。いろいろ
食べて、好みを見つけたい。
のりんごが切ってあったので、そそられた。順番に食べて
いくと違いがわかる。
新しい品種「紅いわて」がとても美味しかった。りんごが
出回るには、ちょっと早いから、この時期においてってこ
とだけど。

硬さがあって噛みごたえがあり、甘いけど適度な酸味があ
る。岩手のりんごは「ふじ」が主流だけど、出荷時期が遅
いので、9月下旬に成熟期を迎える優良品種の開発を行った
そうだ。
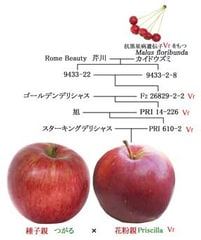
1991年に「つがる」×「プリシラ(推定)」を交雑した
種子からの実生を元に、接ぎ木を重ね、2000年に初結実
したもののなかから選抜。2009年に品種登録。
種子からの実生を元に、接ぎ木を重ね、2000年に初結実
したもののなかから選抜。2009年に品種登録。
岩手県農業研究センターによる開発で約20年。そう簡単にはで
きないんやね。
出荷が始まったのが2011年というと、すごい促成栽培が可
能なのかって思うと、種から育てるのではなく、接ぎ木で
栽培するそうだ;
リンゴの品種改良が盛んに行われるのは、接ぎ木技術が
進歩しているからだそう。千葉さんも接ぎ木した翌年に
は「紅いわて」を収穫することができたといいます。
進歩しているからだそう。千葉さんも接ぎ木した翌年に
は「紅いわて」を収穫することができたといいます。

IBC岩手放送の番組より。2012年10月。写真も。
なるほど。それで、いろんな品種が生まれているわけだ。
千秋、秋陽、秋映なんて、初めて見るような林檎をこの
時期スーパーでみかける。
☆
「紅いわて」が「ふじ」より優れているのは、褐変しに
くい特徴があるとか。すりおろした比較写真がわかりや
すいし、なんか印象的な写真。数十分位では殆ど色の変
化がなさそう。「ふじ」はすぐ変わってる。

皮を剥いたらすぐ食べたから、色の変化は気にならないw
千雪って品種は1日たっても色に変化がないとは。いろいろ
食べて、好みを見つけたい。