平成6年2月27日の事でした。
あの頃は、長男次男とも私立大学に進学して、
授業料の足しになればと、薬剤師の現場に復帰していました。
東洋医学会の創生期の先生が
日大の木村雄四郎先生であった事も幸いして
臨床現場の漢方薬の効果を拝聴することで、
自分の仕事に役立てるつもりで、
出席参加を許可される講習会や学会には参加していた時期でした。
中国の四大中医学院の交流にも参加の機会を得ました。
成都の生薬市場では、そのころは北京大学の先生方が
価格や、生薬の品質ランキングに絶大な決定権を持っておられる時期でした。
日本の病院の方が、滅菌感覚が厳しく管理されていて
医療機械の新世代の物も見当たらない時代だっただけに
漢方薬は
「各臓器でのプロドラックとなってデリバリーされる」のではないかと
薬理的な解明が主流のような情報でした。
しかし日本の医師と合同の地方会などでも
医師の方から、漢方と免疫のかかわりは
臨床例としてしばしば聞く機会があった時代でした。
湯液を主流に学んできた薬学の漢方から
ツムラや小太郎から、又、鐘紡から
エキス剤が発売されてからは
日本の漢方は
医師の手によって
臨床に使われてゆくことが
当たり前になったころ
東洋医学会の北海道支部が「教育講演会」を開催していました。
その中の講演の3番目に「免疫と東洋医学」というテーマで
菊地幸吉先生が講演をされました。
免疫学は昭和42年に大学入学した当時は
かなり、遅れていたと思いますが、
卒業後、大学病院で働くようになったとき
自己免疫と自己免疫疾患の患者さんに出逢う事が多くなりました。
新参の新卒の薬剤師だったころ、当直があるのですが
夜中に40剤もあるのに、一人で調剤するのです。
翌朝昼まで仕事をして、昼から帰るのですが
寝る暇がないため、当直の夜は、大変でした。
処方と病名を
眠気の中で覚えながら
自己免疫疾患という、標的を自分自身に向ける「免疫」は
私にとっては興味の深い謎でした。
橋本甲状腺炎
原発性粘液水腫
甲状腺中毒症
悪性貧血
自己免疫性委縮性胃炎
アジソン病
早発性閉経
インスリン依存性糖尿病
グッドバスチャー症候群
重症筋無力症
男性不妊症
尋常性天疱瘡
類天疱瘡
交感性眼炎
水晶体原性ぶどう膜炎
多発性硬化症(?)
自己免疫性溶血性貧血
特発性血小板減少性紫斑病
特発性白血球減少症
原発性胆汁性肝硬変症
活動性慢性肝炎(HBs抗原陰性)
特発性肝硬変症(一部)
潰瘍性大腸炎
シェーグレン症候群
慢性関節リュウマチ
皮膚筋炎
強皮症
混合型結合組織病
板状紅斑
全身性エリテマトーデス(SLE)
器官特異的から非器官特異的に並べられた疾患を
写真と突き合わせながら
勉強したものでした。
あれから、「免疫学」が目覚ましい発展をして
私のおそまつな勉強では「本の意味も解らなくなってきました。」
実験室向けには「モノクロナール抗体」が飛び交うようになりました。
そのころ、インターフェロン(INF)の抗ウイルス作用が
脚光を浴びていました。
記憶を辿ると、走馬灯のように、免疫という謎に向かう時代だったと思います。
現代のように
イムノクロマト法で各種の迅速診断キットが販売される時代が来るなんて
信じられませんでした。
RSウイルスやアデノウイルス、マイコプラズマ、ノロウイルス
ロタウイルス、肺炎球菌 レジオネラ、、、ピロリ菌に ヒトメタニウモウイルスと
まるで迅速診断キッドの宣伝に使われる時代となりました。
ともかく、、、、菊地先生が、コロンブスのアメリカ大陸に上陸したような
足元からの実感を感じる講演をなさったことが、
私的には、眼から鱗の感動となって心に残りました。
思いでは、、、20年以上も前のセンタービルの23回から始まります。
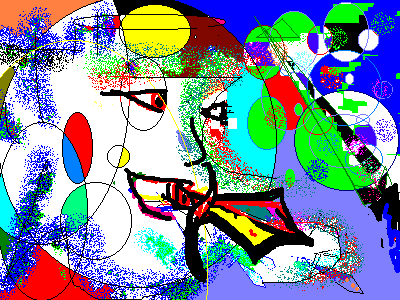
「免疫学と東洋医学」というテーマで講演されるというので
聴きに行きました。
あたらしい免疫の考え方として
免疫系には「物質を認識して自己と非自己を区別する能力がある。」
と、話されました。
その仕組みは複雑であり、神経細胞(140億)の100倍の数の
リンパ球(T細胞、B細胞、とNK細胞)が自由に移動して
リンパ球同士、他の種々の細胞と接触して
シグナルを伝達し合っている。
でたらめではなくて、Ig(抗体)
T細胞抗原レセプター(TCR)
主要組織適合抗原系(MHC産物)
これらによって特異性が規定されている。
そして、、、IgとTCRについて
免疫反応の特異性について話されました。
あれから、高校と大学まで同級だった友人が
生薬学教室から「免疫のジャンルの論文を仕上げて、
薬学生でしたが、「医学博士を取得しました。」
免疫学は日進月歩の進展を見せて、
臨床畠で働いている薬剤師も、東洋医学を勉強中の学友も
免疫には、目から鱗の視点を啓蒙されました。
菊地先生の講義には
ご自分でスケッチされたような絵で
MHC分子と
抗原エピトーブ
T細胞レセプター(TCR)の結合の絵に、
さらに
T細胞とAPC結合を増強させるアクセサリー分子の結合の絵が
パンフレトにして配布された。
平成6年、、、つまり1994年の事であった。
あれから25年も月日は経った。
免疫学は、宇宙ロケット並みに発展を続けていったことだろう。
明日の、北大アカデミーの免疫学の講演は理解できないかもしれないが
25年前の菊地先生の名講義を思い出しながら、
現代の免疫のインターロイキンの
遺伝子構造の判明したプロセスなど
盛沢山の人間と病気と、遺伝と、免疫の話をきってくるつもりですが、、、
案外、アカデミーという講演会であっても、
おもしろおかしく、わかりやすい「文化講演」に
アレンジして、楽しませてくれるのかもしれない、、、などと
明日の非日常の家庭雑事からの脱出で
ボケ防止と、私自身が居る時間を大切にしたいと思っている。
単身赴任から札幌に帰還した主人の為に、
私は仕事を辞めて専業主婦に戻った。
朝から晩まで、三度の食事と、洗濯買い物に追われて
免疫からは、それっきりになっていた。
最近になって、
人生は単純作業だけでは
ボケてしまうと思うようになった。
外科医になってから身に付いたのか、、、?
もともとが、合理的な性格なのか?
付き合って結婚した相手ではないので、
主人の30歳前の性格はわからないが、
多くの男性医師がそうであるように、
仕事第一主義である為、
医師以外の仕事は一切、、、他山の石のごとく
無関心なので、
主婦は雑用に追いかけまわされてしまう結果になる。
ふと気が付くと75歳が目前に迫っている。
貴重なこの世の、自分自身の時間である。
これは「私自身の日記帳であるから」
今日は、自分ファ―ストの文になってしまった。
自分の為に、、、、書いた記録です。

授業を受けてきました。
私的な感想かもしれませんが、、、感謝の心が湧いてきました。
行ってまいりました。
北大アカデミー!
視聴覚教育の、ゆきとどいた、
スライドの楽しい漫画チックな画面で
アカデミックな内容の講義が楽しかったです。
難解な免疫の講演が、
わかったような気がするほど
解りやすい
愉快な展開が、
次々と進んで、楽しかった。

昭和42年卒業の私たちの時代の講義は
教授目線で、黒板に次々と書かれる文字を見ながら、
チンプンカンプンのまま、ノートをとって、
後で、自習で謎を解くようなことが多かった。
あれから50年経過した。

北大の階段教室で、75歳の婆ちゃんは
たった、一時間半で、免疫の事がわかった気になりまして。
素晴らしい講演でした。
8時に講義が終わり、真っ暗になった北大構内を歩いて
地下鉄の駅に着くころ、
やっと現実に戻りました。
いくつかの授業を受けましたが
今日の一日があることで
私の探していた、物が見つかったような気がしました。
北大生は、幸せだと思いました。
心憎いほど、、、生徒の目線でわかりやすく
難解な免疫を、好きにさせてくれる
授業だったと思いました。
感謝!









