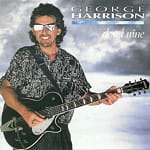Foriegner のヴォーカリストとして数々のヒット曲を放ってきた Lou Gramm がリリースした初のソロ・アルバム。勿論、当時は Foreigner というバンド名を知っているはずもなく、ヒット・チャートを賑わしていたシングル曲 "Midnight Blue" が MTV で繰り返しオン・エアされていたのが Lou Gramm を知ったキッカケです。アルバムは抜群の歌メロを持つ "Midnight Blue" を筆頭にメロディアスながらもソリッドなロックが詰まった好盤です。私のお気に入りは "Time", "Heartache", "Ready Or Not" と、何故かアナログでいう A面に集中しています(笑)。昔は同じく A面、B面があるカセット・テープが主流だったので、どうしても片面だけ聴きまくるということが往々にしてあったものです。現在ではレコードやカセットは現役を退いていますから A面、B面という概念さえほとんど忘れ去られてしまいましたね。このアルバムは何分のテープで録音できるとか、そんなことをしていた時代が懐かしいです。テープ選びだって CD ならまだしもレコードの場合は自分で曲の合計時間を計算しなければならなかったですからね。ちなみに私は曲順を入れ替えてでも短いテープで録音する派ではなかったです。流石にそれは邪道だと思っていたので(笑)。
Foriegner のヴォーカリストとして数々のヒット曲を放ってきた Lou Gramm がリリースした初のソロ・アルバム。勿論、当時は Foreigner というバンド名を知っているはずもなく、ヒット・チャートを賑わしていたシングル曲 "Midnight Blue" が MTV で繰り返しオン・エアされていたのが Lou Gramm を知ったキッカケです。アルバムは抜群の歌メロを持つ "Midnight Blue" を筆頭にメロディアスながらもソリッドなロックが詰まった好盤です。私のお気に入りは "Time", "Heartache", "Ready Or Not" と、何故かアナログでいう A面に集中しています(笑)。昔は同じく A面、B面があるカセット・テープが主流だったので、どうしても片面だけ聴きまくるということが往々にしてあったものです。現在ではレコードやカセットは現役を退いていますから A面、B面という概念さえほとんど忘れ去られてしまいましたね。このアルバムは何分のテープで録音できるとか、そんなことをしていた時代が懐かしいです。テープ選びだって CD ならまだしもレコードの場合は自分で曲の合計時間を計算しなければならなかったですからね。ちなみに私は曲順を入れ替えてでも短いテープで録音する派ではなかったです。流石にそれは邪道だと思っていたので(笑)。