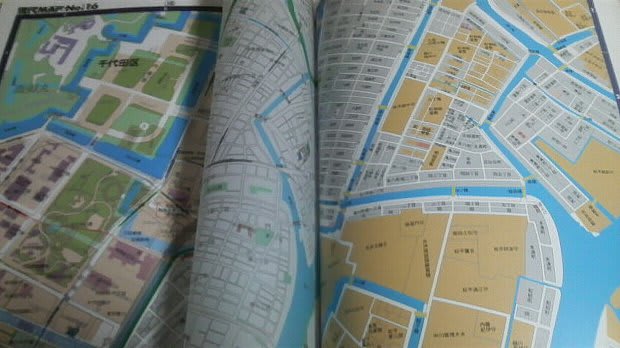幕末ファンの人、とりわけ坂本龍馬ファンの人たちにとっては
けっこう衝撃的なニュースではないでしょうか?
伏見の旅籠・寺田屋は再建されていた!
坂本龍馬や薩摩藩士とゆかりの深い、伏見の寺田屋は幕末当時のままの
建築物で龍馬が泊まった部屋(龍馬が襲われた時の刀痕があるとしている)なども
そのまま保存されているとして、龍馬ファンからは聖地のようにされていた
現在も泊まれる旅館ですが、龍馬死後に起きた鳥羽伏見の戦いでどうやら
焼失していて、その後の再建のようですね・・・。
一言・・・残念ですね。
けっこう衝撃的なニュースではないでしょうか?
伏見の旅籠・寺田屋は再建されていた!
坂本龍馬や薩摩藩士とゆかりの深い、伏見の寺田屋は幕末当時のままの
建築物で龍馬が泊まった部屋(龍馬が襲われた時の刀痕があるとしている)なども
そのまま保存されているとして、龍馬ファンからは聖地のようにされていた
現在も泊まれる旅館ですが、龍馬死後に起きた鳥羽伏見の戦いでどうやら
焼失していて、その後の再建のようですね・・・。
一言・・・残念ですね。